�w�������z2�x��2��
�Ñ�̉���--�V�i�C�̎R�̗h�ꂵ�Ƃ�
��B�ɖ�����
�@�@�@�@�l�n�̍s���������ɐ������
�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�@�@�@�@�@�@�@���̍��A�����̔@���@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�C���N�̂Ƃ��@���獻��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ӍݍY
�V�i�C�̎R�̗h�ꂵ�Ƃ�
�@�@���[�[�ɗ������āA�G�W�u�g��E�o�����C�X���j���̖������́A�O�J���߂ɃV�i�C�̎R�ɓ����� ,�����Ő_�̏\�������������B�w�����x�́u�o�G�W�v�g�L�v��\��͂ɂ͂��������Ă���B�u�O���ڂ̒��ƂȂ��āA���݂Ȃ�ƁA���Ȃ��܂ƌ����_�Ƃ��A�R�̏�ɂ���A���b�o�̉����A�͂Ȃ͂������������̂ŁA�h�c�ɂ��閯�݂͂Ȑk�����B���[�[������_�ɉ�킹�邽�߂ɁA�h�c���瓱���o�����̂ŁA�ނ�͎R�̂ӂ��Ƃɗ������B�V�i�C�R�͑S�R�������B�傪�̂Ȃ��ɂ����āA���̏�ɍ~��ꂽ����ł���B���̉��́A���܂ǂ̉��̂悤�ɗ������A�S�R�͂������k�����B���b�p�̉����A���悢�捂���Ȃ����Ƃ��A���[�[�͌��A�_�́A���݂Ȃ�������āA�ނɓ�����ꂽ�v
�@�@���̃V�i�C�̎R�Ƃ͂��������ǂ��Ȃ̂��B�`���I�ȏꏊ�Ƃ��āA�ꉞ�A�W�F�x������[�T(���[�T�R)�Ƃ���Ă��邪�A�����l�Êw�҂̊Ԃł��c�_��������肵�Ă��Ȃ��i����1,2�j�B
�@���Ƃ��Ύ��̂悤�ȉΎR��������B�u�ΎR�������Î�����p��ɂ��A�_�̌[�����q�ׂĂ���B���̂��Ƃ���A����w�҂����́A�V�i�C�R�����Β��̉ΎR�ł������ƌ��_���A�ΎR�₪���݂���A�J�o�p�̓��́A�k���A���s�A�Ɉʒu�Â����B�����������̓V�i�C�����̊O���ɂ��邾���ł� �Ȃ��A�G�W�v�g���牓������B�V�i�B�R�́A�V�i�B�������̓`���I���ꏊ�A�W�F�x������[�T�̋ߕӂɈʒu�Â���ׂ��ł���A���Β��̉ΎR�Ɨ��ɂ��_�����̕`�ʂ́A�ŏ��̓`���ɑ�����H�Ƃ��ĕ���̒��Ɏ������ꂽ�ƍl����ق����悳�����ł���v
�@�����w�҂̂��̌�����O���ɂ����Ȃ���A������x�A�O�L�w�o�G�W�v�g�L�x�̋L�q���������Ă݂�ƁA�ǂ����[���̂��������_���o�Ă���B�R���k���A���b�p�̉������A���݂Ȃ肪��B���̎O���ǂ����т���̂�?�Ƃ��낪�A�����������ۂ́A���ꂩ���A����ǂ��ďq�ׂ�悤�ɁA���������܂悤�l�X�ɂ́A���܂˂��m���Ă����厩�R�̉��ٌ��ۂł������B����ꂪ�ΎR�○�ɋ��ق�������Ɠ����悤�ɁA�Ñ�l�ɂƂ��Ă͐_�����̕`�ʂɂ͓K�Ȃ��̂ł������B���낢�낽�����ɓ����悤���b���o�Ă���̂ł���B
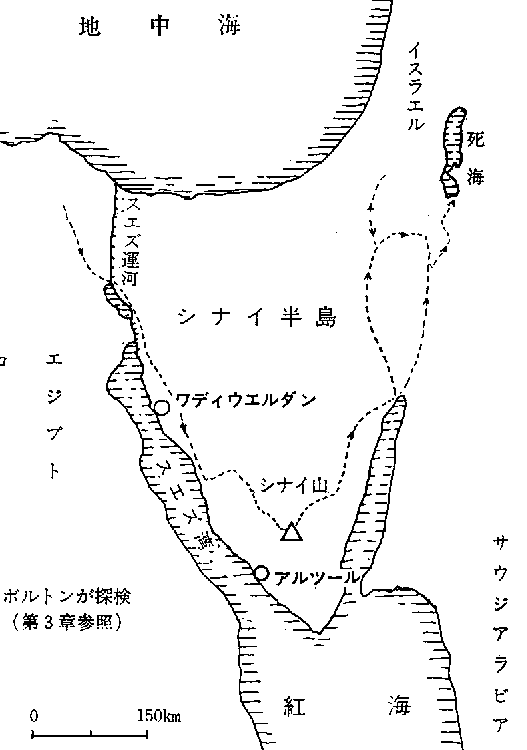
�}2-1�@�V�i�C����-���̎R�iJebel Nagous)�́w�o�G�W�v�g�L�̃C�X���G���тƂ����������x
���̎R�E�W�F�x����i�N�[
�@�@�Â�����A�V�i�C�����̃��[�T�R�t�߂𗷂����l�X�̊ԂɁA�s�v�c���b���`�����Ă����B������R������Ƃ����̂ł���B�A����c�[���̋߂��ɂ��邽���̍��R�����A�Ƃ��ɑ傫�ȉ�����B�����ɏZ�ރA���u�l�����́A�n���ɖ����ꂽ�C���@�������āA�m�����C���m�������ĂяW�߂邽�߂ɏ�(�i�N�[)��炵�Ă���̂��ƐM���Ă����B���̎R�̖����u���̎R(�W�F�y��.�i�N�[)�v�Ƃ����B�@�@
�@19���I�̏����A�����l���̉Ȋw�҂��������̏ꏊ��K��A���̐��̂��𖾂��悤�Ƃ����B���̋L�^�ɂ��Ɓi����3,4�j�A���̕t�߂ɂ͒Ⴂ����̋u�˂������Ă���(���̍��₪���̃��[�c�Ȃ̂���)�B����30���[�g���قǂ́A�݂ɗՂ��ق������₪����A�����ŁA�Ƃ�����A������������������B���V���̔����w�҃[�[�c�F�\(1767-1882)��1810�N�ɂ�����K�ˁA���̂悤�ɏq�ׂ��B
�@�@�u���̉��́A���߂̓A�C�I���A�\��n�[�v�i��1�j�̒��ׂɎ��Ă���A���ɂ͒���̓Ɗy�i���܁j�̉��ɕς�A�Ō�ɂ͔��ɍ������ɂȂ��đ�n��������B���̉��̓M���V���̏C���@�ŏ��̑��ɂ�����y��̉��Ɏ��Ă���v
�@�@���̕s�v�c�ȉ��̌����ɂ��āA�[�[�c�F�\�́A������������̕\�ʂł����邽�߂ł��낤�ƍl�����B1818�N�ɂ̓O���C�Ƃ������s�҂����̉��������A�ނ͋߂��ɉ����邩��A�Ȃɂ��ΎR���̂��̂��낤�ƍl�����B�����1823�N�ɂ̓G�[���\�x���N(�j���������Ԃ���Ă��̒n��K��A���킵���ώ@�������B�ނ͂��̋u�̉����璸��܂œo���Ă݂��Ƃ���A�ꑫ���Ƃɉ������B�܂����ʂ̍����Ζʂɉ����ė���������ƁA���߂͐Â��ȉ������A����ɍ������ɂȂ�A�Ō�ɂ́A�����ő�C�������Ă���悤�ȁA�����ׂ��傫�����ɂȂ�B���̉��͂܂��A���̍��u�������ē���������Ƃ��ɂ��N���邵�A�܂����������������č������Ă����������o��B�Ȃ��A�����̍��͓����ȐΉp�ł������Ƃ������Ă���B���̌�������̐l�X�����̒n��K�ˁA�s�v�c�ȉ��̌����Ƃ��̗l��������ɉ𖾂���Ă������B���̏ꏊ�Ƃ����A���̉��̋����ׂ��傫���Ƃ����A�܂��Ɂu�o�G�W�v�g�L�v�̋L�q�Ƀs�b�^���ł��邱�Ƃ��܂��܂��T���҂����̋��������������̂ł���B�ڍׂ͎��͂ŏq�ׂ邱�Ƃɂ��āA���̑O�ɁA�����A�W�A�̍����ɂ́A���ɂ��悭�������ۂ��Â�����m���Ă������Ƃ��Љ�邱�Ƃɂ��悤�B
�����̒J�c���O�������
�@�}���f���B���́w�������s�L�x�i����5�j��14���I�̗L���ȓ��m���V���s�ē��L�ł��B���ˋ�I���s�L�����A���ꂪ�����l�𓌗m�ւ̌��z�ɋ�肽�āA���m���s�S���������B���̂Ȃ��ɁA����Șb���o�Ă���B
�@�u�댯�ȒJ�Ԃ̈����̎�B�[�v���X�^�[��W�����̉������班�������̃s�\���͂��̂Ƃ���ɂ́A���ɂ��ӂ����Ȃ��Ƃ�����B�Ƃ����̂��A�ӂ��̎R�ɂ͂��܂�āA�S��4�}�C��������k�J������A����l�X�͖��@�̒J�ƌĂсA�܂����ɂ́A�����̒J�Ƃ��A�댯�ȒJ�Ƃ��ĂԂ��̂�����B���̒J�ԂŁA���Έ�Ζ钋�̕ʂȂ��A����ȁA�����Ƃ���悤�ȑ�������������B���ɂ́A�劯�A�̋����ł��Â���Ă��邩�̂悤�ɁA���b�p��召�̑��ۂ̋����̂悤���������ɓ���B���̌k�J�ɂ́A�����Ă���ɂ����ł��������A���ł����������悤�悵�Ă���̂ł���B������y�n�̐l�X�́A�n���ւ̓������Ƃ����v
�@���̕|�낵���b�͎��ɔ��͂ɕx�݁A���̗��s�L�̂Ȃ��ł��ł��ʔ����Ƃ���.�ЂƂ��Ƃ���Ă���B�����}�\�f���B���͎����ł͗��s�����A���낢��ȗ��s�L���܂Ƃ߂āA�܂�Ō��Ă����悤���ˋ�̓Ǖ����������l�ł���i����6�j�B�u�����̒J��v�̎�{�́A14���I���߂ɏ����ꂽ�I�h���R(12651331)�̓��m���s�L�x�i����7�j�ł������B������͂������Ɋm�����������Ղ�ł���B.
�u�������y�̉͂̉͏�ɂ���k�J��i��ł������Ƃ��A�����̎��[�������̂ł���B���͂܂���X�̉��y�����ɂ������A���ɕs�v�c�ɑt�����Ă������ۂ̋����Ƒ����Ƃ́A���ɑ傫���āA�ő�̋��|���P�����������B���̌k�J�́A7�A8�}�C���͂���A�����N�������̒��ɗ������߂ρA�����ďo��ꂸ�A�����Ɏ���ł��܂����낤�B���̂悤���댯�Ȍk�J�ł����Ă��A���͂�������߂邽�߂ɒ��ɂ͂��錈�S�������B�����ŁA�����҂łȂ���ΐM�����ʂƎv����قǑ����̎��[�������̂������B���͂��������������A���Ɍk�J�̑��̒[�ɏo���B�����Ĉ���̍��R�ɏ��A������������������������A�����s�v�c�ɖ炳��Ă��鑾�ۂ̉����݂̂������v
�@���̘b�ɂ��āA��҂͎��̂悤�Ȓ��߂����Ă���B�u�I�h���R�̋L�q�͎��ۂ̑̌��ɂ�������̂ɂ������Ȃ��B�ނ������̂ق�Ƃ��̋��|���o���������Ƃ͖����ŁA���[��(�I�h���R������)�̌��ɂ��A���̌k�J�́A���Ԃ�I�h���R���`�x�d�g�w�ނ����r���ɉ��f�����q���Y�[�N�V�n���A�A�t�K�j�X�^���̎�s�J�u�[���̖k��40�}�C���̂Ƃ���ɂ��郌�O�������(Reg-Rawan)�̂��ƂŁA�܂��A��т̉͂̓p�\�V�[��(Panschir)�͂̂��Ƃł��낤�Ƃ����v
��Ƃ���Ŗ��̕s�v�c�����ɂ��āA��҂́u�����A�W�A�̍����ɂ����闬���̈ړ����A���̂���߂����ɂ����̂ł��낤�v�Ə����Ă��邪�A�͂����Ă����ł��낤���B���̉́A���܂���100�N�O�A���łɃj���[���[�N�Ȋw�A�J�f�~�[�ŕ���Ă����B�����.���ƁA���O���������1837�N�ɃA���L�T���_�[��o�[���Y�����K��A�O�L�V�i�C�����̏��̎R�Ɠ������̎R�ł��邱�Ƃ��m���߂Ă���̂ł���B
�@
�����̉���
�@�@�V�i�C�����́u���̎R�v�A�A�t�K�j�X�^���́u�����̒J�v�A���̂ǂ�������͍̂��������B����Ȃ���܂����̍����ɂ́A�ق��ɂ������傤�����ۂ�����ɂ������Ȃ�o�w���镨��x�́A�A���s�A�����ɏZ�ތÂ�����̐l�X�̑̌����A���邢�͌֒�����A���邢�͏��F����āA�܂��Ƃ��ɂ͒������ό`����ē`�����Ă���B���͕s�v�c�ȉ����錻�ۂ̕З����߂āw���镨��x��ǂݒ^��A��492��Ɏ��̂悤�Ȉ�߂������邱�Ƃ��ł����i����8�j�B
�@�u�������ĎR�X���z���A���܂��̍�����n���ė����Ă���܂��ƁA������o�����������ƉQ��������̂�ڌ����܂����B����ŁA���̍����̕����i��ł������u���[�L�[���[�́A�����⌕�����ł������A�����܂����ǂ�߂��Ȃǂ����ɂ��܂����B�c-���̐⋩�̕������Ă������]���܂��ƁA�������R�n�̓��Q���݂��ɑ�����Ă���Œ��ł���A�o���̗��������N���͐���Ȃ������Ƃ��L�l�ł����B�܂��݂ɔ�����{���͂����������̂��Ƃ��ł����v�B�������ɏ��F����Ă͂��邪�A���̃��[�c�������̉��قɂ��邱�Ƃ͊m���ł���B7���I�O�t��17�N�̍Ό����₵�A���@�����߂邽�߂ɒ��������x�֍������f�̗����������m�A�����@�t(602-664)���A�^�N���}�J�\�������f�̂Ƃ��A�����悤�ȉ��ق��L�^���Ă���i����9�j�B
�@�u�嗬��-�����蓌�s���đ嗬���ɓ���B���͗��ꂽ���悢�A�W�܂���U������̂܂܂ŁA�l�͒ʂ��Ă����Ղ͎c�炸�A���̂܂ܓ��ɖ����Ă��܂����̂������B�l�����n������䩁X�Ƃ��āA�ڎw������m��悵���Ȃ��B�����ĉ�������ɂ́A��[���W�߂Ėڈ�Ƃ���̂ł���B�����͖R�����M���͕p�ɂɋN����B���������͂��߂�ƁA�l�{���ɖڂ�����݁A�����A�a�C�ƂȂ�A���ɂ͉̐�������A�����͋������Ԑ����A�����Ƃ�Ă���ԂɁA�����ɗ����̂���������Ȃ��Ȃ�B���̂悤�ɂ��Ă����Ζ����Ȃ����Ă��܂����̂�����̂��A�܂�͉����̎d�Ƃł���B(�嗬����)�s������400�]���A�s�݂�̌̒n�Ɏ���v
�@���������ǂ�����g�J���̈ʒu�́A���o83�x53���A�k��37�x50���Ɛ��肳��Ă���B�^�N���}�J�������̂܂�Ȃ��ł���B
�@13���I�ɁA�����̋A�H�ɋ߂��R�[�X��ʂ����}���R��|�[��(1254-1324)���܂��A�O��������������������̗��ŕs�v�c�ȑ̌��������i����10�j�B�u��ԁA���̍��������f���Ă���ہA���܂��ܖ��肱��ł��܂����Ƃ��A���邢�͂ق��̗��R�ɂ���Ē��Ԃ���x�ꂽ����c���ꂽ�肵�āA���Ƃ���s�ɒǂ��t�����Ƃ��Ă���悤�Ȏ��A�����̐��삪�ނɌ������Ē��Ԃ̂悤�Ȑ��Řb�������ė�����A���ɂ͔ނ̖��O���Ă肷��B����Ɨ��l�͉��X����ɘf�킳��āA����ʕ����ɗU�����܂�A��x�Ǝp�������Ȃ������Ă��܂��B���̂悤�ɂ��āA���𗎂�����A�s���s���ɂȂ������s�҂͌����ď��Ȃ��Ȃ��B����������琸�삽���̐��́A�Ȃɂ���Ԃɂ݂̂Ƃ͌���Ȃ��ŁA���Ԃł��������Ă��邵�A���ɂ��Ǝ�X�Ȋy��̉��A�Ƃ�킯���ۂ̉������ɂ���悤�ȏꍇ������B���̂��߂ɍ������f�̗��s�҂����́A����ɘf�킳��Ȃ��悤�ɂƂ̗p�S����A��ɂȂ�Ɣn�̎�ɂ����ނ艺����v
�@
�@�����̖��R
�@����(�g���z����)�́ANHK�̃V���N���[�h���W�ȂǂŁA�ŋ߂͂킪���ł��L���m���A�ό����s�ŖK�˂�l�X�������Ȃ����B����.�Ïl�Ȗk�����̒��ŁA���Ƀ^�N���}�J���������Ђ����A��������̗��s�҂ɂƂ��Ă͒����ւ̓����ɂ�����I�A�V�X�ł���A�×��A�V���N���[�h�̗v�ՂƂ��ĉh�����B����Ȍ�͂������B�̎�s�ł������B���݂̓�������̓쓌��30�L���ɁA���R�ƌĂԊ�R������A�����ɕ����̑�ΌA���Q������A�̐畧�������邱�Ƃ��L���m���Ă��邪�A���̎R�Ƃ͉����B����ɂ���NHK�҂́w�����ւ̓��x�i����11�j�ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă���B
�@�u�����̊X���ʂ���ƈ�]�痢�̍��u���A�Ȃ��Ă���B���u�̎���͔w���s���Ŋp���Ȃ��A�������������ƍ��������đ傫�Ȃ��Ȃ萺��������Ƃ����B���R�ƌĂ��̂͂��̂��߂ł���v
�@���̖��̗̂R���ɂ��Č�܂���������������Ă���̂��B�w�b�w�����̗��x�i����12�j�̋L�q���܂��A�͂Ȃ͂��B���ł���B�u���R�Ƃ́A�Ȃɂ�炨���₩�Ȃ�ʖ��̂ł͂���܂��B���������̂ł��B�鋃���Ƃ����̂ł��B���͂Ȃ������̂ł��傤���B���̂ӂ��ƂɃ|�v���̗т̑������R�́A�ʖ������p�R�A���邢�͐_���R�Ƃ����܂��B�ǂ̖��ɂ����̎������Ă���̂ł��B���Ƃ͐��Ă��ꂽ���������邱�Ƃ́A���̖��O�ł��킩��ł��傤�B�~����Ăɂ����Ắ[�ҁX�Ƃ��Đ�����A���̔@��1�Ƃ����Ă��܂��B�����炭���̂�������ł��傤���B���������ȉ�������20�L�����͂Ȃꂽ��������ł���������Ƃ����̂ł��B���̖��R�̓�k1600���[�g���ɂ킽��R�ʂɁA��i�A�O�i���邢�͎l�i�ɐΌA���@���Ă��܂��B����͂��т����������ł��B
�@�@�@�@�g�˓V�����䂽���ɉ�����
�@�@�@�@�@�@��̂Ђ�ɍ��鉹��@�̉ԁv
�@��������̐��̂������Ə����Ă���B�����ւ䂭�ƁA���m�ȋL�q�Œm���鏼�������i����13)���A����̒n�����ŁA�e���̒T���Ƃ������ɂ����Ƃ���������w���搅���L�x�����p����Ă���̂͂������ł���B
�@�u���R�̓���ɐ��̐Ԃ��}�͂�����A�R�͓���40���ɂ���B���̎R�͂܂��ꖼ�A���p�R�Ƃ��_���R�Ƃ������A����ς�ł�����Ȃ��B�����뛷�A��ɂ��҂�B�l�ʊF���낤�A�w���n�̔@���A�l����ɓo����Ȃ킿��A���ɐ����������i�����炭�j���B�������������ĕ��������܂����ɕ����Ă��܂��Ƃ����A�s�v�c�ȎR�ŁA����������R�Ƃ��������o�Ă��邱�Ƃ��킩��B���̎R�̓��[�ɗ���������A�R�ɂ���ĉF���Ȃ��v
�����ǂނƁA�����o��͍̂���������Ƃ��ł���A����͂����ɏq�ׂ��W�F�x����i�N�[��A���O��������Ƃ܂��������ʂ̌��ۂ��Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ�B�����ŁA����ɌÕ����������Ă݂��Ƃ���A����A880�N���̕����w�����^�x�i����14�j�ɂ����Ƃ��킵���L�q���݂������B�����A�u���R�A�B�����邱�Ə\���A���̎R�͓������\���A��k�l�\���A�����ܕS�ځB���������ڋN�B���̎R�A�_�ق���ĕ��͍퐬���邪�@���B���̊ԂɈ䂠��B�����������\�킸�B���ĂɎ����B�l�n�����H�߂ΐ����\����U�킷�B�����̒[�߂̓��A��\�̗\���F����ɓ����Ăɗى����A���̍��̐��^���ė��̂��悤�����@���B�łɎ����Ă�����ł�A���k�͋��̔@���v�B���̕����͒T���ƃX�^�C���������Ύ����玝���o���A�����h���w�^�Ƃ�����������(��p�����َʖ{�j�ł���B
�@���̕������~���[�W�J��.�T���h�̕����Ƃ��āA�C�M���X�ɏЉ���̂̓I�t�H�[�h�i����15�j�ł������B�@�X�^�C�����g���A���̒T���L�i����16�j�̂Ȃ��ŁA���R�ɂ��Ă̑̌��������Ă���B
�@�u���̎R������������B�ƁA�Ȃ�قǍ��͑����ɕ��ꗎ���A�����ŎԂ��S���S����悤�ȉ������Ă��v
�@���̂ق��ɂ��A�Â������̕����̂Ȃ��ɂ͖��R�̋L�^������������B�v�A���̎���ɏ����ꂽ�w�������ځx�ɂ́u蟐��̖��R�͍��B�̓�Ȃ�B���̍��A���邢�͐l���ɐ����ĒĂ�A�h���o�ĎR��Ɋ҂�v�Ƃ���A���ŗ��Ƃ��Ă��A���̂����ɎR�̏�ւ��ǂ�Ƃ����B��ɂȂ�ƕ��������ς���Ă��ǂ�̂����A���̂��Ƃ͎��͂ł��킵���q�ׂ�B�܂��w�G�ׁx���ǂ̒����ŁA�킪���ł��悭�m���Ă��閾��̎Ӕ�����(�ݍY)�́A���R�����Z�p�̑������������W�ŁA�\���S�y������A�n���������Ă���B����ɂ��ƁA
�@�u��B�ɖ�����B���̒n�A�l�n�̍s�ʂ����ɐ�����ƁB����͍��B���ɗL��B���̍��A����(������������)�̔@���B�V�C���N�̂Ƃ��A�����獻��B���̉��A����ɕ���B���̍��A�l�̑��ɐ����ė����āA���ɁB�܂��R�ɂ̂ڂ�v
�@����ɒ��ׂ������ł��݂�����悤�ŁA�u�B����\���̖��R�ɂĐ���̐��v�i����17�j�Ƃ��A�h���g�̘A��̎��u�������i�v�̂Ȃ��Ɂu���䐰�v�Ƃ���Ȃ�(����18)�A���܂˂��m��ꂽ�����ł��������Ƃ�����������B
�@������������R�Ɩ��Â����A���̘[�ɂ́A�������̂悤�ȉ���(19)��̂ő嗋�������������ꂽ�B�w���V�L�x�i����19�j��.�́A���т��ё嗋�������o�Ă���B���Ƃ��ΎO�����V�k���畷�����t�ɁA�u�����̕����܂͑嗋�����ɂ����A�V�����̂Ȃ��A��������\�ݔ��痢�̓��̂�ł����v�Ƃ���B�w���V�L�x�̓t�B�N�V����������A�V����(�C���h)�̂��Ƃɂ���Ă���B�����̐��n�������̂ł���B�w�����x�ł̓V�i�C�R�A�����͖��R�Ƃ���������������ۂɂ䂩��[�����Ƃ́A�����ɂ��s�v�c�Ȉ�v�ł���B�����Ȃ����A�ŋ߂̃V���N���[�h��u�[���ł́A���R��嗋�����̉��ق��A�܂������b��ɏ��Ȃ��B���R�͒��ق��Ă���̂ł��낤���B1981�N�ɓ��n�֗������F�l��(���c�͗Y���A���m���ݏZ)�A���̊m�F���˗������B�ނ͖��R�̒���֓o��A����t�߂̍����̎悵�Ă��Ă��ꂽ�B�ނ́u���n�ō������C�z�͂܂������Ȃ��������A���n�̐l�X���A���������Ƃ��ɖ邩����R�ƌĂԂ̂��Ɛ��������v�Ƃ����B
�@���R�̕ϖe���A����Ƃ��J���̂��߂��A���R�͒m��悵���Ȃ����A���͒���������Ă��܂����悤���B�ނ��̎悵�Ă��ꂽ���́A�͂����肻�̎����������Ă����B�����͒������~�����ꂽ�Ήp���ł�����(10�͂̎ʐ^1015�Q��)�A�������\�ʂ́A�悭��Ă݂�Ƌ��̖ʂ̂悤�Ɍ���P���Ă����B�Ȃ������̍������̂悤���\�ʂɂȂ�̂��ɂ��ẮA10�͂Ő�������B���̍��������āA���͖��R�̉��ق��A�܂������Ȃ��~���[�W�J����T���h�܂��̓u�[�~���O��T�\�h�ƌĂ��A���قȍ��ɋN��������̂��Ɗm�M�ł���悤�ɂȂ����B
�w�V���V�L�x(20)�Ƃ���ŁA���m������̗������Ri�X��n�}�̏�ł��ǂ��Ă݂āA���͋���
�Ѓo�����I�D�O
�}2-2�����@�t����ԓ��m���y�͑傫�������c�ȍ��R(�u�[�~���O��q��)�̋߂��������Ă���B�ׂ������ɋC�Â����B�ނ͖��R���͂��߁A�����ɏq�ׂ��u�����̒J�v���O�ꃋ���\�A���͂ŏq�ׂ�\�A��J�U�t���a���̃A�N����J���J�\���u�ƁA��������傫�������o�����R�̋߂���ʂ��Ă���B�����ă^�N���}�J�\�����ł́A�O�q�̋��|��̌������킯���B�u���@�����߂�̂́A�\�����̗��R�ł������B���͔����̉��قɍD��S��R�₵�āA�u�[�~�\�O��T�\�h�̒T����������v�ƍl���Ă݂�̂��������낢�B�����ЂƂA�w�V���V�L�x�ɂ��b����������̂͂������ł��낤���B���䂸�u�얳����ɕ��A�嗋�����͂܂��������肪������������v�Ɛ�����܂���Ȃ���A�O���͂��o�������Ă����B�����͂������ł��܂炽���B�����Ǝ����o���āA���R�ւ����o�����B�ނ��R�����������嗋�����܂��N�����A���̎R�͗h�ꂽ�B�O���͗������āu���̈����߁A����Ȃ��Ƃ��������B���邳���ł͂Ȃ����v�Ƒ吺�ŋ����A�嗋���ɂ���������Č��̎��ɂ͒B������,�v���䂽���B�u���̂�A�C����������v�B�O���ِ͋Ў��O�����B�u���t�����܁A�����ɂ��A������߂Ă��������B���邳���̂́A���̍��̂�ł���v�B
�x�m�̖�
�@�����̏�ł́A�킪���ł����R�̂��Ƃ��m���Ă����B���i�A�V���N��(18���I)�̏��w�������M�i���イ���������Ђj�x�i����21�j�ɁA�O�L�A�ӍݍY�̈�߂����p����Ă���B�Ƃ��낪�u�{���A�x�m�R�̍����̍��ɓ����v�Ƃ��������Ă���Ƃ��������ƁA���e�ɂ��Ă͂܂������킩�炸�ɕ����̏ゾ���ʼn��߂���Ă����炵���B
�@����ɋ��a��N(1802�j���́w�����댾�i��傲����j�x�ɂ́u�s��̖��v�Ƒ肷��ꕶ�������āA���{�̕x�m�R�ɂ������������̂��ȂƎv�킹��B�u�s��̖��i�Ȃ邳�j-�r������"�ӂ��̂Ȃ邳�Ƃ�܂ꂽ����A�����������A�����������ɂ������B���t�ɂӂ��̍����̂Ȃ邳�͂̂��ƂƂ���B���͂̂͂̎��𗪂��āA���Ƃ���ւ��B�r�����̐S�͂���˂ǁA���̎��A���̏�(�O�L�A�w�������ځx�̂���)�ɂ�����A�ӂ��̎R�ɂƂ�悹�Ă���ӂ�Ƃ����ڂ��B�s��̎R�������ɁA�ӂ��̍��A�[�ɗ���A���̖�̒��ɁA���������ւ��ւ�Ƃ��ւ�B����͂Ȃ鍹�̎������̎R��ւ��ւ鎖����������B�܂��A�s�Ǎ�(�Í��W�̍��)�̕x�m�R�̋L�ɉ]���B"�R�̍��ȉ��ɂ͏���������A�R���ȏ�ɂ͂܂�������Ȃ��A�����R���Ȃ��B����ɝ����o��҂́A�R���̉��Ɏ~�܂�B��ɒB������B��������������������ĂȂ�"�Ƃ���B�����������͂ւĂ�܂ꂽ��ׂ��v
�@����́w�ݗt�W�x(�\�l)���A
�@
���ʂ炭�́@�ʂ̏��͂��肱�ӂ��
�@�@�@�x�y�̍����̂Ȃ邳�͂̂���
�Ƃ���̂����߂������̂炵�����A���V�́A�x�y�R���̐��Ɂ[������V�ŁA��ɑ���]�����邩�疼�Â���ꂽ�B�ǂ������炩���Ă���悤���B
�Q�l�������X�g
1.�@���C�g��,�R�{������w�T���}�����l�Êw�x
2.�@R.E.�N�������c��,���c���F��w�P���u���b�W���������x�i�V���o�Ŏ�,1961�j
3. �@Edinburgh. Phil. Jour., [Jan] 74-75; [Apr.] 256-267 (1830) "On a peculiar Noise heared at Nakuh, on Mount Sinai."
4.�@ Bolton, H.C. : Trans. New York Acad. Sci., 3, 97-99 (1884)
5.�@�}���f���B����,��ꐳ�j��w�������s�L�x���m����19(���}�m,1964)
6.�@�Γc���V����r���l�̎x�ߌ����x(�����m���X,1932)
7.�@�I�h���R��,�Ɛl�q����w���m���s�L�x(�����m,1979)
8.�@�w�A���r�A���i�C�g�x�i���m����,���}��1971�j
9.�@��J�^����w�哂����L�x�i���}��,1971�j
10.�@�}���R�E�|�[����,�������j��w���������^�x�i���m����,���}��1970
11.�@�ΉÕ�,*���ᒘ�w�����ւ̓��x�i���{�����o�ŋ���,1978�j
12.�@�w�b���w�����̗��x�i���}��,1976�j
13.�@���������w��������x�i���}��,1943�j
14.�@�w�����^�x�i����{�����S���@�V���`�p����l����
15.�@Offord,J.:Nature,95,[2368]65-66(1915)"Musical sand in CHina"
16. �@�X�^�C����,��菇�V����w�������������L�x�i������,1966�j
17.�@�^�z�C��r�V�ܑ�j�x�l�Εt�^,���W�V���ԍ�*�g�w��*�L�x(�w�u�������x2��(�����o�œm,1980)
18�@�w�������u�x(1831�N����)�������u�p���ؖk�n��,��351��(�����o�œm,1970�N��k����)(�w�u�������x1�����)
19�@���c�C�v,���j�v����r���V�L�x��,����(���}�m,1972)�B��g�����łł͑�2��
20.�@�d��,�F*������a�r��w�����@�t����I�s�x�i������,1965�j
21.�@�S�䓄�J���w�������M�x�i�w���{���M�听�x2��12������
22.�@�w�����댾�x�i�w���{���M�听�x2��12������
��1�@�C�I���X�̒G�ՂƂ��Ă�A�r�̒��������ɒ������y��ŁA���������ɂ�Ă��̈��͂Ŗ肾���Ƃ����B