第10章 ミュージカルサンドの科学
思考する人間ことっての、
最大の喜びは
探究しうるものを探究し、
測るべからざるものを
静かに畏敬するにある。
10..1 諸説紛々
一見、何の変哲もないただの砂が、妙なるメロディーを奏で、ときには大地を揺がして人々を恐怖させる。科学者たらずとも、そのわけを知りたくなる。だが、「どうして音が出るの?」という問題には、いまだに完全な解が与えられていない。(文献1)
1970年刊のイギリスの科学雑誌にはこう書かれている。
「もっともらしい概念的な理論は提案されているが、砂粒の精確な物理的性質をめぐるミステリーは、いまだに残されたままである」
20世紀末の進歩した科学をもってしても、なお取り払えないミステリーとは何であろうか? 私の研究室ではこのミステリーと真剣に取り組んでいる。中間的な報告はすでに公表されているが、全貌が明らかになるには、まだ何年もかかりそうである。したがって本書では結論を差し控えておかねばならない。まだいくつか、確認を要する事項があるからだ。新しい精密な測定方法が発達した現在の目で、ミユージカル・サンドの現象をみると、今日まで解けなかったのは当然だという気がしてくる。
一見、単純な現象に見えるが、砂粒群の運動は実に複雑怪奇だ。非常に短い時間の間に無数の細かい粒子が瞬間的に動く。
それも外からは見えず、その上ミクロな現象である。ミステリーは砂の層とミクロと高速のベールに覆われていたのである。、
「砂がきしるだけのことじゃないかなあ。なにがそんなにむずかしいのかなあ」と不思議に思う方もあろうが、後で述べるように、いまから90年ぐらい前に、カルスーウィルソンは、砂がきしるのだという粒子間摩擦説を唱えて周囲の科学者から袋だたきに遭った。ことはそう簡単ではないのである。いまから100年ぐらい以前までさかのぽって、科学者たちがどう考えてきたかをたどり、そのあとで現代的観点を紹介する。じっくり読んで、、ミュージカル・サンドのミステリーを、推理小説を読むつもりで、楽しんでいただきたい。10.2 エア・クッション説
猛烈な情熱を傾けてミュージカル・サンドを追ったボルトソ博士は、発音機構についていくつかの仮説(文献2,3)をたて、ひとつひとつ慎重に検討していった。楽音が出るには、規則的な振動を発生するメカニズムが、どこかになければならない。砂粒が均一な大きさだったら考えやすいが、実際の砂を見ると、とうてい均一とは考えがたい。では砂粒が何か特別な細胞構造を形成していて、均一な特性を示すのだろうか。そんな気配もまったくない。湿った粒子の表面で空気が泡立つとも考えてみたが、これも現実離れしている。こうしてさんざん悩んだあげく、彼は次のような結論に達した。
「海や潮や雨で砂がぬれたあと、ゆっくり水が蒸発すると、砂粒の表面に空気あるいはガスの薄い膜が形成される。この膜は砂粒を弾性的なエアクッションにより分離して、砂の粒子の自由な振動を可能にする。 ゲーテ
この説をボルトンのエア.クッション説という。しかしガス膜の存在は証明されていないし、真空中でも空気中でも空気中と同じように砂粒子は振動することが明らかにされ、説得力を失った。
10.3 粒子間摩擦説 (文献4-5)
イギリスのカルスーウィルソンは、 「無数の完全に清浄な石英砂粒が、同時に、互いにこすり合わされる結果、音を生ずる。個々の音は小さくて、とても聞こえはしないが、たくさんの砂粒の音が合成されると聞こえるようになる」と唱えた。これをカルスーウィルソンの粒子間摩擦説という(文献6)。 これに対して、ボルトソは次のように反論した。「砂が音を発する場合、これを次の二つに分けて考える必要がある。ひとつは軋(きしり)音を出す砂、すなわちスキーキング・サソド。もうひとつは楽音を出す砂、すなわちミュージカル・サンドである。カルスーウィルソンの説は、スキーキング・サンドについてあてはまるが、ミュージカル・サソドの説明としては不十分である。粒子同士の摩擦により発する音は、とても音楽的とはいえない」 このようにボルトソはスキーキング・サンド(軋り砂)と、ミュージカル・サンドとを明確に区別した(文献7)。 さらにPoynyingも粒子間摩擦説には真っ向から反対した。「Carus-Wilsonの説は受け入れられない。もっとくわしく研究すべきだ。石英粒の弾性率は10の11乗であり、粒子密度は2.5g/cm^3だから、基本周波数は10の6乗以下ではあり得ない。これはあまりにも高い周波数の音であって、これが合成されても楽音にはならない」 このようにして粒子間摩擦説は完全に否定されたが、Carus-Wilson(文献8)は実験家であったから、いろいろ面白い実験を行なった。たとえば一時的にミュージカルな性質を失った「殺された砂(キルド.サンド)」を稀塩酸で洗浄するとか、粒子形状による選別を回転ドラムで行なうなどして復活させたり、まったくミュージカルではない砂、すなわち「物言わぬ砂(mute sand)」をミュージカルにする方法などを試みている。これらの試みは、彼の説の補強には結びつかなかったが、現象を観測するにとどまらず、砂を実験室で処理加工することを通じて考えようとしたのは、ひとつの進歩であった。
10.4 充填モデル説
実験的に、ひとつひとつ確認したがら考えてゆく人もいれば、そういうことはまったくせず、単純明快な抽象論を唱えて、すまし顔の人もいる。物理学者(文献9)Pointingと、トーマスはその典型である。「均一直径の球が規則的に配列している状態を考えると、撹乱がない状態では全体として最小の体積になるように配列する。これを撹乱すれば、粒子群が静止するまでに、いくつかの体積最小の状態を連続的に通るであろう。このとき、ひとつの最小から、次の最小へと移る時間が一定なら、楽音が発生するはずだ。
砂を均一直径の球の充填に置き換えて考えるわけである。図10-1(a)は制止している状態である。第一層だけを横に押すと図10-1(b)のように第二層の粒子群をのりこえて、次の隙間へと移り、図10-1(c)の状態になる。第1層を押し続ければ、第一層はアップ.アンド.ダウン運動を規則的に繰り返す。とすれば、われわれが聞く音は、砂の表面における規則的な振動運動の、ある関数となるはずだ」
これではあまりに現実離れしていて、納得できそうもない。
10.4 表面被膜説
現実的だが、科学老としてはどうかと思われる説を出した人もいる(文献10)。
アメリカのRichardsonである。
「ミシガソ湖の砂丘地帯はマキナック南端のグレイから東岸に沿って広がっている。晴れた日には、水辺に近い区域はどこでも、歩行者が足で砂をこすると、特異で明瞭な音がする。思いがけないところで、思いがけない音がするので、子供たちも大人たちも大いに喜ぶ。しかしこの問題をこれ以上追求し、説明しようとする人は稀である。皮靴ならよく音が出るが、素手や素足でも出るし、ステッキを引きずってもよい」
音が出る原因については「十分納得のゆく証拠によって裏づけされているわけではないことをあらかじめ断わっておくが、これが叩き台になればと思い、ひとつの仮説を提出する」と前置きして次のように述べている。
「浜辺を渚から砂丘のほうへ向かって、乾いた砂の上を歩いてみると、渚から約15-30メートルで砂の音がぴたりと止む。この範囲にある砂は、湖水を周期的にかぶっている。湖水はマグネシウムやカルシウム炭酸塩を含んでいる。水が蒸発すると、砂粒の表面はこれらの塩の、きわめてうすい膜で覆われる。この膜は砂粒の摩擦係数を増すであろう。このことはバイオリンの弓に松脂を塗るのと同じ理由である。砂が風で運ばれてゆくうちに、表面の摩耗作用により、塩の膜ははがれるし、垢もつくので、後背地の砂丘では鳴かない」
まことにもっともな説で、なるほどと思いたくなる。
だが彼はそれをどのように実証しようとしたのか、その先を読んでみると、がっかりさせられる。
「ミシガン湖の水は最高160ppmの塩を含んでいる。しかし音の出る砂と、砂丘の砂とは顕微鏡で見ても差はないし、砂粒の大きさもほとんど変わらない。化学分析しても塩の膜の成分は分析誤差範囲であるから、分析によって確かめるわけにもゆかない。そこで、実験的に上記の仮説を検討する方法として、音の出る砂を洗うか、実験用タンブラー(回転円筒)で塩の膜を除去するか、または炭酸ガスを飽和した蒸留水で抽出するかして、音が出なくなるかどうかを確かめる方法が考えられる。あるいは風で吹き寄せられた砂丘の砂を湖水に浸してから乾かし、音が出るようになるかどうかを確かめてみるのもよろしかろう」
自分ではやってみていないのである。これじゃ尻切れとんぼだ。純粋な水で十分洗浄しても、発音特性はまったく失われないことは、後でも延べる通りで、海または湖水の成分としての塩類はまったくこの現象に無関係であり、表面膜説は成 立しない。
10.5 空気噴出説
東京高等商船学校の栗原嘉名芽氏は、琴ヶ浜(島根)、十八鳴浜(気仙沼)、およびアイグ島(イギリス)の砂について研究し、こう説明した(文献11)。
「粒子面が摩擦すると、それによって粒子と粒子との間の空気が急激に圧迫されて、音波の疎密を構成すべき素因をつくり、粒子の大きさがそろっているので、これが周期的に繰り返される。この周期的な繰返しということがいわゆる音、すなわち楽音的な音の成立を可能ならしめる」
この当時は、学術論文となると、やけにむずかしい表現をする人が多かった。この説明もその見本だが、内容はたいしたものではなく、すでにボルトンがいちど考えて棄てた「空気が泡立つ」説に似ているし、すでに1926年、新帯国太郎氏(文献12)が「空間空気説」と称したのとも大差はない。新帯先生は、この説を寺田寅彦先生に話したところ、「それはだめだ」といわれた旨、併記しておられる。しかしこの空気噴出説は外国へも紹介され、支持者もあった(文献13,14,15)。神戸大学(文献16,17)の土橋正二氏も、この説を補って次のように表現した。、、、「砂の上に圧力を加えたときに、砂粒間の摩擦のために粒子層が階段的にくずれ、この間にある空気が噴き出すときの音である」
段階的に崩れる現象と結びつけたのは一歩前進であった。問題はこのとき、粒子間の隙間が狭くなって、その間に入っている空気が噴き出すのかどうかにある。噴き出す事実をつきつめてこそ、この説は成立するのだが、それがない。後で述べるように、真空中でも砂粒は振動し、空気の存在は必要条件ではないことが判明し、空気噴出説は完全に否定されてしまった。
10.6 Bagnoldの説(文献18,19)
砂漠と砂丘研究の権威、Bagnold は砂の流動の力学に関する彼の厳密な理論に基づき、ミュージカル・サンドの発音機構を説明した。かなり難解だが、あらまし次の通りである。
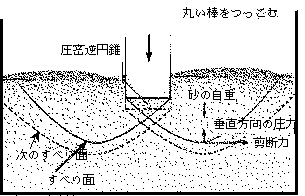
図10-2 Bagnoldのモデル
図10-2に示したように、砂の層を上から棒で押すと、棒の直下には圧密された逆円錐形の砂の襖ができ、これが押し込まれてゆく。それにつれて棒のまわりで砂が盛り上るガ、砂の雇ヰにほ塙+乍の尭をし大づハり値力てきてしZ。准次元え三,」フが十分大きくないうちは、砂の自重のほうが、すべり面で発生している垂直方向の圧力pよりも大きいので、すべりは起ごらないが、棒にかかる力がある値以上に大きくなると、自重WよりもPのほうが大きくなってすべりが生じ、砂は盛り上がるが、砂の層中には特有の形をしたすべり面ができている。棒にかかる力が十分大きくないうちは、砂の自重のほうが、すべり面で発生している垂直方向の圧力よりも大きいので、すべりは起こらないが、棒にかかる力がある値以上に大きくなると、自重WよりもPのほうが大きくなってすべりが生じ、砂は盛り上がる。ひとたびすべりが起こると、すべり面では砂の充填状態が緩み、その結果、垂直方向の力Pは急に減少して、自重Wに打ち勝てなくなり、すべりは止まる。棒にはたえず力が加わって押し込んでくるので、再び前と同じような動きが生じ、これを繰り返す。そのためにすべり面よりも上方にある砂は、まるで弾性的に懸垂されているかのように、垂直方向に振動する。このために楽音を発する。
バグナルド以前の諸説は、いずれも観念的あるいは定性的な説明にとどまっていたため、いずれも実験的事実によって否定されてきたが、はじめて彼により、発音メカニズムに科学的基礎が与えられたといえよう。しかしバグナルド理論の前提となっているいくつかの仮説には、なお検討すべき点が多く、たとえば圧力pの計算式や、すべり面の推定法の確立および実験的な裏づけが検討を要する課題として残された。
10.7 真空でも音が出る?
真空中では、音は出ない。こんなことは中学生でも知っている。出るんだ」「そんなばかな」。この話、もう少し説明がいるので、少し落ち着いて先を読んでいただきたい。
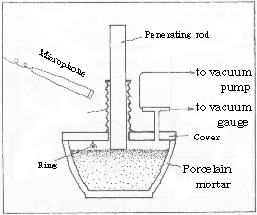
図10-3 真空中で発音させる装置図
図10ー3のように乳鉢にミュージカル・サンドを入れ、厚い透明アクリル板で覆いをし、接着剤で密封する。貫入棒は蛇腹で、アクリル板にとりつけ、棒は自由に動かせるようにしておく。アクリル板には丁字管がとりつけてあって、一方は真空ポンプにつないで空気を抜き、他方は真空度計(マクレオード真空ゲージ)につないである。鈴は、内部の音が聞えるかどうかを調べるためである。空気を抜く前は、鈴の音が聞こえるが、真空度が0.1ミリ水銀柱以上に達すると、鈴の音は外へはまったく聞こえてこない。
このような状態で貫入棒を強く押し込んでやる。さて、どういうことが起こるだろうか。
もし空気噴出説が正しければ、このように空気を抜いた真空中では音は出ないはずだ。また、もしカルスーウィルソンの粒子間摩擦説による個々の粒子の軋り音だったら、音は個々の砂粒の表面から出て、空気中を伝わるはずだから、これも音が出ないはずだ。ボルトンのいうエア・クッションももちろん存在しない。
「さて音は出るのだろうか。それとも出ないのだろうか?」「出ると思う方は赤、出ないと思う方は青のボタンを押し七ください……」。テレビのアナウソサーだったら、きっとこういうにちがいない。あなたは赤ですか、青ですか。世紀の謎の解答ですぞ。
結果は……「ブウ」。
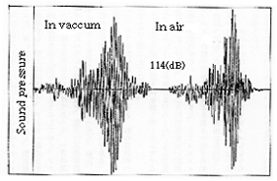
図10ー4(a) 真空中でも大気中と変わらない。
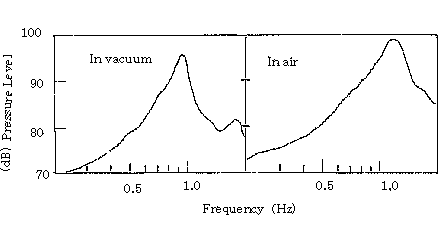
図10-4(b) 周波数解析でも同じ
なんと空気中と同じように、ほとんど変わらぬ大きさの音が出たのである。ここでは読者にその音を聞いてもらえないから、代りにコンデンサーマイクロホンでとらえ、ウェープメモリーに記憶させたのち、音圧波形の記録、および周波数解析を行なった結果を図10ー4 (文献20)に示した。空気中と真空中とが比較してある。少し差があるのは、貫入棒を手で押し込むので、完全には一定条件にならなかったためである。耳で聞く音はほとんど変わらなかった。
「でも、どこから音が出たの?」と不審に思われる読者もあるにちがいない。音は乳鉢と棒から出た。つまり、砂の振動が外に伝わって出たのである。この実験から、砂粒子の周囲に空気がなくても砂は振動することがわかった。月面科学者たちは、超高真空下にある月の砂漠にもブーミング・サソドがあり、音もなく辷って、ムーンクェイク(月震)を起こしていると考えた(3章)。規模こそ小さいが、同じ現象だ。
ところで、真空下の発音実験をやったのはわれわれがはじめてではない。Brown(文献21)は1964年に図10-5のような装置で真空下の発音実験をやった。
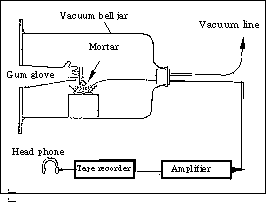
図10-5 Brownの実験装置
ところがその結果はちがっていた。「真空に引いてから砂を突ついてみたが、音は外へは出なかった」と書いている。どうしてなのだろうか。それは実験方法が少しちがっていたからである。小皿に砂を入れ乳棒はゴム手袋で外から真空中で動かした。皿はプラスチック絶縁台におき、振動が外へ伝わらないようにした。だから、音がしなかった。そのかわり、砂の中にはパリウム・チタネート・マイクロフォソを埋め、アソプ、テープレコーダ、ヘッドホソに接続した。「テープレコーダとヘッドホソには新しい種類の音が聞こえた」と書いているのは、ある種の振動を検出したのである。
10.7 水中でも音が出る
空気は必要条件ではなかった。では水の中ではどうなのか? 2章と3章で述べた多くの人たちの観察によると、砂は乾いていることが絶対的な必要条件のようである。湿っていてはまったく発音特性がない。水の中ではもちろんのこと、音が出るはずがないように思える。
だがBrownはこう書いている。ばしば考えられているほどには著しくない。アイグ島の砂は水分5%で美しい音が出た。もっと湿めると、砂がくっつき合って音が出なくなるが、水に浸せば再び美しい音を出す。周波数解析をしてみると、空気中と大差ない(図10-6)」。
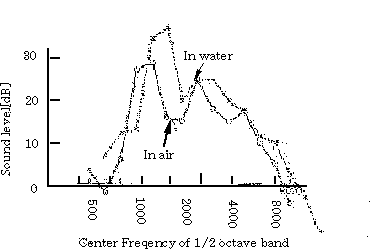
図10-6 Brawn が調べた水中鳴き砂の音波特性
彼は小皿(蒸発皿)に砂を入れ、乳棒で突く方法で発音させている。水は砂の面上1セソチまで入れた。水以外の液体(表10-1)についても実験し、多くの液体で音が出ることを確かめている。水の中でも発音特性があることに私がはじめて気づいたのは、琴引浜を訪ねたときだった。白瀧大明神の滝の水にぬれた砂を踏むと、少し音が出る。この砂はきっと感度がいいだろうと思い乾燥させてみた。その通りだった。特別感度のいい砂は、水中でも音を発するのだ。汚れた砂をポリエチレソ容器に入れ、洗って発音特性を回復させる洗浄実験のときに、いつもこの現象が現われる。十分洗浄した砂は、水が入ったまま容器を傾けて動かすと、ブーッと音が出る
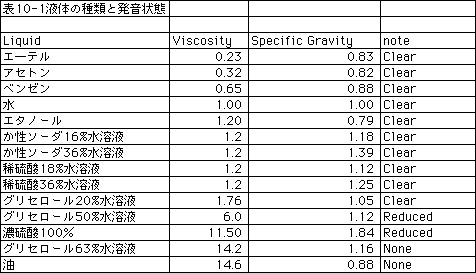
ように土の中へ棒を貫入させるときの貫入深さと、その貫入に要する力の関係を測定する装置をペネトロメータといい、土木工学関係では古くから使われてきた(文献22)。しかし、これは土を対象とするので非常に大きな装置である。
このペネトロメーターのきわめて小さいのをつくれば、ミュージカル・サソドヘ棒を突っ込むときの貫入深さと、その貫入に要する力の関係を正確に測定できるはずだ。
図10ー7
そこで写真10ー11のような粉粒体(文献23)貫入試験装置を開発した。砂を円筒形容器に入れ、上から棒を押し込むのだが、測定の都合上、棒の先に所定の直径の円板をとりつけ、棒は上方に固定したバネ秤りに接続する。砂を入れた容器は下方に置いたジャッキによって、徐々に一定速度で上昇させ、ばね秤りの動きをペソで記録する。より精密な測定を必要とする場合には、棒にかかる荷重と位置を、ロードセルおよび差動変圧器(変位変換器)で検出する。この装置を使って測定した結果の一例が図10ー7である。
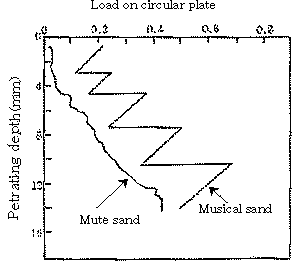
図10ー7 貫入試験結果(貫入板直径10mm,貫入速度1.16cm/sec.,容器径146mm)
このグラフの縦軸は上から下に向かって円板が貫入してゆく深さを示し、横軸は円板にかかる荷重を示している。ふつうの砂(音を発しない)と、代表的なミュージカル・サンド(琴引浜)について比較してあるが、おもしろいことに、ふつうの砂はほぼ連続的にズブズブと貫入してゆくのに対し、ミュージカルサンドは階段状の貫入曲線になる。砂の層は次第に荷重がかかっても、しぼらくの間はぐっとこれを支え、やがて支えきれなくなって、はじめて円板がストンと貫入するのである。貫入すると、バネが急にのびて荷重が減少し、再び砂の層に支えられる。こういう間欠的な貫入を繰り返した結果が、図10ー7のような階段状の曲線(貫入過程曲線)になったわけである。
音がよく出る砂ほど、この階段が大きい。このような階段的特性は、浜辺で砂をゆっくり踏みつけたり、手で押したりするときにもよく注意すれば、このことが体験できる。そして、この特性こそ、発音の秘密を解く鍵なのである。なお、馬鈴薯澱粉や、粉雪などもこの特性があるので、音が出る。小麦粉や米粉も細かく粉砕すれば同じ性質が現われる。
10.7 スティック・スリップ現象
H・D・ソローは「濡れたグラスを指でこするときの音」といった(3章)。ワイソグラスの縁と、指先とを洗剤でよく洗ってから、指先を水でぬらし、グラスの縁に押しつけながら、縁に沿ってグルグルまわすと、やがてグラスはビーソと美しい音色で鳴きはじめる。いい音を出すには、なるべく一定の速さで指を動かす必要がある。洗浄により、グラスと指との間の摩擦係数が大きくなるから、指をグラスに押しつけながらまわそうとすると、静止摩擦力が指の動きを妨げる。指に加えられた力がこの摩擦力よりも大きくなれば指は辻りはじめるが、動きはじめるや否や、グラスと指との間の摩擦係数は、静止摩擦係数よりもはるかに小さい動摩擦係数に変わるので、指はある距離だけ急激に辷る。辷った瞬間、弾力性のある指に加えられていた力は突然開放され、指の辷りは止まる。再び力が加わる。……こういう過程を繰り返して指が間欠的に運動する結果、グラスには周期的な力が加えられ、振動しはじめる。この振動がグラスの周辺の空気に疎密波を生じ、さらにグラスの内部で共鳴して妙音を出す。この場合、指は階段的に辷るので、これをスティック・スリップという。バイオリンの場合は、弓の馬の毛に松脂をぬって摩擦係数を適度に調整し、スティック・スリップを起こさせる。
松脂の代りに、摩擦係数が小さいグリスをぬれば鳴らなくなるし、逆に、おそろしく粘着性の強いものでもだめである。こうして発生したバイオリンの弦の振動が、バイオリソの胴に伝達され、空洞共振により空気が強制振動して、妙音を出すのである。スティック・スリップ現象は、ブレーキがキィーと音を出すのや、洗いたての人間の肌や、髪がクリクリいうことなど、身近かにいつも起こっている。
ところで、先に述べたペネトロメーターの階段曲線も、一種のスティック・スリップ現象である。しかし、この場合は、ワイソグラスの例よりも、ずっと複雑で、様相もちがっている。先に示したバグナルドの図1012のように、砂の中へ棒を押し込むと、砂の層の中で辷り面が発生するが、この様子を強力X線断面写真で観察したのが写真10ー2である(文献24-25)。砂の中にはたくさんの辷り面が発生しているのが見られる。

写真10-2 砂の中に発生する辷り面のX線断面写真
この写真に示す位置まで棒が貫入する間に発生した辷り面が連続的に撮影されている。
辷り面では粒子群が動くので、粒子間に緩い間隙ができ、辷りが止まっても、そのまま残って、連続X線写真では白く写る。この写真から、棒の貫入にともない、砂の中では周期的に辻り面が発生することが確認できる。このために棒と砂は、周期的た振動を発生する。この現象のくわしい解析が目下進行中であるが、それによって、・・ユージカル・サソドの謎は科学的解明へ大きな前進を遂げることになろう。
10.8 最高感度のミュージカル・サンド
浜辺に自然のまま存在する砂は、その場所の条件に制約され、最高の条件にあるとは限らない。ことに最近は浜辺の汚染がひどく、最高の条件にあるミュージカル・サンドを、浜辺で見つけることは、まず不可能である。また自然保護の観点から、いかに研究用とはいえ、浜砂は、採取してはいけない。しかし実験のためには大量のミュージカル・サンドがほしい。さいわい4章で述べたように琴引浜に隣接する網野砂丘の砂を洗浄して、発音特性がきわめてよい、ミュージカル・サンドをつくれるようになった。この砂は鋳物用砂として市販されているので、何トソでも必要なだけ簡単に入手できる。また、8章で述べたように山形県・遅谷の山砂も和用てき.これは自然の浜辺にあるどこの砂よりも、はるかに上等の美しい宝石のような砂である。砂粒の大きさ(粒度)も、浜辺にはないような粗いものも存在する。さらに最近、アメリカのミシガソ湖畔の砂丘の砂も入手し、これから、最高感度のミュージカル・サンドの製造に成功した。
図1018はその発する音の特性である。このことは、研究の進捗に著しく寄与した。
汚れた浜砂の発音特性の回復にも、同じ洗浄方法を利用でき、各地の砂浜や砂丘の砂の発音特性はこの方法で確認した。化学薬品や強力た洗剤を使う方法もあるが、私はあくまでも海の波の機械的洗浄作用に最も近い洗浄法を採用した。もちろん海水は使わず、蒸留水で洗う。上下動式の汎用シェーカーが利用できる。一リットルのポリエチレソ製広口壕に砂二〇〇グラムと水適量を入れ振盈する。ときどき濁った水を捨て、新しい水にとりかえる。赤濁りの水が次第に濁りが少なくなり、最後は一時間振盈してもわずか白濁する程度まで繰り返す。延べ振温時間は数十時間、ないし、百時間を要する。しかしこの方法は簡単だが、時間がかかる割には処理できる砂の量があまりに少なく、それに騒音がひどい。そこでこの方法は浜砂の汚れ具合のテスト用にのみ使うことにした。同時に三-四個テストでき、サソプルは五〇-一〇〇グラムでよいから、浜砂の汚れテストには最適である。水の使用量と時間を一定にきめておき、濁った水の濁度を測定する。次に五-一〇キログラムの処理には、写真1013のジャイロ・ウオッシャーを利用する。一〇リットルのポリエチレソ製広口壕に砂と水を入れて振撮する。(26)この装置は、ふるい分けによる粒度測定用シェーカーとして開発した機械で粒度測定にも併用できる。振藍方法は水平円運動(定半径旋回運動方式)なので、砂粒間に強い勇断力が働くが、衝撃力は働かないから、波の作用に最も近く、前記の上下動方式よりもはるかに有効である。さらに何トソもの大量処理を要する場合は、大型のジャイロウォッシャーを利用し、半連続運転する。騒音がほとんどなく、実験室での操作には好適である。
以上の水洗だけで十分だが、一時間ぐらい煮沸すると、時間が短縮できる。これは砂粒の表面や凹所にこびりついた泥をとるのに有効なためである。なお、洗浄の初期は泥を流し出せばよいので、水道水をそのまま使ってもよいが、最後の洗浄には、蒸留水かイオン交換樹脂層や、活性炭層を通した高度処理水を使わないと、最高感度のミュージカル・サンドは得られない。私自身、これほど敏感なものとは考えず、水道水を使っていたのだが、どうもうまくゆかない。あるとき、高度処理水を使ったところ、見事な音が出るようになった。京都の水道水の質は最近著しく低下した。ミュージカル・サンドはこれを確実にとらえている(声が売物の方はご注意あれ)。
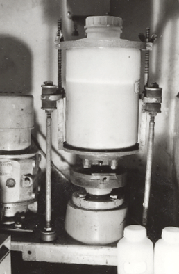
写真10-3 ジャイロウオシャー
洗浄が終わった砂は天日通風乾燥する。通風乾燥器を使うときも、110度C以上に昇温させないことが必要である。砂が変色したり、浜砂の場合は、含まれている貝殻から異物が出て、発音特性を低下させてしまう。このようにして、大量のミュージカル・サンドを最高の条件でつくり出す方法が確立したことは、研究を大きく前進させる力となった。中途半端な試料をもとに議論を進めていては、結論が出たい。なお、このような強力洗浄は石英砂を円磨し、本来ミュージカルではない砂も次に述べる人造ミュージカルサンドと同じように円磨して、ミュージカルに加工するのではないかという疑問が残るが、これについては後述する蛙目珪砂で同じ方法を行ない、円磨効果はまったくないことを確かめた。
10.8 発音実験法
古くから、乳鉢に砂を入れて、乳棒でつつく発音方法が研究者の間で利用されてきた。この方法は、浜辺の上で強く足をこすりつけない限り発音しないようなスキーキング・サンドも発音させることができる利点があるが、これでは、ミュージカルと、スキーキングの区別があいまいになりやすい。私は、ボルトンが使った方法がよいと思う。直径10セソチ、長さ50セソチぐらいの円筒型布袋の中に、1キログラムぐらいの砂を入れ、静かに床の上におろしてみる。このとき、自重でクックッと明瞭な音が聞ける砂は、最高級である。仮にこれをAクラスの高感度ミュージカル・サンドと呼ぶ。
次に、袋の中の砂をゆさぶって、ゆるい充填状態にしてから両手で水平に支えて、強くぶっつけ合わせる。この方法で明瞭な音が聞ける砂を、仮にBクラスと呼ぶ。布袋ではほとんど発音しなくても、乳鉢では発音することがある。これを仮にCクラスと呼ぶ。 布袋を使えば、砂の発する音だけを聞ける。乳鉢では乳棒と乳鉢が別な振動音を出し、さらに下の台に共鳴して複雑な音になる。現地調査の際、荷が軽くてすみ、砂を傷つけるおそれがないのもよい。砂の種類によってちがうが、数百回発音させると発音特性がしだいに低下しはじめ、ついにはまったく発音しなくなる。ミュージカル・サンドは殺されて、キルド.サソドになったのである。この砂を洗えば、非常に細かい微粉(10ミクロソ以下)が生成していることがわかる。再洗浄すれば再び発音特性を回復するが、容易に回復しなくなる場合もある。
10.8 人造ミュージカル・サンド
地質学における岩石風化の理論(文献27,28)によると、岩石の風化順位、あるいは磨耗順位の表がつくられていて、他のすべての岩石が微粉化したあとに石英が残ると書いてある。海浜に白砂が堆積する基本原理である。とすれば、その途中段階にある川砂から人工的磨耗によって石英砂をつくり、うまくゆけば、ミュージカル・サンドもつくれるはずだ。もしこれに成功すれば、製造という観点から研究を前進できる。ひとつの試みとして、京都府綴喜郡田辺町の同志杜大学田辺校地付近の木津川右岸に石英分の多い川砂があったので、これからミュージカル・サンドをつくってみた(文献29)。4ミリと1ミリ目のふるい網で砂粒を揃え、これを直径30センチの小型ボールミルに入れ、直径16ミリの鋼ボールを加えて、15時間粉砕後、研磨材(シリコンカーバイド)を加え、さらに約30時間粉砕した。これ以上粉砕を続けると微粉になってしまうので、鋼ボールだけとり除き、その代りに3ミリのスチール.ショット(鉄球)を砂と同量加え、約40時間、ボールミルを回転させた。この操作で砂粒は著しく円磨されたが、次は砂粒の表面研磨が必要である。そこで、砂だけをとり出し、内径180ミリの小型ステソレス製ボールミルに入れ、シリコソカーバイド微粉(10ミクロソ以下)と水を加え、約300時間、湿式粉砕した。このようにして粒子の形状を整えた砂を、強力機械洗浄すると、写真10-4のように天然のミュージカル・サンドと変わらぬ砂になった。もちろん、発音特性も現われた。鳴かずんば鳴かせてみせよう方式の人造ミュージカル・サソド製造実験は、まだ続行中で、京都の白川砂(花商岩の風化したもの)や、璃璃、フリソト(燧石)、さん.こ珊瑚などからの製造も試みている。自然の浜砂の観察から帰納的に得られる結論と併行して、もっと広汎な条件設定ができるこの種の実験に、私は大きな期待をよせている。
10.8 輝く光沢の不思議
ミュージカル・サンドの砂粒を、ひとつひとつ顕微鏡で眺めるのは、私の最大の楽しみである。それも双眼実体顕微鏡で、倍率をいろいろかえてみる。はじめ低倍率で目標をきめ、次第に高倍率にしてゆくことが必要だ。顕微鏡に馴れない人は、ちょっとのぞいて「わー、きれい」というが、それは素人の見方である。お見合いのとき、ひと目惚れというのがあるが、そんなのはあまりあてにならないのに似ている。
私は少なくとも一時間たっぷりかけて、何度も何度も見る。ひと目では気がつかなかったことが次々にわかってくる。、ミュージカル・サンドは自然が長の年月をかけて創りだした芸術作品であるから、ゆっくり鑑賞するのが当然である。遠くから眺めたり、近づいてみたり、顕微鏡では低倍率にしたり高倍率にしたりすることに相当する。一時間つき合えば相手の顔をいつでも思い出せるように、砂粒の顔がわかるようになる。これは琴引浜の砂、これは十八鳴浜の砂というように。
読者にもぜひ見てもらいたいので、たくさん写真をとってみたが、その迫力の十分の一も表現できない(お見合い写真は実物よりいいのがふつうだが、この場合は逆だ。そこで、走査型電子顕微鏡写真を見ていただくことにする。これもたくさんお見せしなければ面白みhないのだが、紙面の都合もあるので、ほんの一例を写真10-5に示した。残念ながらこれも迫力はない。実物は宝石のように輝き無色透明であると思っていただきたい。低倍率では粒子のほぼ全体像がわかる。高倍率では表面の微構造がみえる。V型の凹みがたくさんあるのは、海浜で円磨された砂粒の特徴だとされている。
中国.敦煙、鳴沙山頂の砂(ブーミング・サソド)は海砂と外見が似ているが、微構造はまったくちがっている。ミシガソ湖のミュージカル・サンドでは表面の性質に特徴がある。
地質学の分野ではこういう走査型電子顕微鏡の写真から砂の履歴を読みとる研究が進んでいる。私にはその能力がないので、コメソトは差し控える。このように、透明な石英粒が一粒一粒、たんねんに磨きあげられ、鋭い角の部分は丸められている。ここには示さないが、気仙沼の十八鳴浜や能登の泣き浜の砂は、低倍率でみると、鋭い角が残っているように見えるが、さらによくみると、やっばり角の部分は、わずかながら完全に丸めてある。こういう見事な砂粒の加工を、自然はどういう方法でやり遂げたのであろうか。人造ミュージカル・サンド製造の場合にはいろいろ粒度がちがう研磨材を使い、重い鉄球や、高速回転、強力洗浄という速効性の方法を駆使したが、それらはいずれも工学的方法である。大自然は、そういう荒々しい手段をつかわず、そのかわり、多分、何万年という気が遠くなるような年月をかけて艶出しした芸術品をつくりあげた。
石英粒子の輝く光沢の秘密について研究したクエソネソ(文献30)は、浜砂や砂漠の砂の調査と、'数多くの実験をまとめて、こう書いている。「奇妙なことに、石英粒表面の艶出し作業は円磨された粒子の突起部からはじまるのではたく、粒子全面から同時にスタートする。深い凹みも、溝も、凸起部や尖端部と同時に同程度の艶出しが進行する。溝は非常に深く、狭くて、磨く作用があるような粒子は入りこめない」彼は溶解とか、結晶の析出というような化学的作用が波による機械的作用とならんで重要た役割を果たしていると考えた。
飯豊山麓・遅谷の砂やミシガン湖の砂を見ると、結晶の析出があった形跡がある。海浜の砂なら結晶の析出は納得できる。わずかだが海水にはシリカ分が溶解しているからだ。だが砂漠の砂はどうなのか。風に吹き飛ばされて磨耗し、円磨されることはわかるが、艶が出るのはたぜか。これについては、夜間に水滴が凝縮するのが溶解、結晶析出の原因だという。想像を絶する地質学的年代の推移がなせる技だ。
ところで、いったん艶出しされた粒子は、容易には磨滅せず、その光沢を保持する。クエンネンはこう述べている。
「乾いた、角ばった粗粒の川砂0.5キロを、大きなガラス瓶に入れ、周速40セソチ毎秒で回転させる。この中に2-3個、艶出しされた粒子を入れる。おそらく短時間に、艶を失うにちがいたいと思うだろう。ところが驚いたことに、このようにして走行距離2000キロメートルに相当する回転を与えても、光沢を失わないばかりか、その凸部はいよいよ光り輝いてくる。」と。ミュージカルサンドのミステリーはこんなところにもあるのだ。
10.8 石英砂のルーツ
京都の名園、竜安寺や天龍寺には白砂を敷きつめ、波の風情を演出している。また銀閣寺には圧倒的大量の白砂を盛り上げた銀沙灘(ぎんさだん)がある。この白砂は比叡山麓に産する白川砂で、良質の花崗岩で知られる白川石の風化物だ。
茶褐色の粘土に混じって石英粒と、残存する長石粒がある。庭に広げておけば粘土分が洗われて白砂が表層に現われる。花崗岩はふつう石英、長石、雲母などの結晶の集りだが、数百年間風雨にさらされると表面がぽろぼろになり、さらに長い年月を経ると、長石が先に風化して粘土化してゆく。植物はこの風化を促進する。白川砂のような風化物が水で流され、川を下って海に出るまでには、機械的磨耗に弱い長石が先に微粉化し、次第に石英粒に富む砂になってゆく。海に出て海浜に打ち上げられるまでに、長石分が完全になくなる場合と、まだ長石が残っている場合とがあり、その程度はさまざまである。長石分が少ない砂ほど洗練された白砂だ。
「千代に 八千代に御影石の沙となりて琴を弾くまで"」
とでもいうべきか。いずれにしても、最後には石英粒が残るが、その粒の大きさと形は、ルーツである花崗岩の結晶の姿をとどめている。「砂粒の大きさや形は、マグマが冷却しつつある過程で石英が結晶する瞬間にほとんど決定され、磨耗や破砕はほとんど影響しない(文献31)。」
といわれるのはそのためである。組織の粗い花崗岩からは大粒の石英砂が、また組織の細かい花崗岩からは細かい石英砂が生成するわけだ。
だが、石英砂のルーツは花崗岩ばかりとは限らない。気仙沼の十八鳴浜は浜に隣接して存在する砂岩が風化して堆積したと考えられている。だがこの砂岩の石英砂のルーツはといえば、そのまた大昔の花崗岩かも知れない。琴引浜や琴ケ浜や、遅谷の砂は直接花崗岩から来たものとすると、十八鳴浜は桁ちがいに古い時代の花崗岩がルーッだということになる。砂の履歴書、ないし血統書というものが次第に明らかになるのは楽しい。
10.8 蛙の目玉を洗う実験
瀬戸の陶磁器原料の陶土は、蛙目(がいろめ)粘土や木節粘土を原料として製造されている。蛙目とは蛙の目玉の意。粘土層の中に石英砂が含まれているので、それが飛び出して水にぬれると蛙の目玉のように見えるところから、その名がある。木節は亜炭が含まれている。私はほんとうに蛙の目のように見えるのかどうか、それを実見したくて、1982年2月、土岐市の丸釜釜戸鉱山を訪ねた。蛙の目玉だけ見るために、わざわざ雪のなかを訪ねる不思議なやつもいるものだと、案内してくださった噛龍森の方々はあきれ顔だった。「これが蛙の目ですよ」と指さされた。蛙の目玉、すなわち石英砂は、精製してガラス原料に出荷されている。ところでこの石英砂のルーツは花崗岩なのか、凝灰岩なのか、「定説はないよ」という。この石英砂はまったく円磨されていない。私の興味はそこにあった。遅谷の石英砂も同じように粘土層に混じって産出するのに、それは円磨されている。その差について考えたかった。
湖と海岸との差なのだろうか。もうひとつの興味は、蛙の目玉を前述のように強力洗浄したら、ミュージカル・サンドにならないのだろうかということだ。もし、ミュージカルになれば、円磨という条件はミュージカル・サンドの必要条件から除外される。もうひとつは、強力洗浄するために砂粒を機械的に激しく振盈するから、この機械的作用によって石英粒が円磨されるかも知れない。もしそうなら、遅谷の砂や、網野古砂丘の砂を強力洗浄して、ミュージカル・サンドができたと喜んだのは、ナンセソスな実験だったということになる。
人造、ミュージカル・サンド製造ならどんな人工的変化を与えてもよいが、自然が創りだしたのか、人工かの境目は、はっきりさせておく必要があるからだ。そこで遅谷の砂の洗浄と同じ条件で蛙の目玉を強力洗浄してみたその結果は、まったく発音特性を示さなかったし、粒子が円磨された形跡もまったくなかった。純粋な石英砂というだけではミュージカル・サンドにはならないことが確認でき、強力洗浄は砂を円磨しないことも確かめられた。蛙の目玉を洗う実験は貴重な成果であった。
10.9 ミュージカル・サンドの粒度
砂粒の大きさ、すなわち粒度は、日本工業規格(JIS)に定められた表10-2の網目寸法をもつ標準ふるいを用いて測定する。地質学などの分野では、2,1,1/2,1/4,1/8,1/16ミリで区切って極粗粒砂,粗粒砂,中粒砂,細粒砂,微粒砂と区分する。ミュージカル・サンドは粗粒〜細粒の範囲で、大部分は中粒と細粒の範囲にある。 粒度を測定する場合には、必要な範囲の標準ふるいを組み合わせ、最上段に試料の砂を一定量(ふつう100グラム)のせ、一定の方法で、一定時間(ふつう5分間)ふるい分ける。ロータップ・シェーカーと呼ぶ機械にかけて振潅する。ふるい分けが終わったら、それぞれの網の上に留まった砂の質量を測定し、質量百分率(%)を求めて、表1013のように数値をまとめる。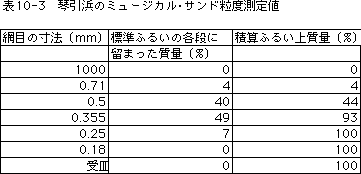
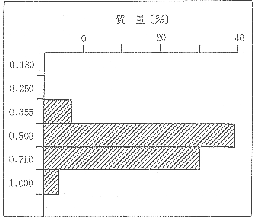
網目寸法は等比級数にとってあるので、対数目盛では等間隔になる。.図10-10では網目寸法を、ミクロン(1ミリの1/1000)単位で示し、それぞれの網目の位置が示してある。表10-3の値を書き込んだのが・印である。これを結ぶと、一本の直線が得られる。このように対数正規分布線図を使うと、直線で近似できる場合が多い。参考のためいくつか、他の砂の粒度分布も図示してある(・印はわかりにくくなるので、他の砂については省略した)。この線図で右のほうにある亘腺ほど阻図を使うと、直線で近似できる場合が多い。参考のためいくつか、他の砂の粒度分布も図示してある(.印はわかりにくくなるので、他の砂については省略した)。この線図で右のほうにある直線ほど粗い。また直線の勾配が急なほど粒度分布の幅が狭く、粒ぞろいである。この図から粒度分布を次の二つの値(粒度指標)によって表現することができる。。氏……50%粒子径と呼び、縦軸五〇%に対応する横軸の値9…-幾何標準偏差とよび】ソ=\U♂U薯は縦軸一五・九%に対応する横軸の値琴引浜の砂では、U呂HOトooPU旨.oH900しoq11060ミO.ハooN"一』切表1014には代表的なミュージカル・サソドと、ブー、・・ソグ.サソドの粒度指標を比較してある。このように整理してみると、比較しやすい。それぞれ、粒度の粗いものから順に並べてある。一般に浜砂は場所により粗さがちがうので、その一例として琴引浜の砂は三種類示した。これをみると、琴引浜は世界中のどの浜辺のミュージカル・サンドに比べても、すばぬけて粗い。一般に浜砂は粗いほど周波数が低い音、すなわち低音を発する。低音ほど迫力のある音になる。琴ケ浜もそれについでおり、わが国は世界的に最も優れたミュージカル・サンドを保有していることにたる。この世界の宝をたいせつにしたいものである。
なお、地質学の分野ではφスケールという特殊な粒度表示がしばしば使われる。素人にはわかりにくく、そんな面倒た値を使わなくてもよいが、文献を読む上では必要になるので、次に換算法を参考のため記しておく。
表1012には網目寸法に対応する¢の値が示してある。0.5ミリを基準にとってあるから、次の関係がある。電卓で容易に換算できる。
log(網目寸法mm)=¢*log0.5
10.9 充填特牲の特異性
ユージカル・サンドは、貫入度試験機で測定すると、著しい貫入抵抗を示すことをさきに述べたが、それは砂の表面摩擦係数が大きいことのほか、砂を容器に詰めたときの、砂粒の詰まり方、すなわち充填特性にも影響されている。一定内容積の容器(内容積100ミリリットル、内径5セソチ)に一定の方法で砂を詰め、砂の面をならし、このときの砂の質量をはかる。この質量を内容積で割った値、すなわち単位体積当りの質量を、嵩密度という。なるべくゆるく充填したときの値を疎充填嵩密度、なるべくかたく詰めたときの値を密充填嵩密度という。一般に、ゆるく充填するためには、ふるいを使って少しずつ詰める。砂が全部通るような粗い網目のふるいを容器の上におき、これを通しながら充填するのである。密に充填するには、容器の底を一定の方法でトソトソ叩き、それ以上詰まらないことを確認する。ところがミュージカル・サンドだけは、ふつうの砂とちがって、ふるいを使って充填したほうが密に詰まる。トントソ叩くと、かえって容器の中の砂があふれだすこともある。これは、砂粒子が密充填しやすい整った形状をもっているためである。ふるいで少しずつ詰めてゆくと、石垣を積んだように、一個ずつきちんと積まれてゆくのである。
そこで、容器の上、一定高さにガラス漏斗を置き、急速に流しこんでやる。実験してみるとこの方法が最も疎充填が得られ、表10ー5に示すように測定値のバラツキが少ない。密充填には逆にふるいを使う。次の値は琴引浜の砂の測定値である。
疎充填嵩密度1.55〔g/cm^3)〕
密充填嵩密度1.72〔g/cm^3)〕
この差は、密充填すると、どれだけ嵩が減るかを示している。次の値を圧縮率と呼ぶ。
((密充填嵩密度)-(疎充填嵩密度)/(.密充填嵩密度〕)(覇計斌藤鼠陶)*100=である。普通の砂の1/2〜1・3である。このことから、ミュージカル・サンドは、非常によく充填される性質をもっていることがわかる。さきに、空気噴出説は誤っていると述べたが、砂を圧縮しても、砂粒間の隙間はわずかしか変わらないのだから、とても空気が圧縮されて吹き出すわけがないことが、このことからもわかる。動けば逆に隙間は大きくなるのである。
充填特性について、もうひとつ興味ぶかい事実がある。充填状態にある一個の砂粒は、隣の粒子何個と互いに接触し合っているか。これを配位数という。直径の等しい球を最密充填したときの配位数は12である。1個の球に12個の球が接触している。ではミュージカル・サンドではどうか。琴引浜の砂について実験してみた(文献20)。
砂を墨汁に浸してから遠心機にかけ、余分な墨汁を振り切ってやると、墨汁は粒子の接触点にだけ毛管力によって残る。このまま乾燥すると、粒子の上に黒い点が印される。これを一個一個顕微鏡で調べて、一個の砂粒に何個の黒い点がついているかを数えて集計する(表10-6)。これはたいへんやっかいな仕事だが、研究室の学生諸君が協力してやり遂げた。平均配位数は10.6、最大20のもあった。粒子の大きさが一定ではないので、大きい粒子には小さい粒子がたくさん配位することもあるわけだ。このように配位数が大きいことが貫入抵抗を大きくし十分力がかかってから、粒子層が動く。そのとき音が出る。ここにもミュージカル・サソドの秘密がかくされている。以上のようにミュージカル・サンドの秘密がかくされている。
以上のようにミュージカル・サンドの謎は急速に解明が進んでいる。最近ミュージカル・サンドと、それを発音させつづけて音が出なくなったキルド・サンドの内部摩擦係数を精密に比較検討する装置を完成し、キルド・サンドになったときには、摩擦係数が著しく小さくなることも明らかになった。その原因は、砂粒間の摩擦により、10ミクロソよりも細かい微粉が生成するためである。
なお摩擦により、静電気が発生する。高感度の砂ほど著しい。微粉が発生すると静電気は少なくなる。このことは真空放電によって確かめることができる。「ミュージカル・サンドの謎が解けたとして、いったいそれが、何の役に立つのか。,無弦琴や、無膜太鼓を開発するつもりなのか」と聞く人がいる。何かの利益につながることを、唯一の行動原理にしているビジネスマソに多い質問である。私は答える。「解明する過程が楽しいのです」。楽しいばかりではない。その過程で、たくさんの副産物が生まれる。新規な研究方法、装置、理論、天然以上にすぐれた、ミュージカル・サンド。そして限りない夢。
参考文献
1. Ri1dgway, K,, Rupp, R. : Nature, 226, [52 4l] 158-159 (1970) "Whistling sand of Porth Oer. Caernarvonshire "
2 Bolton, H.C., Julien, A.A. : Science (N. Y.) 2, [43] 713 (1883) "Musical sand."
3 Julien, A.A., Bolton, H.C.: Trans. New
4 Carus-Wilson, C. : Nature, 44, [1136] 322 -323 (1891) "The production
of musical
(1915) "Early references to musical sand
6 Bolton, H.C. : Nature, 43, [1098]30( 1890)"Squeaking sand versus musical sand"
7. Poynting,J.H.;Nature,77,[1994]248(1908)"Musical sand"
8 Carus-Wilson, C.: Science, 18, [446] 99 -100 (1881) "The production of musical sands.
9. Poynting,J.H.:Textbook of Physics"2nd.ed.p.144-145(Griffin,London,1900}Brown,A.E.:Philosophical Soc.Proc.A.,1-7(1964)に引用)
10. Richardson,W.D.:Science(NY),50,493-495(1919)"The singing sand of Lake Michigan."
11. 栗原嘉名芽『応用物理』6巻1号、18-20(1937)『鳴り砂に就いて』
12. 新帯国太郎『満鉄読書會雑誌』13巻5号,106-116(1926)「鳴る砂の話
13 Brown, A.E., et al.: Phil. Soc. Proc., Ser. A, [2l] 217-230 (1961)
"The sing-**-;1* -f+1** ~~**k-** P**+ T "
Takahara, H.: J. Acous. Soc. Amer., 5 [2] 634-639 (1973) "Sounding
mecht ^~;"'
14. 高原 光『応用物理』34巻,5号,42-45(1965)「鳴り砂の発音機構と振動数」
15. 高原 光『千葉大学文理学部紀要』4巻,4号,417-419(1966)「鳴り砂の雑音」
Takahara,H.:J.Acous.Soc.Amer.,53{2}634-639(1973)"Sounding mechanism of singing sand"
16. 土橋正二『応用物理』21巻9号,361-363(1952):29巻2号,83-86(1960)「鳴砂の音響學的研究」
17. 土橋正二『表面』4巻,2号:92-99(1966)「鳴り砂について」
18. Bagnold, R.A. : Proc. Roy. Soc., A225,49-63(1954)"Experiments on a gravity-free dispersion of large solid spheres in a Newtonian fluid under shear."
19 Bagnold, R.A. : Proc. Roy. Soc., A295, 219-232 (1966) "The shearing and dilation of dry sand and the singing mechanism."
20. 日高重助,三輪茂雄『粉体工学会誌』18巻5号301-310(1981)「鳴き砂の発音機構について」
21. Brown,A.E. et al.:Phil.Soc.Proc.,Ser.A.,1-7(1964)"The singing sands of the seashore,Part2"
22、サソグレラ著,室町忠彦,赤木俊允訳『貫入試験と地盤調査』(鹿島出版会,1976)
23. 日高重助,三輪茂雄『化学工学論文集,7巻2号,184-190(1981)「粉体の貫入特性」