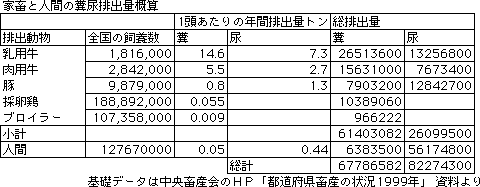味噌田楽屋
味噌田楽屋 味噌田楽屋
味噌田楽屋
6.1 擂鉢が作り出した食文化
最近の家庭から、擂鉢が消えた。あっても非常に小型化し、本来の機能を発揮できるかどうか、疑問のものが多い。調理済の食品が圧倒的で、使わなくてもよくなったことが原因している。擂鉢と擂粉木(すりこぎ)は、つきウスと杵のミニチュアまたはポータブル型である。中国で発達し、鎌倉時代に石臼や茶磨とともに伝来したが、上流階級に限られていた。当時のすりばちは四本の先端をもつ櫛目で、底から上縁にむかって条溝をつくったもので、筋が少なかった。当時はロクロで作られ、安定してガタつくようなことがなかった。しっかりした、非常に頑丈なものだった。しかし底の部分が厚いために焼成中に割れることが多く、収率は三つに一つだったという。江戸時代末、備前で鋳込みに変り、大量生産が利くようになって一般に普及したといわれている。現在に残る溝の数が多いものである。2003年ころ岸和田市に西念陶器研究所が出来て、資料室だけでなく、その料理とともに保存しようとしているのはうれしいことだと思う。擂鉢と擂粉木がつくり出す調理は実に多様多彩で、味噌汁、味噌和え、胡麻味噌、芋汁(とろろ)、白和え、そのほか諸々の料理がつくられた。変ったところでは、東北地方の甚太餅(ずんたもち)がある。枝豆のシーズンにつくる。豆の緑あざやかで、これにつきたての餅にまぶして食べる。
擂鉢の使いかたも、複雑である。単なるかきまぜ容器のこともあるが、複合操作のことが多い。とろろを造るとき、おろしただけではざらつくが、擂鉢で摺るとなめらかになる。また、味噌の中でも豆味噌はかたい。これは、まず、つついて砕き、練る操作が要る。これを「かたねり」という。工業的操作では"捏和(ねつか)である。これに十分時間をかけてから、つぎに少しずつ水を加えて薄めてゆく。最後は分散操作である。湿った粉扱いの常道だが、こういうことも常識だったが、最近では工学として教えなければならない時代になった。
6.2 忘れられたせっかい
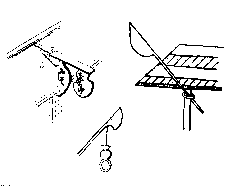 江戸時代の味噌屋の看板戸時代の味噌屋の看板、
江戸時代の味噌屋の看板戸時代の味噌屋の看板、
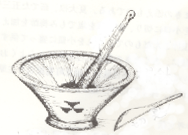 せっかいはセットで使うものだった
った
せっかいはセットで使うものだった
った
ところで「せっかい(狭匙、切匙)」という道具をご存じだろうか。しゃもじを二つ割りにした形をしている。よけいな世話をやくのを「お節介」というのはこの道具に由来する。すりこぎに粘りついたものは直線部分で、内部は曲線部分でかき落す。均一に摺るための道具である。さいごに溝の中を先端で掻き落せば無駄がない。鉢から掻きだすにも便利である。これなしでは、うまく使えないのに、なぜか明治頃から次第に家庭から消滅した。本来古くなった杓文字を半分に割って自作するものだった。
ここで、擂粉木、擂鉢に関する話題を紹介しよう。つぎは名文の紹介。名古屋藩士で俳人の横井也有(やゆう)著『鶉衣(うずらごろも)』(天明六年)に「摺り鉢伝」がある。
「備前の国に、ひとりの少女(おとめ)あり。あまざかるいなかの生れながら、姿は名高き富士の悌(おもかげ)にかよひて、片山里に朽ちはてん身を、うき物にや思ひそみけん。馬舟の便につけて遠く都の市中に出で・・・」と立板に水をながしたような名文がつづく。人の世の哀歓と変転を、おもしろおかしく、そして巧みに、これでもかとばかりに徹底的に追求し、摺り鉢に託して語る。その最後は、涙の物語。「猶五月雨(なおさみだれ)の折折は、雨もりの役につらなれば、いとど長門(ちようもん)の涙かわく隙なく(中略)遂に橋づめの塵塚によごれふし、果はさがなき童べのままごとに砕かれ、行方もしらぬ闇の夜のつぶてとはなりにけるとぞ」電動ミキサーでは、とてもこのような人生文学は出てこない。
韓国には唐芥子(とうがらし)用の擂鉢がある。目が粗くて臼の目と同じく八分画である。これで挽く新鮮な唐芥子の味と香りがすばらしかったので、買ってきた。帰国時の韓国税関で機内持ちこみ荷物検査のとき、「どうしてこんなもの?」と質問された。割れば凶器にもなりかねないからであろうか。「ここに二千年の歴史が刻まれているから」とこたえ、ウスの目の講釈を一席やってOKが出た。好奇心に満ちた税関吏は「またいらっしゃい」と手を振った。
6.2 胡麻
ごま(胡麻)は昔から「万能食餌」と呼ばれ、延命長寿、強壮補精、便秘解消など、さまざまの効能が知られてきた。また調理に胡麻をうまく使えば、どんな食べものでも旨くなる。筆者の祖父にあたる人は、生まれつき、魚類が嫌いだったので、煮干や鰹(かつお)の出汁(だし)を使えず、すべて胡麻味だったという。それがまたとてもおいしかったと母が語ってくれた。同志社大学の近くの閑臥庵で 、尼さんが万福寺の精進料理をはじめて話題になっていた。それがまさに胡麻昧の極致だった。鰻の蒲焼だの、蒲鉾など、「あれ、これが精進料理?」と思うが、材料には全く生嗅いものは使っていない。それでいて本物そっくりだ。食べてしまってから、「ほんとに肉や魚は使っていないの」といいたくなるほどだ。「誤魔化し」は「胡麻化し」に通ずるというが、わるい意味ではなく、よい意味でここまで誤魔化されるのは、すばらしいことだ。閑臥庵は美味のうえに美人の尼さんとあって、大繁昌だった。男子禁制ではないが、女性客が多い。一週間ほど前から予約する必要があった。材料の調達と煮込みに日数がかかるためであった。
ところがあるとき行ったら、すっかり味が変わっていた。後味がわるく、とにかくくどい味だった。多分古くなった(酸化した)胡麻を使ったのだろう。たまたま悪い日に行ったのかも知れないが、それに懲りて行かなくなった。後日談は知らない。
胡麻はエジプト時代から西洋で重要視され、シルクロードを経て東洋に伝わり、わが国では千年ほどまえ(延長年間(923-930))の記録がある。古来万能食餌といわれ、さまざまの効能が知られてきた。「ごまかす」というのは、胡麻を用いれば、何でもおいしいことから来ている。生臭い材料を一切つかわない京都の精進料理にも使う。家庭では、洗い胡麻を買って、擂鉢で摺るのが一番である。生の胡麻を焙烙に入れて火にかけ、かきまぜて三粒はねたらOK。こった料理用には奉書紙を遠火にかざして焦がさぬ程度。この炒るときの香りがすばらしい。これを工場ですててしまうのはいかにも惜しい。洗い胡麻は生きているから、これを、炒ってすぐに摺って食べるのが当然。炒り胡麻として売られているものは、長時間放置した焼死体だ。うまい筈がない。
ものぐさの現代人向きに、安価な電動胡麻擂り機なるものもあるが、所詮おもちゃ以上のものではない。値段の都合にあわせて作った中途半端な機械だから、目が詰らないよう不十分な摺りかたで止めてある。ほんの少量ずつ摺るには百貨店の文具売場にある絵具用の乳鉢が便利だ。乳鉢は旧石器時代以来の石器から磁器に変わった万能の道具である。私はダイヤモンド工具を利用して直径約一〇セソチのミニチュアの挽き臼を作ったが、性能は抜群だ。
たかが胡麻と思うが、集中大量生産ともなれば大変である。現代の日本では国産胡麻はゼロに近いから、黒胡麻は中国、インドネシア、タイなど、白胡麻は、アフリカのタンザニアあたりから船で運ばれてくる。かさばるから輸送も厄介だが、その精選にも特別な技術が要る。粗いごみをまずふるいで除去してから、丸目、つぎに長目のふるいにかける。形状選別である。なぜこんな難しいことが必要なのか。実は胡麻とそっくりな昆虫の糞の完全除去である。つぎに水洗いし、乾燥したのが洗い胡麻である。これを回転ドラム式の大きい胡麻炒り機械にかけて炒り胡麻になる。
もっとものぐさな人のためには摺り胡麻もある。生産の八○パーセソトが摺り胡麻というから驚く。これがものぐさ人工比を示している。古くなった胡麻は油の酸化が味を落し、そのとき、くどいと感じるのは人間の拒絶反応である(前述の精進料理がそれだった)。体のことを思うなら食べないほうがよいが、不思議なことに、これが自然食品売場に出ている。
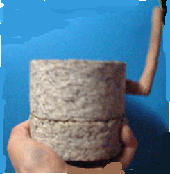 世界最小直径10センチのミニ石臼
世界最小直径10センチのミニ石臼
では本物の石臼で胡麻を擂ったらどうなるか。当然、目が油でつまって、どうしようもない。そこで私はひと工夫して、石臼の花崗岩を目たて方法もかえて、いろいろ実験してみたところ、ある日成功した。直径十センチぐらいのミニ石臼であった。私はこれで、うまい胡麻の味を楽しんでいた。小皿で受ければよい。たまたまそこへ、日本の胡麻のシェアー日本一という大手の擂り胡麻の会社の社長が来た。ミニ石臼を見つけて、これを欲しいという。「冗談じゃない。これは私専用で手がかかってたまらない」。「じゃー是非工業化したいという」。そこで中間段階として直径36cmの機械を試作した。高精度の加工のために、かなり苦労を重ねて、とにかく成功に漕ぎっけた。ところが、調整方法が不充分だったために、原料の炒り胡麻を入れると、擂り胡麻ではなくて、練り胡麻が、まるで蜂蜜のように出てきた。練り胡麻というものを知ってはいたが、自分でつくったことのない私は、驚いた。練り胡麻は、胡麻油に胡麻粒をまぜたものだろうぐらいにしか考えていなかったのが、目の前で炒り胡麻が練りごまになったからである。あとで知ったことだが、胡麻は50パーセント位が油であるから、当然のことだった。失敗が生んだ練り胡麻は実においしいので、さっそくパンをもってきて、これで石臼を掃除しながら食べた。ずいぶんたくさん食べたので、あとで胸やけするのではと心配したが、その気配は全くなかった。さすが生きた胡麻からの挽きたてだった。
6.3 荏胡麻(えごま)の味
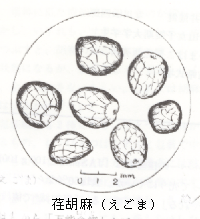
「東大寺正倉院文書」の天平(729〜)年間の記録に荏胡麻の名がある。岐阜県の高山を訪ねたときのこと。朝市で「えごま」の種子をを見つけた。食べてみると、白ごまや黒ごまとはちがったコクのある味で、香りも高いので、栽培してみることにした。翌年、どんなのが生えるかと楽しみにしていたところ、青紫蘇によく似た植物になった。夏もすぎる頃には背丈ほどに成長した。ところが秋になっても、いっこうに花が咲く気配がない。徒長したせいなのだろうかと思っていたら、開花の気配がするので楽しみにしていると、さらに葉が出てきて、枝に枝が伸びるばかり。母が「そろそろ大根を蒔く季節になったので、邪魔になる。もう引いてしまおうか」という。もうちょっと待ってと頼んだ。この芽は、こんどこそ」。自信はなかったが、更に一週間待った頃、一斉に花がついた。待った甲斐があった。上図のような実がついて、コクのある味で、香りも高い味を楽しむことが出来た。
その味を求めてホームページで荏胡麻を検索したら荏胡麻サミットというのがあった。福島県郡山市に日本エゴマの会なるものがあり、荏胡麻の全国的普及を目指していて、ここでは種子も分けてくれるいるという。うれしい話だ。
6.4 蕎麦の味
日本の伝統食品の中で、そばはとくに熱心に残されているものの一つである。ホームページで検索すると、そば名人やら、偽名人やらがいっぱい書いている。まさに日進月歩の感がある。石臼挽き、または石臼そばと称するそば屋がある。西洋には石臼挽きパン屋があるように、伝統を正確に生かしているという意味が石臼という文字にこめられている。しかし店先に石臼が飾ってあるからといって、そば粉が石臼挽きとはかぎらない。ほんとうに石臼挽きでも、輸入玄そばでは意味がない。輸入玄そばにくらべると国産玄そばは格段に高価で、しかも産地の土質や気候にもよるから、本物に出合うのは容易ではない。実はそこにぜいたくがあり、通の楽しみがある。
ところで、なぜ石臼挽きなのか。そばは、もろくて、挽きやすいから粉にしやすい。皮は細かく砕けずに、臼の目から出てくる。そこで上手にふるい分ければ白い粉になる。そばは黒いものと思っている人もあるが、臼とふるいの使い方に問題がある。田舎そばが黒いのはそれである。そばの実を高速度で板に衝突させて皮を分離する機械もある。玄そばは必ず土石を伴っているから、前処理を入念に行う必要がある。ふるいで石や異物を除去する。つぎに磨きである。これは玄そばの粒同士を互いにこすり合せて表面に付着したゴミを完全に除去する。ふるいと風で吹き飛ばす石器時代以来の手法である。以上の前処理が完全であれば、土石がまじることはない。石臼で挽くと、石臼から石の粉が入ってジャリジャリになると考えている人があるが、粗末な石臼を使うからである。上下石の調整が完全であれば、周縁部分で粉末を潤滑剤として浮いており、石と石とは衝突しない。 最大の問題は粉焼けである。正確には粉の熱変質である。石臼は上下石が周縁部分だけで接触していて、中央部には適度のふくみがある。磨耗してくると周縁部分だけでなく、ふくみの部分でも接触するようになる。ここで激しい摩擦が起り、粉の送りが不良になって粉の熱変質が発生する。味と香りのほか、打って見てはじめてわかる未知の特性まで変化する。東京と京都で、老舗を誇る有名店のそば粉を集めて、粒度を測定して見た。実に多様であった。
葉山の御用邸前に知人のそば屋さんがあって、私はそこに納めた機械の石臼の目立てに出張したことがある。ハチマキしてコツコツやっていたとき、御用邸の警備員さんが、「へー、今どきこんな商売もあるんですか」と聞く。「京都からきた臼屋ですわ」といったら感心された。さて目立てが終って、午後四時頃からだったろうか。私たちは夕餉のテーブルに着いた。酒、おつまみ、鴨肉の鍋料理などと、次々に出てくる。テーブルに着く以前から、主人はソバ打ちに余念がなかったから、もうとっくにソバが出てきてよさそうなものだが出てくる気配がない。製粉をはじめる。粉をジーッと眺めたり、指でこすったりしながら、主人は何も言わない。黙ってそばを打ちはじめたが、まだ何もいわない。私は気になってならない。待ちあぐねて待つことひととき、やっと出てきた。もちろん、山芋や小麦粉のつなぎは全く入れない。「うまい」とお代わりを」。主人いわく「腹がへった人には食べてほしくない。満腹してもお代わりしてほしかったんです」。こんな職人気質が残っている間は日本もまだ健全である。
やまと福島県山都町には、名物「はっと蕎麦」がある。製粉は60パーセソトだけ、あとは棄てるから、殿様から「さような、ぜいたくは御法度なり」といわれながら、内緒で伝わったという。そば特有の香りは少ないが、そのかわり、これがそばかと思うくらい「こし」が強い。これもひとつの地方色である。信州から学んだと伝えられるが、本場の長野には伝統が絶えているらしい。
6.5 豆腐
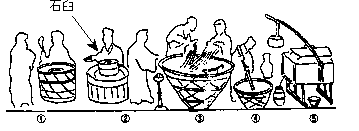
粉の話でなぜ豆腐と思われるかも知れないが、豆腐は、一晩水に浸した大豆を笊にあげて水をきり、やわらかくなった大豆に水を加えながら、水挽きするところからはじまる。これを湿式粉砕という。やはり「粉づくり」の手法である。
豆腐は中国漢代の発明といわれているが、その起源を巡って諸説があった。「豆腐之法、始於漢淮南王劉安・・・」(本草綱目)「漢代に淮南王劉安(前178-122)が豆腐のつくり方や道具を朝廷や諸公に献上したために豆腐が広く伝えられることになり、後世その発見者として淮南王の名が伝わることになったのかも知れない。」(『やさしい豆腐の科学』)しかし古文書には豆腐の文字がなく上記は俗説かも知れないというのが従来の定説だったが、以下の2つの事実から定説はくつがえった。
『文物考古三十年』の文献に世界最古の豆腐製造工程図があると聞きこの文献がある959年-1960年間の河南省鄭州市西南45km、密県城西6kmの処にある、ここは淮南の西北約400キロの地である。大中国ではお隣りである。密県打虎亭の後漢代漢墓打虎亭1号漢墓出土の石に描かれた石刻線図で豆腐製造プロセスを書いたもの(豆腐作坊石刻)が見つかった。「墓底に厚さ50cmの木炭層がある。独特の様式の画像石刻が豊富であり、壁に図を彫っている。中でも一番興味を覚えたのは《制作豆腐工芸図》生き生きとした東漢(後漢)風情の画巻きだった。東漢時期の人々が豆腐を制作する完成過程の表現があり、中国内でもこれに比したものは無いと言う。現在発見されたものは此れが世界史上最早の豆腐に関する記載であると言う。」(http://www.ccv.ne.jp/home/tohou/tabi129.htm)に制作豆腐工芸図がある。墓底に厚さ50cmの木炭層がある。独特の様式の画像石刻が豊富であり、壁に図を彫っている。中でも一番興味を覚えたのは《制作豆腐工芸図》生き生きとした東漢風情の画巻きだった。東漢時期の人々が豆腐を制作する完成過程の表現があり、中国内でもこれに比したものは無いと言う。」
日本では画像石と呼ばれているもので、王樣の墓の副葬品で石に線で彫ったものという。「磨制豆腐画像」と書かれていて、
これはどう見ても豆腐である。
そこで毎年豆腐まつりがあるという。こうなるとじっとしてはおられない。淮南の現地を日本豆腐起源問題考察訪問団を作って1998年11月1日(日)上海- 合肥
経由で豆腐博物館がある淮南を訪ねた。寿春の報恩寺には漢代の明器があり、それには受け皿に大きな孔があいていて、豆乳を出す口に間違いないことを確認できた。ガラス戸越なので、写真は明瞭でないが、イメージは下記である。明器だから素焼きで、臼はせいぜい10cmぐらいだが、受け皿が大きく、さらに豆乳を受ける皿らしく、豆乳を流しだすための工夫がある。間違いないことが確認できた。なお民放テレビで町中が豆腐屋だというのは誇張である。また石臼で挽いているのは豆腐村という施設だけで、大部分は高速機械挽きであった。何よりもその豆腐は決して美味しくはなかった。
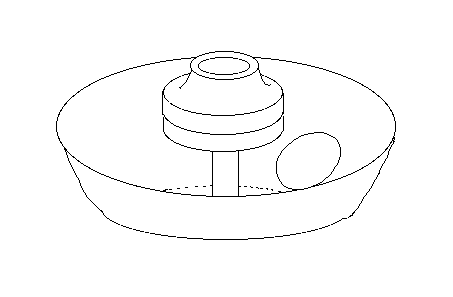 報恩寺にあった漢代の明器
報恩寺にあった漢代の明器
powder/food/waimeik.gif
報恩寺にあった漢代の明器
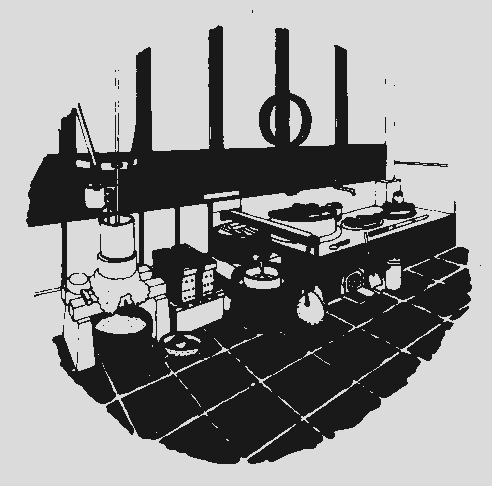
日本の昔からの食べ物で、アメリカで新しい食べ物としてブームになったものに、豆腐がある。適量の水を加えながら挽くと、下石の周囲には白い挽き汁(呉汁(ごじる))がしたたりおちる。加える水の量は呉のたれ具合で調節する。できた呉を約三十分煮ると、豆の青臭みがとれて、大豆の蛋白質、油分、糖類、ミネラルなどが溶出する。呉汁を袋で漉し、袋の口を固く縛り、完全にしぽり出す。この濾液が豆乳である。
このしぽる所作を江戸川柳はおもしろおかしく表現している。
生捕つた やうに豆腐屋しぽる也
袋に残ったのが、「おから」である。最近、かん入り豆乳風飲料がスタソドで売られている。その味のまずさや添加物を気にするくらいなら、すりばちで豆をつぶして、自家製造したらいい。石臼がなければミキサーでも十分だ。少しぜいたくして軽くしぼれば、おからもおいしい。かつて豆腐は、家庭でつくるハレの食べ物で、正月やお盆などに自家製造した。石臼のたいせつな用途のひとつだった。いろんな豆腐があったと思われるが、いま沖縄に残っている豆腐はその原形をとどめているのかも知れない。にがりを入れてから、固めずにモヤモヤに浮いたままの汁である。
京都には、今も石臼で豆を挽く豆腐屋さんが、まだ何軒も残っている。豆腐臼独特の目立てを継ぐ代々の目立て屋さんもいる。豆腐臼は、水平軸式で、機械化されている。あるとき店舗を改装したお店があった。「とうとう時代の波におされたのですか」と聞くと「そやおまへん、まあみとくれやっしゃ」。サニタリー化、オートメ化と至れりつくせりで、呉はパイプラインで輸送され、ヒーターの温度も浸出時間もプログラム制御である。だが、石臼の工程と、にがりを添加して凝固させるところだけは、設備こそ新鋭だが、もとのままだった。 「今の機械のグライソダーに替えたんですが、お得意さんから豆腐の質が落ちたと不評でした。やっばりあきまへんわ」とのこと。グラインダーというのはセラミックス製のディスクが高速回転する。直径が小さく、回転速度が速い。円周部分の速度は伝統的な石ウスの十倍程度である。能率は格段によいが、高速のため、微粒子の微妙な組織をずたずたに切断する。鈍刀でも素早く振れば糸が切れるのと同じ理屈である。グライソダーの組織が粗くて、ここがバクテリアの巣になるおそれもある。最近、ニューセラミックスのグライソダーが超高速回転し、豆の皮も微粉にして収率を高める機械も出現しているが、こういうのはハイテクではなく、文化的ローテクである。
呉に、にがりを加えてかためる凝固剤も変化した。昔は塩から出たにがり(苦汁)を使った。家庭では塩をかます入りで買い、潮解して出る汁を受けて集めた。これは塩化マグネシウムを主成分としているので、昭和十年代にマグネシウムは戦略物資として使用が禁止された。代用として硫酸カルシウム(石膏)が奨励された。カルシウムは健康食という俗説を高名な化学者がとなえたこともあるという。カルシウムだけを摂取すれば、ピタミンも同時に消費されることは、わかっていなかったのである。硫酸カルシウムは凝固時間が長く、作業性がよいので普及し、当時は健民豆腐とよばれた。現在では、グルコン(グルコノデルタラクトソ)という有機化合物がつかわれている。ネオニガリともよばれる。これは熟練を要せず、低温で操作でき、水を抱き込むので収率も高い。伝統の豆腐の味が完全に消えた一つの原因である。箸でつまめない充填豆腐は工場での大量生産に適し、保存性も著しくいい。京都の店に二〇〇キロもはなれた地方で生産された豆腐が販売される。一方、しぽり滓(かす)すなわち、おからは、しぼりとれるだけしぽるから、味がだめになった。.2001年.9月9日(日)に京都で京豆腐の有名店を共催した。ここは今でも私が指導した石臼機械で京都と東京で石臼豆腐を市場に出している(http://www.kyuzaya.jp/zidouhu/ishiusu1.html,http://wwwe1.osakagas.co.jp/pr/dnkyoto/ha017.htm)。
6.6 湯葉と凍豆腐
ところで、上図はアメリカの豆腐の本(Shurtref著The Book of tofu(有名な本で本屋の棚にならんでいる)の表紙の絵だが、京都のゆば屋(湯葉半)のイラストである。豆乳をつくるまでの工程はまったく同じだが、その後、豆乳を蒸発鍋に入れてゆっくり蒸発させる。水の蒸発につれて、牛乳を温めるときのように、表面に皮ができる。頃合を見はからって、箸でひきあげることを繰返す。このままですぐたべるのがもっともおいしく、生ゆばである。私も、さっそく自作の石ウスをまわして造ってみた。本職がつくるのは手拭のように大きいが、私のはティシュペーパーみたい。でも味は一人前だった。いまや京都では最高級のぜいたく食である。乾燥したものが多いが、生とは比べ物にならない。これも石臼がなければミキサー豆乳で自作すればいい(これヒミツ)。
凍豆腐(高野豆腐)も、かつては西北の季節風が吹く寒中に、豆腐を屋外に吊して冷凍乾燥した。これも工場生産されて以来、往時の味は完全に失われた。鉱物の粉製品の乾燥用として発達した凍結乾燥や赤外線乾燥、電子レンジなどが食品工業にも応用されて、食品の味を台無しにした例は数え切れない。
 だんご屋(歌川国定「菊寿童1霞盃」文政10,草双紙<模写修正>
だんご屋(歌川国定「菊寿童1霞盃」文政10,草双紙<模写修正>
だんご屋(歌川国定「菊寿童1霞盃」文政10,草双紙<模写修正>
6.7 だんごの美学
京都の下鴨神杜には、本殿東に御手洗川(みたらしがわ)と御手洗神杜がある。土用丑(うし)の日には御手洗祭が行われ、参詣人がこの川に膝までひたり、無病息災を祈願する。
御手洗の みそぎはかみも うけじかし
みぎはまされる ながれとおもへば
(岩波日本古典文学大系74、歌合集古代編一六)
恋せじと みたらし川に せしみそぎ
神はうけずも 成りにけるかな
(『伊勢物語』)
御手洗に 影の映りける 所と侍れば、
(『徒然草』、上第六七)
とあるように、御手洗は、神様へ御参りするときの浄めの水場であった。かつて京都の下鴨神杜のお祭には、みたらしだんご屋が並んだという。言い伝えによれば、その昔、御醍醐天皇が、下鴨の御手洗川で水をすくったところ、泡がひとつ浮き、やや間をおいて四つの泡が浮きあがった。その泡にちなんで、指頭大のだんごを竹串の先にひとつ、やや間をおいて、四つ続けてだんごを刺す。これは頭と四肢をあらわすともいう。これを十串一束とし、熊笹で扇形に包んだ。
ところが関東のだんご、たとえば言問だんごや追分だんごは現在も四粒である。その理由は江戸時代に五粒で五文だったのが、四文銭が出て、四粒四文になったためという。今は関西でも四粒ものがある。
だんごにも美学がある。熟練した手づくりのだんごは、ひとつひとつのだんごに微妙な形の差がある。これを無造作に串に刺すと実にみっともない。私はある時だんご屋へ一晩弟子入りして挑戦してみてそれがわかった。だんごの名人は、いびつな形状のあつまりに、ひとつの調和をとる。私のつくるだんごは売り物になりそうもない。その目で今の機械だんごを見ると実に味気ない。ひどいのは串に棒状につけてから、プレスして形を整える。粉っぽくて、歯にくっつくだんごが.それである。最近京都の店頭でよく見かける。爪楊枝(つまようじ)で、だんごを離して見ると、だんごが、つながっているので簡単に見分けられる。
これは、形状の美学的問題だけではない。練る技術上の問題もある。だんごをひとつひとつ練れば、だんごの表面に力がかかり、これが、だんごのうまさを造り出しているこのことを教えて下さったのは思いがけない人物だった。鉄のだんご屋さんである。ボールミルの鉄ボール製造工場では、だんご屋にならってこの技術を開発したとのことであった。「これノウハウだよ」と。だんごのように真赤な鉄を丸めると、鉄のボールの表面が特殊処理されて、ボールの寿命が長くなる。その本家本元はその技術を棄てて形だけのだんごを造る。
御幣餅を食べる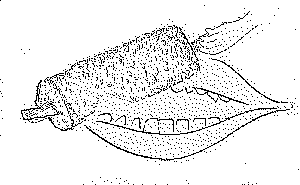
6.8 御幣餅の粉体工学
御幣餅は長野県上伊那郡宮田村の考古学研究者、向山雅重先生を訪ねる途中、木曾から馬籠へ至る峠にある「七平」さんを訪ねた。ここは御幣餅を食べさせてくれる峠の食堂として知られている。一九七八年の十一月高遠石工の調査の途中だった。四方山話をしているうち、御幣餅の話が出て、奥さんも詳しいつくり方を教えて下さった。先生のお宅は上伊那郡宮田村で、この地方一帯は、御幣餅が盛んである。「三河から信州の南部の伊那谷・木曽谷の山村でのご馳走にごへい餅がある。まず硬目に飯を炊く。いろりで大火を焚き鍋飯を炊く。よく煮えた鍋を下ろして少しく蒸らして置き鍋蓋をとり、すりこぎでご飯をつつき潰す。よくつついて飯粒の形が七分通り潰れたら、これをしゃもじで手に取り串へ握りつける。この串はサワラ材などを鉈で割り、少しく削った幅四センチ、長さ三五から四○センチほどの大きいもの。これを膝などへ挾み、掌ほどの大きさで、厚み四〜五センチほどに、しっかりと握りつける。これを囲炉裏の周りへ立てて並べたり、二本の棒の間へ串の尻をはさんで火にかざしたりして、焚き火の焔でよくあぶる。火がよく透って、いささかふくらみ気味になってくると、おいしそうな香りがしてくる。その串をとり、こんがり焼けたところへ味噌を塗る。ふるくは赤味噌であったが、後にクルミをいれてよく摺った胡桃味噌となったという。
春の芽吹き時だったらサンショウのわか芽を入れてよく摺った山椒味噌がいい。これらの味噌をたっぷり塗って、ふたたび火にかざすとまもなく、味噌の香りが漂ってきて、すき腹にしみる思いがする。それをめいめい選り取りにとって,串にかぶりついて食べる。食べたのがそのまま身になっていくようなうまさ。また、焼けあがったのを食べるというようにして、いつか腹力満ちて来て、うっかり立上れないほどになる。そっと後ずさりして、柱や壁に背をもたせかけたまま,しばらく談笑の花が咲くといった有様。
山小屋では、これができると、まず一串を山の神様にあげる。串の先に掌大の餅がついている姿は、ごへい(幣束)に似ているところから、いつか「ごへい餅」の名がついたのである。このおいしい御幣餅、いつか食が進んで「御幣五合」といって、一人五合は食べるといわれている。
山小屋で男手だけで作るこのおいしさを、里などで学びとって作るとき、大きい串がないと細い竹串などになってくる。その串へ握りつけるよりも、小さいむすび形に握ったものを、二つくらいづつ串にさし、煙であぶって焼くということになる。これがふしぎと伊那谷では二つざし、木曽谷では三つざしといった姿になって、山小屋風な大きい御幣餅を,いつか「山御幣」とか、「天王御幣」なとの名がつけられるようになってきているのは面白い。山村の暮しでは、白飯を食べるのは祝いの日ばかりで、常の食は、粟飯、稗飯、麦飯といった雑ぜ御飯か、うどん、焼餅などの類であった。それに味噌は蛋白塩分の補給の大切な食品。その味噌を最も経済的に使うのは味噌汁であって、味噌をよく摺り、むだなく味噌汁にする。生味噌をご飯の菜にすると、五人家内の味噌汁分ほどの量をひとりで食べてしまう。それで「大名でも味噌贅はならぬ」といわれてきたという。その味噌を焼くといい香りがしておいしく生味噌よりも食い込んでしまい、一そう不経済になるので、「焼味噌するとエビス様がいやがる」ということばさえあるほどである。そうした貴重な白米を炊いた白飯を潰してこんがり焼き、大切な味噌をたっぷりつけて焼いた御幣餅、これこそ正にご馳走なのである。
5.9 御幣餅を作る実験
翌日は大学へかえってさっそくつくってみることにした。串は大学生協から割箸をもらってきて、これを割らずに平たいままでつかった。ごはんは少し固めに炊いた。これを擂鉢と自製の擂粉木で潰した。いずれも臼狂の七つ道具だ。胡桃(くるみ)がないときは、胡麻味噌でもよいというので、生胡麻を炒り、磁製乳鉢ですった(胡麻を乳鉢でするとうまいのは、私の最近の発見)味噌は八丁味噌をつかう。
さて、ごはんを箸につける段になって、これがなかなか難しいことがわかった。向山先生が「素人は掌大の大きいのをつくらず、小さいむすび形のものを三つくらいつけなさい」といわれた意味がわかった。でも私は無理して「七平」さんで食べたような掌大にしたから、いざ焼く段になって、こわれてきて苦労した。限られた串の面積に粒の付着力を最大にするにはどうするかという問題である。掌大どころか、鬼の掌大のもつくるというからおどろく。このときは串の面積はいくらにするのだろうか。ここで粉体工学の物性試験法として、串に握りつけてこわれる限界を,串の面積と付着総量との関係を調べてみたらどうだろうと考えてみた。
6.10 稗だんご
ひえだんごといえば、江戸時代の貧農が飢えをしのいだ食べものと思われがちだが、私は、20数年まえにダム建設で水没する岐阜県揖斐郡徳山村で、稗の種を入手した。育種研究室で鑑定してもらい、それがわが国古来の「"シコクビエ」だと知り、栽培してみた。当時は母が田舎で生存していたので、栽培を頼んだ。先祖代々人間の手によって栽培されてきた栽培種なので、播種、移植と手をかける必要があった。「稗など栽培したら,
田んぼに被害が出るのではと心配した人もいた。日照りつづきの年にも生育はきわめてよい。稗刈りの頃には、強靱な茎になって、稲刈鎌などうけつけない。昔、徴兵検査があった頃「稗食の村の壮丁の体格は抜群」といわれたのもなるほどとうなずける。さて、精白法はいろいろあるが、ぜいたくな方法を実施することにした。石臼で粉砕し、皮の部分は捨てるのである。古文書によると、白い粉は地主に納め、皮を自家消費したというから、ほんとうは、バチがあたる食べ方だ。いまどき食べてくれる地主もいないから
これを団子にして食べてみた。砂糖を入れなくてもほのかに甘く、なつかしい郷愁を誘う珍味だった。中尾佐助先生が、私にこういわれた。日本は世界の博物館ですよ。なんでも残っている。正倉院に限らない、全国を歩きなさい」と。現在でも各地に稗を栽培している研究グループがあるようだが、縄文時代の栃の実やどんぐりの食べ方グループの存在などとともに、日本のどこかで、味の多様性が残っていることはすばらしい。
私は稗の種子を10年ほど保存していたので、もう一度播種してみた発芽しなかった。そこでダム建設で徳山村から離村した人を探し出して、稗の種子を入手した。すでに母は他界していたので、同じ村の叔母に栽培を依頼した。大いに期待していたが、生育こそ盛んだったが、まえの味はなかった。実にまずい。「なぜでしょう」と雑穀研究会の総会で話題にしたが、多分それは種類が違うか地質の差だろうということであった。同じ稗だけでも種類は複雑で何十という種があるという。
mochifukei.gif
6.11 集団行事としてのもちつき
食事とは、単に満腹感を与え、栄養を摂取するだけが目的ではない。そのことを考える一つの行事が、私の研究室にあった。毎年十二月二十六日に実施しているもちつき大会だった。たくさんの道具が必要になるが、臼や杵などの道具類は、使わないとダメになるので、保存の目的ではじめたのが恒例になった。博物館のように展示したまま、または収蔵庫に入れたままにしておくと、道具はまもなく乾涸びてミイラになってしまう。
上図のようなもちつき風景が普通だが、熟練を要するもちの「手がえし」作業が必要である。ところが千本杵は、一挙につき上げるので、その必要がない。横杵のような危険も伴わないので、子供(幼稚園児)が飛入りでつくこともできる。臼も弥生時代以来の胴の部分がくびれた臼である。くびれには十二枚のひだがある。十二支の思想であろうか。 江戸時代中期頃、都市部から太鼓胴に変り、杵もハソマー状の横杵にかわった。これには理由があった。かつてもちつきは、多人数が集まる集団行事だった。それが次第に家庭毎に行うようになった。そのため個人プレイが多く、多勢の場合には座がしらける。それに比べると、千本杵は集団行事の光景が展開する。もうひとつ大学独特の秘密もある。千本杵はかつてのゲバ棒の変身で、角材の角を削って作ったもので、一九八二年で十回目になった。毎年、学生が新しくなるので、熟練者に期待するわけにはゆかない。現代の学生諸君は勿論もちつきなんか経験がない。そこで、次ぺージの表1のように役割分担を明確にして、何日も前から準備万端整える。集団でひとつのことをやる訓練になる。
当日は多くの学生があつまる。現代には、このような集団行事がないので、学生達は、はじめとまどうが、まもなく大変盛りあがりを示す。ふだん、あまり目立たない学生が意外な行動力をもっていたり、女子学生だけで一臼をつきおえて、歓声をあげ、通りがかった教授連を巻き込んで気勢を上げるなど、クールになりがちな人間関係が、突如として改善される。そこには、セレモニーあり、コミュニケーションあり、遊びと楽しみがある。それは、食べる過程よりも、食べ物をつく過程に含まれていることがよくわかった。
こうして、わいわいガヤガヤ、食べ物をつくりながらさわぐのは、人間の本来の姿である。あるとき、電気もちつき機械がいいと主張する学生がいた。そこで新しい機械を購入し、彼が、むこうを張って実演した。ところが、まったく人気がない。やむなく杵臼の餅にまぜてならべたが、すぐ学生たちに見やぶられて電気もちつき機械は売行きはさっぱりだった。比較すれば新人類にも本物はわかるらしい。また餡この会社の社長がただで餡こもちをサービスしたが、こちらも派遣された社員さん達はサッパリで気の毒だった。
6.12 八丁味噌
味噌に関する日本最古の記録のひとつ東大寺古文書,尾張国正税帳に「天平2年,尾張国から未醤弐斗壱升を朝廷に納めた」とある。『味噌沿革史』(川村渉編,全国味噌工業協会刊,昭和33)に詳しい考証がある。「味噌の字が現れたのは平安時代のことで,奈良時代には「未醤」と書くことが多かった。
夏季は高温多湿で腐敗しやすい尾張,三河地方の気候風土は,大豆だけを原料とし,米や麦の麹を用いない味噌を発達させ,その伝統は三州味噌,三河味噌の系統をひく八丁味噌につながっている。手前味噌」の言葉が示すように,味噌は地方性が濃く,よその味噌にはなかなか馴染みにくいものである。八丁味噌も,そのくせの強い香と味のために,愛知,岐阜,三重の三県を除いてはあまり一般化せず,他の地方では高級料亭や味噌通の間で愛用されるにとどまっている。
天皇家は,もと京育ちだから京の白味噌を連想しがちだが,意外にも八丁好みだという(雑誌『ウーマン』(昭和54年1月号「皇室御用達の品々)。その納入元,岡崎市八帖町(古地名八丁)の八丁味噌カクキュー合資会社(旧名早川久左衛門商店)を訪ねて確認した。この店は創業が中世まで遡る老舗で、明治25年以降「宮内省御用達」の木札をかかげる八丁の本家で現在も年間3、4樽を皇室へ納めているという。振動篩機、ソーティングテーブル(異物選別機)などを使う大豆の精選から,水洗,浸漬,蒸煮,玉握りまでの工程は,いずれも粉体処理機械で近代化され、原料大豆の90%以上が風味に欠ける輸入大豆になっているなど,昔の趣はないが,建物や熟成のための樽を並べた倉庫は古い伝統をそっくり残していた。
玉握りは味噌玉をつくる工程で,昔は蒸した大豆を臼に入れ杵で搗いたものである。豆の臭いが鼻をつく,その厳しい労働の 体験は自家製味噌造りで筆者もあるが,現在は混練機から直ちに味噌玉が出る連続作業になっていた。出てきた味噌玉は摂氏35度の恒温麹室に四日間入れて嫌気性菌による醗酵が行われる。これを荒砕きしてから,水と食塩を加え,30石人りの大きな樽に入れるのだが、これから先は江戸時代そのままなのがうれしい。現在使用中の大部分の樽は,慶応年間から昭和初年のもので,吉野杉に見事な竹の組みたが嵌った文化財級のしろもの。約6トンの味噌を入れ、その上に人頭人ほどの丸い石を約3トン積みあげて重しにし,2夏以上、約三年間熟成する。蔵には約600本の樽がある。
信長も秀吉も家康も三河,尾張の地で育ち,豆味噌のエネルギー源で天下をとるスタミナを養った。筆者には天下をとる必要などないが,中京育ち故に,八丁味噌なしでは日が経たない。信州味噌の本場に住んでいた頃も,今、白味噌の京都でも,八丁の粒味噌を樽から出して秤り売りしてくれる店を探しあてて,八丁を切らさないようにしていた。粒味噌で味噌汁をつくるときは,必ず摺鉢を使う。はじめは水を入れずに,つつきながらよく摺る。次に少しずつ水を加えながらのばしてゆくのがこつ。こうすれば味噌滓は全く出ないから,味噌漉しは不要。へたに味噌漉しをつかうと味が変る。白いカビのようなものが浮くが、これを「ささみ」とか「ざみ」といい,これは僅かに渋味を呈して,八丁の味の秘密を握るひとつの重要成分だ。その主成分は,チーズの中に発見され,チロシンと名づけられた蛋白質構成アミノ酸のひとつである。網や布で漉すと,吸着により失われやすい。粒味噌を固めて庖丁で刻み、布で包んで,おつゆのなかでゆり出したのを「赤だし」という。高級料亭向きのぜいたくな食べ方だが,八丁独特の「くせ」がぬけるので一般向きする。パックされた「赤出し八丁」は,ずばら族向きだから,熱処理により死んだ味噌で,ぐっと味がおちる。ずぼら族向けには豆味噌を潰した漉し味噌もある。すりこぎ摺小木も,せっかいも使いこなせぬ物臭じゃ天下はとれないが。
6.12 あるおでん屋さんのつぶやき
以下はあるおでん屋さんで聞いた独り言である。
おでん」は「御田」と表記し「御田」すなわち 「田んぼ」にも似たりというところから赤味噌で煮込んだ名古屋の郷土料理が元であり、 現在 一般的な「おでん」(関東炊き(煮))は、
その昔 堺に渡ってきた渡来人(広東人)が浜辺で煮炊きしていた異国の鍋料理を 「広東炊き(煮)」とよび広まったという。
「八丁味噌」も 「極上品」を除けば 輸入大豆に頼らざるを得ないという。国産大豆のみで 醸造しようと思うと 現在の価格では到底無理。 「国産有機大豆」のみで造る樽もあるが
生産量も少なく高価な物になってしまう。現在 殆どの「赤味噌商品」が 圧をかけて絞る(擂るとは言わない)ペースト状の商品なのは 原料に 輸入大豆を使うためだ。理由は
輸入大豆の流通経路が問題のようだ。船の荷室の問題か 米国での荷造りの問題かはしらないが,「大豆」に 本当に微々たる程度だというが 若干量の「とうもろこし」が混入してくるらしい。「豆味噌」の状態で出荷した場合
「輸入大豆を使用しています」と公表していても その辺りの事をご理解頂けない為「何故 とうもろこし が入っているのだ!」と 「異物混入」でクレームが出るらしい.。「国産有機大豆」のみを使用し醸造した味噌は
問題ないので「豆味噌」の状態 若しくは 「手で擂った」状態で 出荷している。そう言う問題を気にしない蔵は そのまま「豆味噌」で出荷しているようだ。
経済第一主義の時代は終わったので、これから日本の伝統の生活文化をベースにした文化の時代になると思っている。何よりも 「味のわからない世代」の出現が心配だ。
6.8 遺伝子組み換え(GM:Genetically Modified Organisms)食品
最近特定の除草剤をかけても枯れない遺伝子を組み込んだり、殺虫毒素をもつ微生物の遺伝子を組み込んだ大豆や菜種、トウモロコシ、綿などがアメリカやカナダ、アルゼンチンで栽培されている。日本に大量に輸出され、そのほとんどが表示のないままに日常の食卓に上っている。大豆、ナ菜種、玉蜀黍、綿実、馬鈴薯、トマト、甜菜、スクワッシュなどがそれ。詳しい情報はhttp://www.yasudasetsuko.com/gmo/faq.htm#78にある。
飼料にはもっと多くの組換え作物が使用されている。欧州では餌に組換え作物を使わない畜産品・乳製品が販売される動きが広がっているという。NON−GMOミルクとかバター、ハム・肉などがそれ。
6.8 遺伝子組み換え(GM:Genetically Modified Organisms)食品
最近特定の除草剤をかけても枯れない遺伝子を組み込んだり、殺虫毒素をもつ微生物の遺伝子を組み込んだ大豆や菜種、トウモロコシ、綿などがアメリカやカナダ、アルゼンチンで栽培されている。日本に大量に輸出され、そのほとんどが表示のないままに日常の食卓に上っている。大豆、菜種、玉蜀黍、綿実、馬鈴薯、トマト、甜菜、スクワッシュなどがそれ。詳しい情報はhttp://www.yasudasetsuko.com/gmo/faq.htm#78にある。
飼料にはもっと多くの組換え作物が使用されている。欧州では餌に組換え作物を使わない畜産品・乳製品が販売される動きが広がっているという。NON−GMOミルクとかバター、ハム・肉などがそれ。下記は大部分が外国からの輸入に頼る飼料の生産量である。
.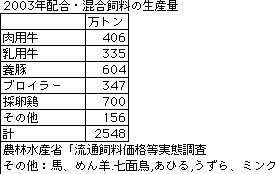
9 トイレのお話
美味しい物を沢山食べた。そこで自然にトイレと言うのは昔も今も変わらない。
第1章で糞体工学といたずら書きしたのが、いよいよ下表で現実になる。
前著『粉の文化史』(法政大学刋,1987) には日本国のマテリアル バランスと書いた部分だ。2003年のデータで計算し直したのが下表である。単なる数字の比較だが、日本国の家畜の糞尿だけで一億トンに迫っている。この1億トンとは日本の年間鉄鋼生産1億4千万トン(2002年),セメントの約9,000万トンに匹敵する数字だ。そして日本の総人口1億2767万人と対比すると、マテリアル バランススは大丈夫かなと心配になる。