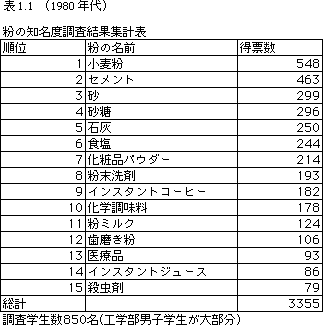
リンク:第2章人類史一万年|第3章火薬製造工場|第4章石臼伝来|第5章粉の文化|第6章食文化|第7章ダイナミックス|第8章二十世紀を演出|第9章鳴き砂|第10章ナノ微粒子|
粉の文化史
第1章 粉とは
小麦の粒を"粉"に挽き、麩(不純物)を除去して"白い粉"をつくり、この粉(素材)を捏ねて、形を整えて焼けぱパンになる。順を追って述べるように、陶磁器も、絵具も、金銀財宝も、茶の湯も、その他すべての物が原点までたどれば、みな"粉"づくりから始まっている。本書は、素材としての"粉"に注目して人類の文化史を古代から現代まで見直す試みである。このような視点に立つと、文化の台所、あるいは舞台裏に入りこまねばならない。これはいつの時代にも隠された部分、あるいは人に見みられたくない場所だったから、記録にはほとんど残されていない。華々しい鉄砲の歴史は書き留められても、火薬については記されない。金銀財宝の記述はあっても、金銀鉱山の粉づくりの歴史は闇に葬られている。いうなれば文化の台所に踏み込むわけだ。
難しいことであるが、私が見た考古学的遺物と、あいまいな記録や文書とを考え合わせていって文化の裏方さんの歴史を掘り起こして見るのが本書である。現代のハイテクもまた、現代科学の粋をつくして、おそろしく手のこんだ"粉"(パウダー)を造るところからはじまるが、何のことはない、それを捏ねて、固めて(成型)、焼いて(焼結)と、誰にでも理解できる工程が展開している。
物質の種類を超えて製造工程の共通性に注目する"粉"の概念は、ものと人間の文化史を探る有力なキーであり、同時に現代技術を理解するキーでもある。そして、"粉"にはじまり、"粉"に終わる現代を眺めて、人間とは何かについて考えてみるのが本書である。
1.1 粉占い
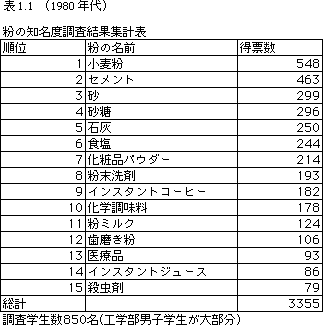
表1-1は1985年にNHKの教育テレビ市民大学講座『粉の文化史』で発表し、1987年刊の拙著『粉の文化史』に出したデータである。主としで学生諸君(理系も文系も男女を問わず)を対象に調査集計した結果だ。私の講義のはじめに「思いつくまま粉の名を書きなさい」と命じた。所要時間1O分間。いくつか違う教室で総数850人に行なったが、トップ5位までは、その順番まで、ピタリとー致した。多くの学生が粉といえば小麦粉を連想したのはなぜか。いろんな人にこのデータを見せてコメントをえた。これは明治の文明開化期にアメリカから小麦粉が来たとき、日本人はそれが真っ白だったので驚いた。その記憶が長く伝承されてきたのではという説がもっともらしかった。私のような昭和の世代の者にも、粉といえば小麦粉と遺伝子のように伝承されてきたのだろうか。
同じ質問を西洋人にしたら、肩をすくめるゼスチュア付きで黒いパウダー(火薬)をまっさきに挙げた。数人のイギリス、アメリカ、ドイツ人などがそうだった。確かにパウダー(powder)は辞書を引けば粉、火薬とある。日本人ではまず火薬は出てこない。平和の国だからでもなかろうが。
ところが、約20年後同じ質問を学生にしてみたところ、すっかり様子が変化していた。小麦粉のトップは不変だが、セメント、石灰といった生産材が殆ど出てこなかった。その代りに、各種インスタント食品など、こまごまとしたものがいっぱい。すでに学生の「粉」の認識は一変していた。まさに消費文明時代である。現代生活は完成品に取り囲まれ、粉状の素材を扱う仕事はすべて工業化された。コンクリートブロックは見ても、素材のセメントや砂利は見ない。いわんや、家庭で粉を挽く風景など、昔話の世界でしかない。歯磨き粉も粉ぐすりも現代の若者たちは知らない。粉のままでは嫌われるので、練ったり、錠剤やカプセルになった快適な生活である。
当時小麦粉と答えた学生諸君もそろそろ定年を意識している頃だ。2002年に入ってから粉の話題で民放のお笑い番組に呼ばれることが重なった。それは粉の話が一般大衆にも広がったと喜ぶべきか。NHKは別としても、とりわけ民放の程度が落ちたのか、それともお笑い番組に出るなんて研究者としての堕落なのか?気になったが、わるい話でもないので、引き受けた。大阪で漫才師との対談があった。生放送だった。打ち合わせのとき対面するや否や紙切れを渡して、10分間かけて、これに思いつくまま粉の名前を五つ書いて」というと、「いきなり試験ですか」といいながら書いてくれた。隣にいたアナウンサーの女性にも書いてもらった。なんとほとんど粉の食品(商品)か、お化粧品だった。ただひとつ一番年増の漫才師がセメントを書いていた。このようなテストを私は粉連想、または粉占いと呼んでいる。初対面の人に聞くと,だいたいそれでその人の職業や趣向のおおよその見当がつく。時代は変わったと実感した。
だが日常生活から「粉」の姿は消えても、世の中から粉が姿を消したわけではない。むしろその逆で、工場では、粉の状態で扱う物質の種類も量も飛躍的に増加し、粉の技術(パウダーテクノロジー)の重要性は、ますます高くなっている。食品や建材からテレビ、コンピューター、冷蔵庫、自動車に至るまで、それらの原材料を生産する工場へ行ってみると、製造工程で、さまざまな粉が扱われている。ただし、それらの粉状の素材に直接に接触する立場にある人は、極めて限られているから、自分の職場の粉は知っていても他の分野のことはわからない。これでいいのか。その危機感が本書を出す気になった第一の理由である。
1.2 粉と粒の差(粉粒体)
ところで粉占いのときよく出た質問は、「砂も粉ですか」だった。粉と粒はどうちがうか。難しい定義や規則があるわけではないが、肉眼で粒々が見えれば粒、粒々が見えず、正体がよく分らない、ボヤツとノッペリしているのを粉だという。その点日本の漢字は立派だ。粒は米が立つと書く。粉は米を分けると書く。その通りだ。そこで工学の世界では粉と粒をまとめて粉粒体という。粉粒体工学では面倒だから簡単に粉体工学ということが多い。ちなみに大学で研究室の看板に粉体工学研究室と書いたのは、同志社大学が日本初だった(1966年)。当時私を同志社大学へ紹介した京都大学工学部の井伊谷鋼一教授の研究室ではまだ粉体工学と呼べなかった。国立大学の悲しさで制御工学と呼んでいた。教授曰く「いいなあ、私学は」。
粉のことをわざわざ体という字をつけくわえる訳はどうしてか。物理学では物質に液体、固体、気体の三態があるが、それにもう一つ粉体を付け加える必要があるからだ。そう言い出したのは科学随筆で著名な昭和初期の物理学者寺田寅彦先生であった。
「要するに此等の問題の基礎には”粉”といふ特殊な物の特性に関する知識が重大な与件として要求されるにも拘はらず,其れが殆ど全く欠乏して居る。さうして唯現象の片側に過ぎない流體だけの運動をいくら論じて見ても完全な解釈がつきさうにも思はれない。粉状物質の堆積は,瓦斯でも,液でも,弾性體でもない別種のものであって,此れに対して「粉體(体)力学」があるべき筈である。近頃,土壌の力学に関連して大分此方面が理論的にも実験的にも発達して来たやうではあるが,それは併し殆ど皆静力学的のものであって,粉體の運動に関する研究は皆無といっても過言でない。此の新しい力学の領域に進入する一つの端緒としても上記の如き諸現象の研究は独自な重要意義をもつであらう。」(寺田寅彦:科学,3,77-81(1933)”科学雑纂、自然界の縞模様”)
粉とはもう少し正確にいえば、粒を見分ける人間の目の視力の限界、すなわち、目の解像力は大体10分の1ミリだ。このあたりが、日常語の粒と粉を使い分ける境目であろう。ところが肉眼のかわりに顕微鏡を使えば、lOOO分の1ミリぐらいまで粒を見分けられるし、さらに電子顕微鏡なら、もっともっと細かい粒が見分けられる。現代の技術はますます細かい粉を追求し、21世紀のハイテクは超微粒子、1万分の1ミリ、すなわちナノメートルの世界、さらにはそれ以下に踏み込んでいる。それが現代の粉の科学である。
ついでに日常語の粉と粒の区別にこだわらず、なんでもバラバラの状態、たくさんの粒の集りを「粉」、専門用語では「粉体」と呼ぶことにすれぱ、大変便利なことがある。扱う物が、石であろうが、食品であろうが、みんな粉、扱い方は共通しているから、一方の技術で他方の技術を考えることができる。これをテクノロジー・トランスファー(技術転移)という。日常語では粉といえば細かいという感じがあるが、本書では粒の大きさには無関係に"粉"と呼ぶ。そう考えると至るところに粉が見えてくる。思いがけないものにも共通性を見出して、アイディアが湧く。粉の発見は人間の知恵の発見でもある。
このようなものの考え方は幼児教育の段階で教えるべきと思う。そのために拙著絵本『粉がつくった世界』(福音館、1999)がある。この本は家庭内にひそむ粉からはじまって、いきなり旧石器時代に入り、エジプト文明-ローマ文明を経て、中世ヨーロッパ、中国の中世、戦国時代、江戸時代、そして現代のゴミ文明までを絵ときしている。この本の最終ページは私が工場建設の顧問であった縁で採用した奈良のゴミ処理工場の絵である。ここまで来ると「糞体工学」と落書きする失礼な学生も出るが、「ウン」と返事すると学生は「参った」という。
1.3 なぜ粉にするのか
小学生用の粉の話は「粉と生活」という題目で光村書店の文部省検定済の5年の国語教科書にあったが、2001年に別の題材に変わった。2003年にもそれが学習書のドリルの材料や入試問題に利用されたりしていた。中でも石臼の目の記述はなんと某大学の国語入試に出たものだ。
なぜ細かい粉なのか、第一の理由は細かくなるほど、固体の表面積が増えることである。
このことを理解するには、下図のような模型が分りやすい。
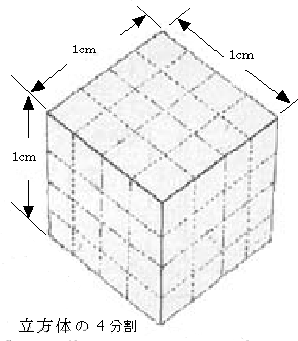
各辺を4分割すると4×4×4=64個の立方体になる。図のように一辺一センチの立方体を、次々に一辺が1/2の立方体に分割してゆくと、表面積は分割ごとに倍増してゆく。この計算はまじめに考えないと間違う。(私の友人で粉体工学の大教授だった名古屋大学の故神保元二教授もそうだった。結果は過少だった。「先生が間違えたら困りまっせ」とそっと手紙を出した。返事はなかったが、改訂版『粉体の科学』で直されたかどうかは知らない)。一辺1cmの立方体の表面積は6平方cm、これをを各辺1/4cmに分割すると表面積は4倍の24平方cm、これを繰り返し各辺1ミクロン(10000分の1cm)に分割すると表面積は10000倍の6平方m,さらに10万分の1cm=0.1ミクロンになれば60平方mになり、狭いながら分譲住宅ができる広さになる。さらに21世紀の粉は1ナノメートルというからすごい。計算は読者にまかせる。(三十六畳敷の面積になる。)まさかと思う方はこの計算を確認してほしい。ひとつまみの米粒でも細かくすればものすごい表面積をもち、空気に触れると爆発することもある。
NHKのクイズ番組で、煙硝蔵を爆破しようと潜入した敵の忍者を逮捕したところ、変な粉を持っていた。それがなんと米の粉だった。米の粉で爆発させるなんて、なぜだ。私が説明に出されたので、米の粉を爆発させる実験をして見せた。ドカーン。(2004年にも同じ人たちがテレビでやっていたから、ご覧のかたもあろう。)ただし、東京のスタジオでぶっそうな実験をするのには消防庁の許可をうける必要があった。そんな危険なことを見せたら誰でもまねする奴がでるのでは?という声もあったが、素人では無理だ。わたしも大学へ帰って実験してみたが、爆発しなかった。実はこの実験をやったのは日清製粉の粉塵爆発の専門家だった。第一非常に細かい小麦粉は専門家でなければ作れない。
金属の粉も、その他なんでも細かくすると爆発する。この実験の粉は超微粉ではないが、もっと細かくなると一ミクロンのまたその千分の一のナノメートル(nm)という単位が使われる。超微粒子というのは一ナノメートルから一〇〇ナノメートル程度の粒子をいう。それくらい細かくなると、まったく違った種々の性質を示すようになる。たとえば構成する原子のうち、かなりの割合が表面に露われ、結果として、特異な機能、性質を示すようになる。これを利用して多様な機能を有する新素材が開発できる可能性があるから、いま世界中が注目している筈だ。.
1.3 京都にあった私の研究室
粉占いのとき、ぜひ書いてもらいたいと思うが、出てこなかったのが、土である。「土もコナですよ」というと、コナの専門家でも「エッ」という。あまりありふれていて、あたりまえで、忘れているのだ。
1969年7月、アポロ宇宙船で月面に歩をすすめた飛行士の第一声は「あ、パウダーだ」だった。月には水がないから粉が月面を覆っていた。そうだ地球の大地は水に濡れた粉なんだと私自身あらためて再認識したものだった。地球は水に濡れた土に覆われている。水をなくすれば(乾燥すれば)粉になる。地球の大地も粉なのである。
粉なる大地には粉ゆえに微生物の王国がある。そしてその上に土から生まれ土に帰る人類の文明がある。今や都会では園芸用の土をデパートやスーパーで売っている時代になった。
同志社大学工学部は烏丸今出川、京都御所の北に隣接していたが、そのキャンパスも年々舗装がすすんだ。樹木の根元に、わずかばかりの土が顔を出しているだけになった。秋に銀杏の葉や実が落ちても、その風情を観賞する間もなくセッセと掃除されてしまう。クルマが踏みにじって醜くするからだ。ただ一箇所、草が生いしげり、落葉が堆積するにまかせている一角があった。以前私の研究室はそれに続く場所だった。かつて薩摩屋敷の桑畑だったところで、残っていた一本の桑の木が夏には実をつけて学生諸君が口元を赤くして食べるのを皆楽しみにしていたものだ。
重要文化財の赤レンガの建物に隣接し、生物学教室の実験用動物(いもり)の池があって舗装をまぬかれていた。ここには季節があり、春はタンポポ、夏は、十薬(どくだみ)、うらじろ、よもぎ、水引き草、秋には、すすきの穂がゆれ、彼岸花が顔を出し、漆の葉の紅葉が美しかった。昔はどこにもあった植物である。大学に隣接している冷泉家の庭も、ここと同じ状態になっていた(最近は整備されたが)。
ここはひと昔まえの京都のありふれた景色だった。私の友達のミミズや蟻やダンゴムシ、などなど、たくさんの昆虫が住み、縁の下には私が大好きな蟻地獄が住んでいた。いまどきはお寺か神社でないと住んでいない。ときには蛇もきた。あるとき私を訪ねて来たお客さんが真っ青な顔で私の部屋へ飛び込んで来た。「アー驚いた。キャンパスに青大将がいた」と。野良猫がなぜか気にいって、住みつくこともあった。落葉は、しばらく虫たちの隠れ家になってから腐敗して、土にかえる。ここの土は鴨川の氾濫で堆積したから砂が多かった。2メートルくらい下が室町時代、その上にも下にも京都の歴史が埋っていた。室町時代の地層から火事で焼けた茶わんに混じって茶臼の破片も出た。
その頃(1985年)NHK教育テレビで粉の文化史の取材のためここから採取した土から砂を除去した細かい土は、乾燥させてからほぐすと、フワフアの粉になった。その粉は、いまどきハイテクで花形の超微粒子に匹敵しそうな細かい粒子も含んでいた。その泥水はいつまでたっても上澄みができなかった。これは超微粒子だ。母なる大地の土は、まさに粉そのもの、粉なる大地であり、粉ゆえに生命が宿っていたのだ。
「そこは舗装はしないとして、せめて芝生にしたら」という大学の事務所の忠告もあった。なぜ雑草がいけなくて芝生がいいのか、私には理解できないが、なぜ芝生がいけないのか、すぐには理解できないひともいた。ある強制力がかかりかけたときは、「舗装するなら私の顔に舗装してからにして」と言い放ち、工学部が郊外(京田辺市)の田辺校地に移転するまで安泰だった。移転した翌年元の巣を訪ねて見たら,待っていたように私が大切にしていた大地は見事にアスファルトで覆われ、学生が語らうベンチが並んでいた。
人間はもともと土の上で生きてきた。道を歩きながらふと気づいたことだが、土の道は歩くとデンデンとかすかに足音が聞こえたものだ。コンクリートなどで舗装された道ではトボトボという音がする。ここで思い出したのは私がNHKで土の話をした直後、京都にある船舶の舗床材のメーカーの方と広島の同じようなメーカーの方がそれぞれ訪ねてこられた。遠洋航海の船舶の甲板用には特別な配慮がいる。コルクの粉砕屑を混ぜた塩ビ板が使われている。「鉄板だと乗組員が殺伐になって喧嘩が多くなるからだ。なにかよい方法はないか」と。頭脳に伝わる振動が影響するらしいという。そういえば2002年頃からに目立つ険しい世相もそのせいかと思いたくなる。
 図1.1 桑の木の下は夏も涼しい蔭をつくてくれた
図1.1 桑の木の下は夏も涼しい蔭をつくてくれた
1.4 石工修業の場は学問の交流の場だった
私がこの場所にこだわったのは、本書で述べる石臼の加工場になっていたためだ。桑の木の木陰は最高の仕事場だった。この脇に一般教養の学生や教授達が行き来する通路があった。同志社では専門課程の教授も一般教養の科目を分担したので、全学の教授が往来していたことになる。偶然だったがそのことが大変な学問的意味があった。 今どき石屋が仕事している光景は珍しい。そういう場所には見物客が集まるものだ。大学のキャンパスとて例外ではない。あるときジッと見ていた人が「こんな仕事をやらせているのは誰ですか」と聞かれた。「私自身ですよ」と答えると、「エッあなた教授ですか」といわれるから、「そうです」と答えると、「実は私は古代法が専門ですが律令などに意味不明の語があるのですよ。「碾磑」といいましてね、どうもこの石臼らしいのです」。私はそれまで全く知らなかったことだ。「すぐ文献をもってきますよ」。この出会いが私の研究にシルクロードを越えてヨーロッパに至る新しい道を拓くことになろうとは当時思い掛けないことであった。
またドイツ語の教授はドイツには石工の遍歴という制度があったことや、水車小屋の娘という歌があるからとレコードを持参していただいた。神学部の教授は旧約聖書に鳴く砂の山の話が出ているという耳寄りな話を、などなど、思いもかけない分野から情報をいただいた。なかでも考古学の森浩一教授との出会いは私を思いがけず古代史にまで誘う重要な意味があった。森教授は「室町時代まで石臼の歴史は遡るのではないですか、実は京都市内で出土したのですが、それを裏付けしたいんです」と。それまで考えてもみなかった、石臼の日本史への本格的な道が拓けた瞬間だった。
1.5 母なる大地は微生物のマンションだ
では、粉としての、どういう性質が生命を宿すのであろうか。ゆたかな土壌は1ミクロン以下の微小粒子が集まって、ゆるい塊、すなわち顆粒をなしている。それがまた、たくさん集まって、複雑な隙間のある土壌の団粒構造ができあがっている。
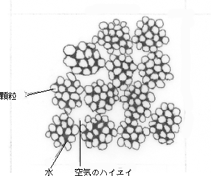 図1.2。土壌の粒子構造
図1.2。土壌の粒子構造
土壌の粒子構造
細かい粒子ではカチカチに固まるが、この顆粒と適度に混じっている砂粒子がそれを妨げる。この微妙な隙間の性質に土の機能の秘密がある。顆粒の間には大きい隙間があって、空気と水が行き来する。大きい隙間は水と空気のハイウェイ、小さい隙間は水を強く保持する小路地である。こうして土は水の保持と水はけという相反する機能を持つことができるのだ。
吸い取り紙が水を吸うのは毛管現象だが、土も粒子間の隙間が、毛管の役割をする。土の中の水は想像以上に高い減圧状態にあり、土の種類や状態、細かさによって、水を引っぱる力はさまざまだが、そのおかげで、晴れた日が続く真夏でも、土の表面は空気より低い温度に保たれる。道路が舗装された京都の夏は昼も夜もたまらない暑さだ。冷房がなかった時代は、さぞかし大変だったろうと思うが、そうではない。今でも京都御所や大きなお寺へ行けば、樹木が多く、床が高いので、縁側に坐れば快適だ。舗装して住みにくくし、莫大な金をかけて冷房して、クーラーから発生する熱風は隣の家へ追う。どう見ても合理的ではない。そのあげく危険承知のうえで原子力発電所を作らねばならないのが現代文明だ。
大地が粉であるゆえに、ここには無数の微生物(主として土壌菌)が棲んでいる。豊かな土壌一グラムの中には驚いたことに数千万から一億もの生命が宿るという。まさに微生物の王国がそこにある。そしてそれが大自然の物質とエネルギーの完全な循環系を形成している。ところがあたかも、この微生物に依存しない人間の文明が可能であるかのごとく、21世紀になっても日本中でベター面の舗装工事が限りなく進められている。クルマが通りやすいめ、コストが安いため、なんと単純な20世紀的発想か。
下図は1970年代の学園紛争時代のムードがあるが、当時、私がある雑誌に描いたマンガである。
 図1.3 1970年代の舗装反対斗争
図1.3 1970年代の舗装反対斗争
最近ではアスファルト舗装をはがして隙間のあるレンガで舗装し、水が土に浸透するようにする工事を見かけるようになった。この絵そっくりなのでうれしくなる。だが、まだ都市の大部分はコンクリートで塗り固められ、雨が降ったら、水は土にしみこむことなく、ただちに下水道に入り、つぎにこれもコンクリートで固めた川を経て、海へ注ぐ。ときに大水害をもたらす。土にしみ込んで、水が
土を洗い微生物を養う作用は全く果せない。これを.Run off Pollution(流れ出てしまうことによる汚染)という。そのかわりに各種の有毒物質が浸み込み、土壌菌の王国を絶えず侵略している。
京都は日本中でも特別に汚染がひどいので、井戸水を飲料水に使わないようにと、お触れが出た(ずっと昔の京都新聞一九八六年十月二十日トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどの発ガン物質があるという)。京都市の有名な豆腐屋さんなどは深井戸を掘って対応している。舗装した大地の下は、死の大地、その上につかの間の現代文明が栄えている。
1.4 せせなぎの文化とその消滅

上の字はあまり馴染みのない字だ。小さい辞書には出ていない。特別大きい辞典、たとえば平凡社刊『大辞典』をひくと「せせなぎ、またはせせなげは、せせらぎに同じ。みぞ、どぶ」とある。せせらぎは、現代語では清流を連想するが、古い時代の書物、たとえば文安三年(一四四六年)の桑門行誉著『*・・・・*』(あいのうしよう)』には、「常に不浄の水なんとの流れやらぬところを、せせらぎといふ」とある。江戸初期の書『甲陽軍鑑』には「せせなぎの傍に立ち寄り、小便の用をたし」とあり、江戸時代の『浮世床』には、おちぶれた貴人のなげきを「今の身は、せせなげに流れる米粒を拾っていれど」と記している。
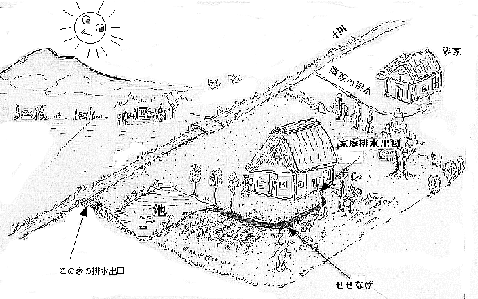
下水道が今日のように普及していなかった頃、民家の裏口から畑にそって、土を掘り割っただけの下水溝があった。お勝手場からの炊事汚水は、この溝をゆっくり流れ、近くの小川か池にそそいでいた。これをせせなぎとよんだ。せせなぎという語を記億している人は、最近めっきり少なくなった。若者たちに説明するのは難しい。環境の変化が言葉の変化に直結している。方言では、ショショナゲ(宮城)、セアナゲ(奈良)、ゼーナ(丹後)、シシナゲ(新潟)などいろいろで、今のうちに採集しておかなければ、まもなく日本語から完全に消滅する運命にある。さいきん検索サイトで「せせなぎ」が出たのはうれしかった。しかし字はもちろん古語の書物の話も出ていない。
諺に「水三尺流れれば清し」という。もっと古い書物には「水は三寸ながれれば、水神様が清める」ともある。
この諺を具体的に見せてくれたのが、このせせなぎだった。汚水流入点から数メートル先で溝の幅を広げ、水をよどませる。ここは悪臭ただようもっとも不潔な場所だから、植物を繁らせて覆い隠した。夏には、無花果(いちじく)、酸漿(ほうずき)、蕗(ふき)などが繁茂し、柿の木もすくすく育ち、木登りなどたのしい子供の遊び場にもなった。現在40代になる私の娘もその記憶をもっている。きたないところをうまく利用した、すばらしい工夫であった。法事などで排水量が一時的に増しても、この湿地帯が緩衝作用をもち、汚水が下流に押し流されることはなかった。せせなぎは巧妙な戸別汚水処理施設であった。
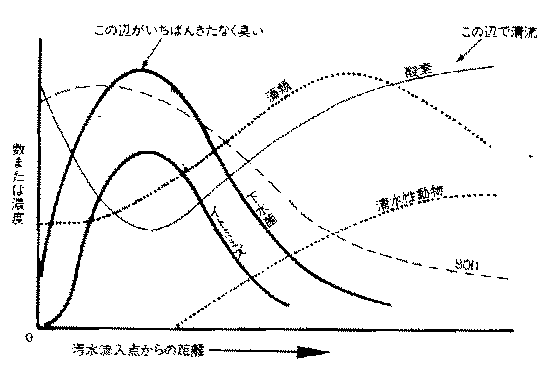
流れに沿っての水の変化を概念的に示したのが上図である。下水菌がピークに達するところでバクテリアが活発に活躍し、汚水中の有機物を分解する。多量の酸素を消費して、酸素が欠乏するので、酸素のないところで活躍する嫌気性菌が主力である。土の中の鉄分は二価の鉄に還元されて青味をおび、ときにはメタンガスを発生する。
このバクテリアこそ、昔の人たちが言った水神様だ。ここには生態学でいう食物連鎖、つまり互いに食いつ食われつの関係が成立した、微生物の王国が展開している。
ところが、この不浄な場所から数メートル下流では、溝の中の様子は一変する。イトミミズはいなくなり、青い藻類が繁茂し、水は次第に澄んでくる。下流に下るにつれて水は澄み、池や小川に流れ込む頃には、清水に近い。せせなぎの周囲の土壌は、バクテリアの分解生成物を吸収して畑の作物に養分を供給する。下流の池に鯉や鮒(ふな)を飼えば、すくすく育つ。これを自然の自浄作用という。まこととに合理的な、自然の完全な循環システムである。大地の活発な自浄作用を学ぶ最高の教材であったが、今では子供たちに見せることもできない。
都市の成長にともない、都市部からせせなぎが消滅していった。土地に余裕がなくなったことや、生活水準の向上により、排水の量も質も変わったことなどが、原因である。土地に余裕がある田舎でも、せせなぎはコンクリートやビニール製下水管に代わった。このほうが衛生的という単純な20世紀的発想であった。
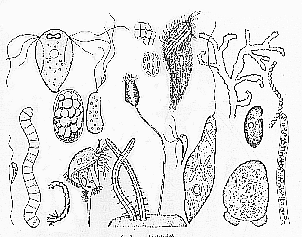 水神様の正体はこれだ
水神様の正体はこれだ
水神様は住み場所を失い、炊事場の水は直ちに小川に排出されるようになった。洗濯汚水には洗剤が多量に含まれ、微生物を棲めなくした。かってはメダカや小鮒が泳ぎ、ときにはウナギも釣れた小川は一変して死のドブ川となった。すべての河川の風物詩を完全に崩壊させてしまった。それは海へと及んでいる。ただ単に物質的環境汚染にとどまらず、こどもたちの遊び場であり、博物学研究室でもあった施設を奪ったのである。せせなぎという言葉が忘れ去られたのは、実に象徴的な文化史的事件であった。
せせなぎに代って工業的装置で、集中的、効率的に実施しているのが、下水処理場である。活性汚泥法と呼ばれる方法の原理は、せせなぎそのものだ。かつては家ごとにやっていたことを、都市単位でやっている。つまり、隣の家との関係だったことが、都市単位に巨大化した。滋賀県から大阪までの淀川水系はその見本である。しかし、そこに決定的な違いがある。汚泥の大部分は焼却処分し、灰は埋め立てられる。その灰には現代の生活廃棄物から来るもろもろの毒物が入っているから、肥料には危険である。それをこともあろうに山地に棄てるから、長い年月には地下水を汚染し、人間にふりかかる。現代人の悪しき遺産である。最近、戸別生ゴミ処理機が使われはじめたのは一つの反省のあらわれである。
1.5 奈良の大仏様で発想の転換
話はまったく違う話に変わるが、上記のような発想も教科書の延長線上では出てこない。砂も粉である。すると奈良の大仏さんの前で砂の山を 想像することができる。
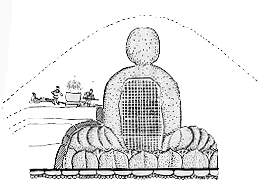
上図で大仏様の後方の山は三笠山ではなく砂山だ。大仏様は金銅仏だが、鋳造されたというから、莫大な鋳物砂が要った筈だ。その砂はどこの砂か、そしてその砂は後は不要だったから、どこかに捨てられた筈だ。しかし古文書を見ても、献上された金が何貫目とあっても砂はどこから運んだかは書いてない。それは現在でも同じで、マイカー1台造るのに鋳物砂はその重さの2倍は消費するというが誰も見たことがない。現在では鋳物砂は大部分外国産だ。昔はベトナムから来たが今はオーストラリアから運ばれている。その現地を訪問したら、日本の企業が独占していて、巨大なタンカーに美しい海岸の砂が運ばれて日本へ行く姿を目撃することになった。その砂は日本に来て、鋳物砂になったり、ガラス工場へ行ったりしている。
奈良の大仏は盧遮那仏(るしゃなぶつ)。平凡社の百科事典をひいて見ると,「サンスクリット語で光明遍照などと訳され、煩悩の体が浄く、衆徳備わり、一切処にあまねきこと、あたか日光のごとく照さぬ
ところがないとの義」と書いてあった。現代人がこの大仏の足下に立って仰ぐ像は千二百数十年前とほとんど変わるところないが, 受ける感動は、およそ異質のものである。いまでは、国の総力を挙げてこの像をつくった想像を絶する権力もないが、作りあげた人達の苦労話も伝えられていない。それに現代の巨大建造物を見慣れた感覚で見るから、クレーンでいとも軽々と吊りあげるさまを想像する。
奈良時代を再現し、奈良時代の感覚で大仏を仰ぐことっは出来ないものかと考えてみた。食物史を調べて、大仏造営の工事に参加した人々の食糧について知りたいと思つたが、どうもよくわからない。麦のにぎりめしに味噌ぐらいの粗食であったに違いない。
だがこれを「粗食」と評価するのも現代的感覚である。現代人のために「粗食」を「自然食」と言いかえてみるのも面 白い。
鍍金の時発生する水銀による中毒については記録があるが、鋳物砂については書いてない。大仏鋳造について技術的検討を加えた『奈良と鎌倉の大仏』(荒木宏著,有隣堂昭和34年や、『鋳造』(石野享著、産業技術センター、昭和52刊)から、工事の推移をたどることもできる。それによると、まず木材を組み立てて骨組をつくり、その外側に壁を塗るようにして、鋳物砂と粘土の混合物で大仏の原型をつくった。
この原型に雲母粉のような離型材を振りかけておき、その上に、外型用の粘土砂を塗りつける。原型に接する肌砂は細かい砂、その上にやや粗い砂、さらにその上にもっと粗い砂というように、篩(ふるい)で粒を揃えた鋳物砂を用いて繰り返し塗り固め、外型の厚みを50センチぐらいにした。この外型は一個が畳一枚ぐらいに分割し、これを自然乾燥してから、薪や木炭の火で焼成した。
一方、外型を取り外して露出した大仏の原型は表面を一様に削り落してから、外型をもとの位 置にもどせば、削り取った分だけの隙間ができる。ここへ少しずつ鋳込んでゆく。全高を八段に分割し、下方から順次鋳込み、一段鋳込むごとに、まわりに土手を築いて、そこに手鞴(ふいご)の溶解炉をおいて作業した。最後には大仏の周辺に高さ約17メートルの小山.が築かれた。
三年の歳月を費して本体を鋳造したが、これではまだ無恰好な鋳放しの大仏である。表面 を砥石で磨き、塗金を施さねばならぬ。水銀に金を融かしたアマルガムを塗るのに5年の歳月をかけた。このときにはアマルガムを加熱ずるので、大仏り周辺には有毒な水銀ガスが充満するという、聞くも恐ろしい光景が展開したわけだ。
全国から駆り出された人々が帰り途で死にたえる光景もあったに違いない。
大仏周辺の工事のほかに、諸国の鉱山をはじめとして、材料調達のための大規模な事業が行われた。「國銅を尽して象(像)を鎔し、大山を削って堂を構え」と天平15年に発せられた聖武天皇の詔(みことのり)は、国土の荒廃と引換えに行われた大工事を素直に表現している.
当時の燃料は木炭であった。『木炭の文化史』(樋口清之著、東出版、昭和37)には大仏鋳造に使われた木炭だけでも16656石、これは史上最大の木炭消費であったと書かれている。大仏と大仏殿は度々の戦火で焼失するたびに再建され、そのつど、森林の大量
伐採が繰りかえされたから、たとえば中国地方の森林の現在に残る荒廃を生んだ(富山和子著、ポと緑と土L中公新書、昭和49)。鳥取砂丘はその頃できたのである。「日本列島の砂漠化」)は、すでに古代より着実に進み、とどめの一撃が加えられようとしているのが現代だ。
今も昔も、鋳物砂は、白砂青松の砂浜や、美しい山を削って採取され、華々しい文化の舞台裏で、人目に触れず、焼けただれて捨て去られる悲しい運命を担った砂(粉体)である。現代社会は、1トンの鋳物をつくるのに3-5トンの鋳物砂を産業廃棄物にしている。ガラス製造原料用の砂も含めると、わが国では一人当り年間数10キロの美しい砂を消費する勘定になる。奈良の大仏は、文明と国土とそして日本人の煩悩について考える巨大な記念物だといえる。
私は昭和電工勤務中に、近所にあった鋳物砂製造工場の技術指導に出かけて、その粒子の大きさを揃える技術に関わったときに上記の幻想が出てきた。粒を揃えることだけでも大変だったに違いない。現代人の想像を絶する努力と技である。鋳物砂は主成分が石英であり、これが第9章の鳴き砂に関係していることも付記しておく。
[挿話] 秘密の小箱-石英との出会い
子供の頃、父の机のひきだしに古銭や勲章を入れた小箱があった。父が留守のときにそっと覗くと、いつもきれいな水晶が光っていた。もう一つ青みがかった石があった。青い石は火打ち石だと教えられたが、その青色にはえもいわれぬ魅力があった。私は人生を通じてこの2つの石をを追って来たようだ。粉体工学といって、物質を粉にして扱う工場の建設にかかわる仕事をしてきたが、そこでは粉砕機械で物を粉にすることが基本だった。その機械の歴史を追って、石臼にたどりついた。工業化社会のなかで失われていった中世の道具である。
だが現代の鋼鉄の機械には出来ない秘密が石臼にはあることが分かってきた。日本古来の微妙な蕎麦や豆腐そして抹茶の味や香りなどは鋼鉄では出せない。この秘密こそ石の中に閉じ込められている水晶の微結晶による切断がなせる技であった。脱工業化社会を目指して石臼を復活させたい日が来る筈だ。それまで石臼の秘密も小箱に入れて置こう。
水晶は二酸化ケイ素の結晶で、コンピュータ部品に欠かせないシリコン原料であるが、シリコンの語源は火打石である。約5千年まえの遺跡から火打石と黄鉄鉱(鉄がない時代なので)のセットが発見されて文明への道を拓いた人類の火の発見だったことが確かめられている。その後、鉄の文明になって黄鉄鉱は火打金にかわった。火打石と火打金、それに火口(植物の繊維を炭化したもの)の三点セットが貴人の所持品であったことが、古墳からの出土によって確かめられ、武士の太刀に必ず火打袋がつけられた。これは秘密の小箱ならざる小袋である。
小さい水晶の集まりである鳴き砂は私の現在の研究の中心であった。かつて日本列島も世界中どこにでもあまねく存在したものだが、最近50年間に海洋汚染で失われていった。エジプトのクフ王のピラミッドにある未探検の秘密の部屋から、鳴き砂が発見されたことが当時話題になったことがある。今の現地では想像もつかない5000年前のエジプトの自然を見せてくれる記念物だ。このほんのひとつまみの砂をカプセルに入れて秘密の小箱に
入れて京都府網野町にできたき琴引浜鳴き砂文化館に保管されている。私の人生の原点として。
最後に粉の1キロあたりの値段の表を対数目盛りで下に示す。同じ目方でも随分な違いだ。これを造リ出す苦労はほとんど変わらないのに何だか変だと思いませんか。
図1-5 農