リンク:第1章粉とは|第2章人類史一万年|第3章火薬製造工場|第4章石臼伝来|第5章粉の文化|第6章食文化|第7章ダイナミックス|第10章ナノ微粒子|
第八章 二十世紀を演出した粉
8.1 粉体工学はなぜ急成長したか
1970年代のいわゆる技術革新あるいは産業の高度成長期に忽然として現われ,急成長した新しい工学分野の一つが「粉体工学」であった。それは大変地味な工学であったから,一般の人たちには知られなかったが,関連の深い分野の専門家達からは,驚きの目をもってみられた。
ほぼ同じ時期に,アメリカとドイツで"Powder Technology"とよぶ学問が出現した。一般の人々の目にふれなかったのは,以下にのべるように,生産システム設計のバックグラウンドをなすもので,とりわけ,専門的設計者の間で注目される工学であった。物質的には最終製品ではなく,大部分が製造工程の中間に現われるものが多く,一般消費者の目に直接触れる粉は殆どなかった。
ではこの時期の具体的にどんなテーマに深く関連していたのかを,以下数項目にまとめてみよう。
1) 材料革命:20世紀末にはプラスチックスや各種複合材料を中心とする新しい材料が次々に現われたが,その製造プロセスでは至るところで粒子状物質が原料,中間製品として扱われた。それらの粒子状物質(粉体)をつくり出したり,その性質をコントロールする技術開発が,きわめて重要視された。発泡ポリスチロールの包装材は粉体ではない。だがその製造プロセスでモノマーを重合させたとき,小球状の粒子ができる。ここで液相中に分散した粒子系が現われ,粉体工学の対象となる。スクリーンニングと遠心分離による脱液,乾燥,分級という粉体処理プロセスを経てから,含浸一発泡一成型の工程を経て,かの包装材になる。発泡により粒子径は50倍になるから、その分級プロセスはきわめてシャープな分級を要求した。10ミクロンのエラーは0、5mの差となって現れるからだ。 不均一粒径は成型体の機械的強度に致命的な影響をもつが,ここでは分級機の性能はいうまでもなく,その輸送,貯蔵などのプロセスでも,粉体静電気除去など高度の技術を必要とする。筆者はそのプロセス設計に参画して,こんなところにも粉体工業があったことを知り驚いたものであった。
新建材の名でよばれるボード類や,床材は粉体ではない。だが原料は材木の粉砕物やプラスチック粉末,あるいは体質材料としての炭酸カルシウム粉末,着色顔料など,すべて粉体であり,その粒子系のコントロールは製品品質を左右した。現代人は粉体成型体の中に住んでいる。自動車のタイヤはカーボンなど数種類の微粉末をゴムで固めたものである。カーボンの生成工程,発じんしやすいカーボンの発じ'ん防止のための造粒,原料粉体材料の捏和混練などの中間工程で各種粉体処理技術の出番があった。
ポリエチレン,塩化ビニールなどが消費者の目にふれるのは成型体であり,着色済みの製品だが,中間製品は,球状粒子だったり,フレーク状だったりする。この粉体の状態で成形工場へ送られ,顔料や他の材料などこれも粉体と混合してから成形されたものだ。
8.2 大量集中生産
:高度成長時代のシステム原理の中核をなしたのは,大量集中生産,巨大化,それはしたがって扱う物量の増大を伴なった。その場合,液体と気体については流体力学を設計原理にとしたタンクとパイプラインによって容易に解決されたが,粉粒体状物質の輸送(固体輸送)は数々の面倒な問題をひき起した。流体は密度と粘性係数によって物理的物性を完全に把握することができるが,粉粒体においてはその物性値の把握は簡単ではなく,それに状態によって変る不確定な因子を多数含んでいる。不確定な物性,数値化できない因子を含む設計原理などというものは,現代工学には含まれない。このことが,従来の工学思想の下に育った設計者をテコずらせた。そして新しい設計原理を粉体工学に求めた。
外国から輸入される鉱石,穀物などの原材料は船舶にバラ積みされて港に到着する。これは粉粒体である。多くの場合,空気輸送システムから成るアンローダーが活躍し,巨大な貯槽(サイロ)に受入れる。一見,単なる大きな容器とみられるサイロであるが,日本でも外国でも,サイロの崩壊事故がたびたび起った。サイロ壁にかかる粉体圧が時として予期しない値に達したためである。とくに粉体の動力学は複雑を極めており,未だ解明されない現象も多い。 ニューマチック・コンベアは流体力学を基礎にし,粉体の混入による偏差値を考慮する方法がつかえるため,比較的設計しやすい対象にみえる。粉体の混入率が少ない間は確かにそうであるが,輸送コストおよび付帯設備の観点からは,なるべく粉体混入率を増大したい。この課題は,設計者をより深く粉体に没入させた。
8.3 公害問題: 大量集中生産システムは必然的に各種の公害問題を発生させた。その中心的課題である大気汚染と水質汚染防止技術は,究極的には気体または液体中に分散した微粒子状物質の捕集分離技術に帰する。煙突から出る煤煙,工場から発生する粉じん,などは,大気中に浮遊する微粒子の捕集技術によって解決された。
東京発の新幹線下りで列車で富士山を過ぎたころ,窓外に展開する工場風景で,見えるのはほとんどが大気汚染や水汚染装置だ。できるだけ乾式集じん装置によって除去するのが望ましい。水を使う湿式法は,必然的に水汚染へ移行し,溶解性物質では,より厄介な操作を更に要求するからだ。サイクロン,バグフィルターなどを主力とする乾式集塵装置が発達し,さらに大気汚染監視用の各種機器が開発されたが,これらは粉体技術の輝かしい成果の一つであった。濁った水をきれいにするには,水中に県濁する微粒子を沈降分離,凝集沈降,濾過などの操作によって除去すればよい。水溶性の有毒物質を含む産業廃水は,何らかの方法で沈殿物,つまり固体微粒子に変えて,同上の方法で処理される。
顕微鏡の発達によっ-て粉の正体が究明されると、粉の技術は千分の一ミリ程度まで進んだ。しかし、光学顕微鏡は焦点深度が浅く、粒の一部しか見えなかった。走査電子顕微鏡はこれを補い、粒の表面構造をくっきりと見せてくれた。さらにもっと細かい千分の一ミリ以下の世界も、鮮明にとらえることが可能とたった。同時に元素や化合物の化学成分を知ることも出来る。さらに、電子顕微鏡は新しい世界を拓いた。現代は、機械が巨大化、多様化しただけではな一く、扱う技術も粉自身も精密化、微細化し、粒揃いにし、ものすごく手の込んだ方法で、粉の粒自身をミクロに加工する。かつて考えもつかなかった精妙を極めた粉が造られるようになった。素材の粉を構成する粒子自体を設計し、今までにない、全く新しい機能を持った材料がつくれる。微細構造のコントロール、人類史の積み上げが最近の一世紀あるいは半世紀にもみたない間に凝縮されている。
これを自分の眼で見る幸せを現代人は有している。
しかし21世紀の華やかな技術、ハイテクは、突然に現れたものではない。現代人が特別に優秀なためでもない。今、長い歴史の流れの中で積重ねられた技術の延長線上で、成果が次々に顕れる時代なのである。にわかに珍しい花が咲く人類の栄光の時代、、それをハイテクと流行語で呼んでいるわけだ。工学は現代だけを見据えて進んでいるから、誰も語ってはくれないことを見直すのが本章だ。NHKテレビの「クローズ アップ現代」と「歴史はそのとき動いた」の文化史版である。
8.1 エジソンの電球
「夜のしじまから解放されたい」それは人類の太古からの夢であった。ラソプから電灯への進歩がもたらした人間の心理的解放効果は、はかり知れないものがあった。二十一世紀の技術のべースになった。人間が未来を考えるとき、現在の技術の直線的延長線上なのだ。技術は枝分れしたり、予想もしない他の枝と融合したりして進んでゆく。その例を電球の発明に見ることができる。
電球の開発はフィラメントの製造であった。これには、一世紀を越える研究の積み重ねがあった。電球というとエジソンを思い出すが、実はそのまえにもあとにも、数十年の歴史の積み上げがあった。
最初の電灯(白熱電灯)は、一八二〇年(文政三年)に出現した。しかし、フィラメソトが白金だったので、高価で寿命が短く、実用にはならなかった。十九世紀中期は、厳しい条件で使うフィラメントの材料と製法を求めて、多くの人達が苦労した時代であった。一八七九年、エジソンが竹という自然物で真空炭素電球を造ったが、これはまだ自然物の利用から脱却していなかった。金属でフィラメントを造ればよいことはわかっているが、高融点で溶かして線に引くわけにはゆかない。溶かすのではなく、粉を固めてつくれば、という発想の転換が成功の鍵であった。一八九七年、オーストリアのウエルスバハがオスミウムという金属でフイラメントを造った。-オスミゥムは融点が摂氏二七〇〇度という高温のため、溶かして線に引くことはできない。彼は、粉を固めて線を造ることに成功した。
いまでいう粉末冶金である。その成功の基礎は化学的沈殿法で粉をつくったところにあった。オスミウムの細かい粉を、糖蜜で練って、均質なぺースト、つまりネバネバのものにしてから、これを細い孔から押し出して、細い線状にし、これを乾燥した後、加熱して糖蜜を分解すると、オスミウムと炭素からなるフィラメソトが得られる。つぎにこのフィラメソトに電流を通して炭素を分解した後、熱でオスミウム金属を焼きかためる(焼結)ことにより、目的の白熱電灯用フィラメソトを造った。この発明は、金属粉を固めて金属部品を造る新技術であった。その後さらに多くの人々によって、いろいろの金属(タンタル、バナジウム、タングステン)が試みられた結果、今日のタングステン電球が生まれた。タングステンの融点は摂氏三四〇〇度であった。しかし、タングステソ電球まで到達する道程は、なお容易ならぬものだった。第四章にのべた蘇東披の詩が、ここでもぴったりである。
計を尽し功を極めて磨に至る
信(まこと)なるかな、智者は能く物を創る
亦其の遭遇に伸屈あり
歳久しく講求して、処所を知る
20世紀粉末冶金技術の確立
その成功は、ついに一九○八年になって、アメリカのクーリッジらの一大研究プロジェクトによってもたらされた。その方法を要約すると、タソグステソ粉末を小さな塊状に加圧成型し、水素気流中で加熱、焼結させる。これを高温で叩いて引き伸ばす(鍛造、圧延)。その焼結体は常温では脆いが、高温では鍛造、圧延できるという特性を利用する。加工が進むにつれて次第に温度を下げ、最後には常温でも加工、線引きできるようになる。金属を融解しないで、金属粉を加圧成型後、融点以下の温度で焼結させて金属塊をつくるという、現代粉末冶金技術工業化のスタートであった。粉をつくり、練って、形をつくり、焼きかためるという人類の仕事の基本パターンが、ものすごく複雑化したものである。この方法が確立するや、たちまち高性能超硬合金、含油軸受(注油不要の軸受)、各種金属部品(たとえば時計の歯車)、電気部品などの新技術をつぎつぎに生んでいった。この成功は、もうひとつ大きい意義をもっていた。エジソンの発明は天才の個人プレイであったのにたいし、クーリッジらは、有能な化学者、機械および電気技術者の秩序立った一大研究開発ブロジェクトの成果であったことである。現代研究開発システムのハシリである。この辺で2004年になって特許発明の権利を巡る訴訟問題が浮上したのもこのことと、法律との矛盾の露呈であろ。
科学技術に個人プレイ、英雄の時代は去り、バベルの塔やピラミッド建設を思わせる現代科学の巨大研究開発体制時代の開幕である。後世の歴史家は、科学技術者がもはやエリートではなく、ピラミッドをつくる無数の人々に比せられる時代になったと書くのかも知れない。
必然的に凡人を忠実な科学者にしたてあげる方策が必要になる。猫も杓子も大学へという受験戦争時代の出現である。天までとどく、バベルの塔を思わせる現代科学技術の大規模開発体制。文明という仮想の目標を与えれば、人間はかぎりなく積み上げてゆく特性を本来そなえている。
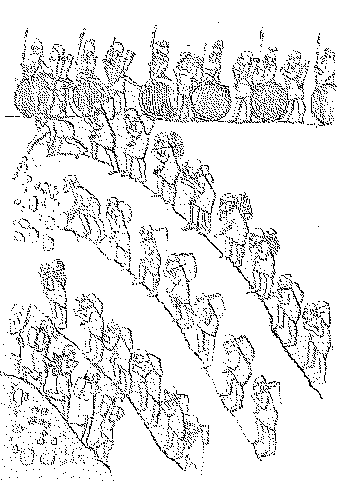
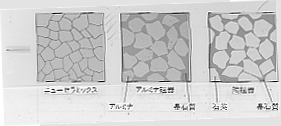
ファインセラミックス
粉末冶金はやがてファインセラミックス時代を生んだ。粉の固め方、ファインセラミックスすなわち焼結および成型技術は、今日のファインセラミックスの基礎である。
城の石組みに私は人間の果しない営みを見るような気がする。おおきい石の間に小さい石が詰め込んである。この延長線上にコソクリートがある。大、中、小の骨材の隙間をセメソトで埋めるのがコソクリートである。粉の充填体を焼き固めてつくるセラミックスも、この精密を極めたものだと思えばよい。普通の瀬戸物は、天然産の粘土を原料にしている。上図はその、ミクロな構造である。石英粒の石垣、つまり石英粒子が骨格となり、その周囲に石英より融点が低い長石質がとりまいて石英粒子を包んでいる。冷却すれば接着して石英粒子を骨格とした固体になる。これがふつうの陶磁器の共通した構造である。つまり陶磁器は石英粒子を長石質で固めたもので、良質粘土は両成分をちょうどよい比率で含んでいた。しかし石英も長石質も非常な高温には弱い。登山家は、そこに山があるから登るように、科学技術は難題への挑戦である。
自動車の点火栓(スパークプラグ絶縁体)の改良がその難題を提出した。エンジンの中でガソリンが爆発的に燃えるときの激しい機械的衝撃、急激な温度変化、燃焼ガスの化学的腐食に耐え、しかも高電圧(三-四万ボルト)にたいして絶縁性がよくなければならない。一八六〇年、フランスで開発された当時は、普通の磁器すなわち、ふつうの焼物であったから、こわれやすかった。そこでこの石英を耐火度の高いアルミナに置き換える研究が進んだ。一九三〇年代にドイツでアルミナ磁器が開発された。我が国でも第二次大戦中に航空機儲用エンジンに応用され、一九五〇年代には一般用に普及した。この頃私もドイッの技術に関連するアルミナ製造に携わっていたことがある。今でこそ言えることだが、見せられたドイツの粉のサンプルを見て、多分ホワイト溶融アルミナのバグフィルター集塵微粉を精製すれば同じ粒度の製品になることを見つけて、客先に出したところ、お客様に大いに気に入られた。そこで私の研究室で極秘裏に製造を命じられた。まさか集塵微粉とはいえず、特殊な製法で作ったことにし、会社は特別高価な値段で売れた。課長いわく「君の何年分もの給料は出たよ。
その当時にはそれが、ニューセラミックス時代への中間過程にあるのだというような自覚は勿論なかった。未来はどこに潜んでいるかわからない。しかし、石英がアルミに変っても、まだ長石質が残っている。これをなくする方向へ進んだところでニューセラミックスが生まれた。原料を、サブミクロン(一ミグロン以下)まで細かくすると、融点以下で固まる、すなわち焼結である。こうしてサブミクロソから超微粉の時代へと突入した。このアルミナセラミックスの技術は猛烈な波及効果を呼び起こし、切削工具、IC基板など現代ニューセラミックス時代が開幕した。
ここでひとつの問題があった。粉を固めるのに、型に入れてプレスすると、内部の圧力分布が不均一になる。この解決にはゴム袋のような容器に粉をいれ、この外側から流体圧をかける。するとパスカルの原理で圧力が周囲から均等にかかる。流体としては溶融状態のガラスや高温高圧気体、あるいは溶融している鉄などをつかうことができる。これは熱間静水圧焼結法(HIP)と呼び、セラミックス製造技術のひとつになっている。
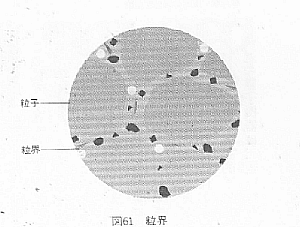
粒界の利用
粉を焼き固めて物を造るさいに、もうひとつ大切なことがある。焼結体を構成する粒子と粒子がくっつき合っている境界のことを"粒界"というが、実は、この粒界は特別な性質を持っている。ここには、隙間や不純物、正確には介在物が集中している。..はじめは厄介ものだったが、やがて逆にこれを利用する技術が発達した。これには微量元素分析法の進歩が寄与した。粒界を自由に造り出すことを「微細構造のコントロール」という。
この粒界の意味がわかるまでの歴史にも曲折があった。一九四〇年代、第二次大戦のさなか、日本、アメリカ、ソ連で、それぞれ独自に、チタソ酸バリウムを主体乏する電子材料(強誘電体材料)が開発されていた。これは、常温で、電気抵抗が大きい絶縁体だった。最近の電子機器は、覗いてみても、まるで毒茸のような部品が一杯だが、そのなかに、バリスターといって、電気機器内部で何か異常電圧がかかったときに、電流を逃がして部品を保護する役割を持つ部品がある。低い電圧では全く電流を流さないが、電圧がある値以上になると、.大きい電流を流せる特性をっている。避雷器、スイッチを切るときの異常電流による火花防止などの働きをもっている。チタン酸バリウム系PTCサーミスターが、もっともはやく出現した。PTCというのは正の抵抗特性を意味し、温度が上昇すると、抵抗値が急激に増加する性質がある。そのために異常温度上昇がなく、安心して家庭用の熱発生器具が使える。日常生活では定温強風発生器(ハニカムセラミックス)が、ふとん乾燥機などに応用されている。この焼結体をつくるさい、粒界の問題が浮上した。ところが一九五〇年代になって、この厄介な粒界を利用しようという考えが現れた。それがチタソ酸バリウム系PTCサーミスターであった。チタン酸バリウム粉末を不活性ガス中で焼いて焼結体を造り、つぎに空気中で再加熱すると、酸素が粒界に拡散し、粒界だけが酸化される。この酸化の程度により、温度特性をコントロールする。焼結をただ固める手段としていた時代から、焼結体の微細構造を造り出し、利用する時代にはいって、焼結技術は他の分野に驚異的インパクトを与えた。
電子技術関係の
. エレクトロ エンジニアリソグ・セラミックスがある。プラスチックス時代には、その蔭にかくれて注目されなかったセラミックスが、にわかに脚光を浴びる時代になった。
プラスチックス時代には、その蔭にかくれて注目されなかったセラミックスが、にわかに脚光を浴びる時代になった。精密化、巨大化、多様化、それが20世紀末を演出していた。現代の粉がひと昔まえの粉と決定的に違う点は、粒子がますます細かくなる傾向にあることと、ひとつひとつの粉の粒におそろしく手の込んだ方法で細工すること(微細加工)、つまり高度の科学技術を縦横に応用して粉を造ることにある。、
テレビの粉
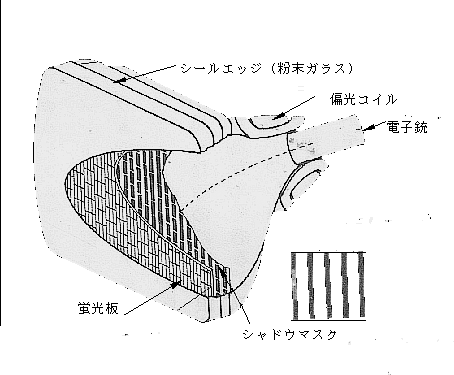
テレビ抜きで二十世紀は考えられない。米ソ首脳がテレビで茶の間に話しかける時代のはじまリだった。このテレビを虫メガネで覗いて見ようとするのは粉屋の執念だ。赤、青、緑がブラックマトリックス(黒い線)を境にして、交互に並んでいる。じつは1980年代に大きな変化があった。それ以前は丸い三色のつぶつぶだったものだ。ここには蛍光体の粉末が塗ってある。まさに20世紀末を演出した光の点の集りであった。
ブラウソ管の内面と外面に導電膜として、黒鉛粉末が塗ってある。この微粉製造はたいへん難しい問題を含んでいた。鉛筆の字が滑らかに書けるのは、黒鉛がツルッル滑るためである。ボール・ミルで粉砕しようとすると、滑ってうまく粉砕できないし、品質変化も起こった。ひとつの解決策は、水素気流中での粉砕だった。.粉砕能力は一躍八倍で粉の性質改善が進んだ。一九七〇年頃から、テレビの画面が鮮明になった。これは、外の光線が蛍光面で反射するのを防ぐため、蛍光面に黒鉛の導電膜と蛍光体を塗った蛍光膜とを交互配列したブラックマトリックスの登場がもたらした改造であった。それ以前は、前面のガラスはグレーだったが、それが透明になり、コントラストがよくなった。
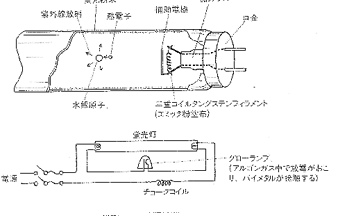
蛍光灯
人類を夜のしじまから解放したタングステソ電球も、今は大部分が蛍光灯になった。封入されている水銀蒸気の分子にフィラメソトからの電子が衝突して、紫外線を出す。この紫外線が、管の内側に塗ってある蛍光粉末(ハロ燐酸カルシウム)を発光させる。タングステンフィラメシトには、電子放射を盛んにするために、バリウム、ストロンチウム、カルシウムなどの酸化物粉末(エミッタ)が塗ってある。古くなると蛍光管が黒くなるのは、水銀などが蛍光粉末の表面,に付着するためである。これを防ぐためにジルコソ酸化物がつかわれている。外のガラスも原料は粉、つまり蛍光灯は粉の塊である。
フェライトという記憶媒体(記憶メディア) MO(磁気光ディスク)が出たと思ったらいつの間にかCD-ROMに変わり、記憶容量も、今ではギガバイトが普通になり、どこまで進むか見当もつかない。本著は20世紀末までの歴史なので、それをまとめておく。
オーディオ、ビデオの磁気テーフからパソコンのフロッピーディスクまで、現代は、日常生活でもさまざまの情報記憶装置を使うが、その記憶を担当しているのは、微小な粉の磁石である。磁気テープには、無数の粉の磁石が、、ひとつひとつ互いに分離されて、バインダーにくるまって、整然と一定方向に並んでいる(下図)。その磁石はガンマフェライトと呼ばれ、粒揃いの針状粒子である。長さは○・五から○.三、ミクロンという、この魔法のような微小な磁石を、どうやってつくるのか。これは、一九四七年に「針状結晶ガンマフェライトの特許が出て以来、二十数年間のおびただしい研究の積み上げによって確立された。今もなお日進月歩が続いている。一粒ぞろいの極微粉、超高純度超微粉の時代の粉、サラサラながれる粉、千分の一ミリ(一ミクロソ)以下の超微粉の製法や開発の情報が新聞をにぎわせている。
電子コピー
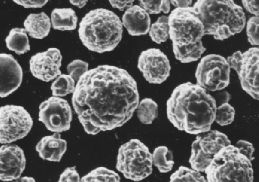 キャリヤー
キャリヤー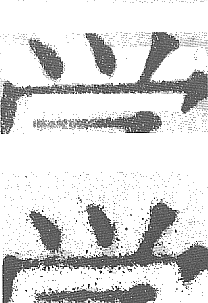 活版印刷とコピーの差は歴然
活版印刷とコピーの差は歴然
上図は宇宙探検のマンガに出てきそうな写真だが、オフィスには欠くことのできない電子コピーの黒い粉を運ぶキャリヤー粒子である。普通のコピーは黒い粉で字を書くが、この粉の運び屋で、人目にふれることなく、機械のなかで循環し、身をすり減らして働き、寿命がくれば捨てられる。文字通り日蔭者の運命を背負った粒子である。多分オフィス勤務のレディーもトナーは見てもこの粒子は見たことがない方が多いはずだ。 左はコピーする原本の文字とそれをコピーした文字を比較してみると、すこしぼやけてくる。これを顕微鏡写真に撮ると、ずいぶんきたない。機械が故障しているのではなく、ごく普通の条件のコピーである。粉がまぶされ、それが焼付けられた状態がよくわかる。電子コピーの原理は、一九三九年にアメリカのチェスターカールソンが発明し、一九四四年にバトル・メモリアル研究所が実用研究を開始、一九五〇年に商品化した。金属セレンを巻いた(蒸着)したローラーに暗い場所で高電圧の静電極を近づけて、ローラーの全面にわたり均一に帯電させておく。次に明るい光で原本を照らし、レンズによってその像をローラー上につくると、文字や絵の部分だけが暗いから、その部分だけに静電気が残り、その他の部分の静電気は消滅する。金属セレンは光が当った部分だけ、電子が動き易くなる性質(光電効果)を持っているのを利用している。こうして静電気の文字(静電潜像)がローラ上に書かれるが、これは目に見えない。ここに色のある粉をまぶして余分の粉を払い落せば、粉なの文字になる。
この粉には実に大変な仕掛けが施してある。各社にノウハウがあって委しいことはわからないが、溶着しやすい合成樹脂粉末(エポキシ樹脂、アクリル樹脂)に、着色材(黒ならカーボン、カラーなら色粉)を加え、さらに静電特性を調節する帯電制御剤、流動性改善剤、離型剤などが配合されている。製造工程では、これらの混合粉末を加熱して溶融し、これを捏和機(ニーダー)でよく練ったのち、水冷したスチール ベルトに流し出す。ベルトで送られる間にカチカチの煎餅状になる。これを粗砕きし、次に特殊な粉砕機にかけて微粉砕する。最後に気流分級機やふるいで、粒の大きさを二〇-五ミクロンに揃えてある。
戻る
「ユピキタス(時空自在)社会」とは、2003年になってマスコミにも登場するようになったが、1990年代にゼロックスのマーク・ワイザーが言いだした言葉で、ラテン語で「どこにでもコンピュータがある」社会が現実になっている。
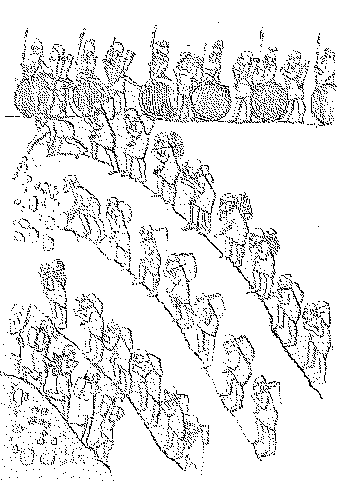
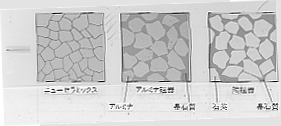
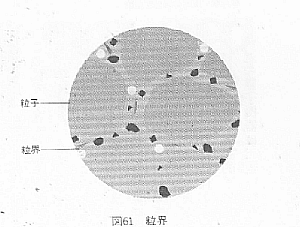
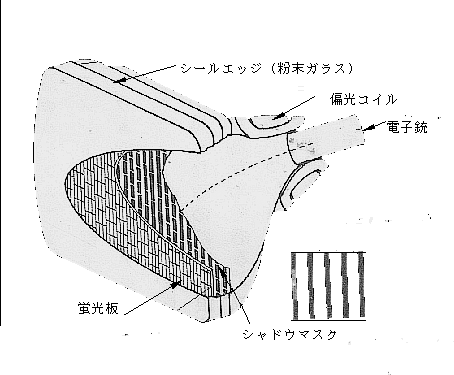
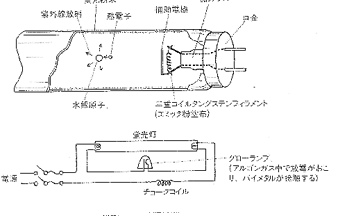
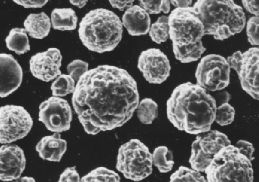 キャリヤー
キャリヤー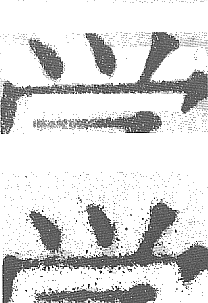 活版印刷とコピーの差は歴然
活版印刷とコピーの差は歴然