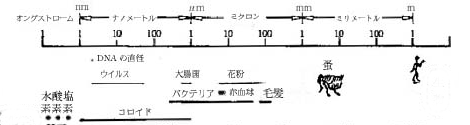
�����N�F��1�͕��Ƃ��b��2�͐l�ގj�ꖜ�N�b��3�͉Ζ��H���b��4�͐ΉP�`���b��5�͕��̕����b��6�͐H�����b��7�̓_�C�i�~�b�N�X�b��8�͓�\���I�����o�b��9�͖���
�w���̂Ɛl�Ԃ̕����j�ꕲ�x�@�@�@
��10�́@21���I�̕��̓i�m�����q
10.1.�@�i�m�e�N�m���W�[�̎���
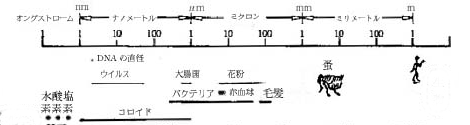
�@�i�m�e�N�m���W�[ �̌��1990�N�ɏo�����A�L���m����悤�ɂȂ����̂́A21���I�����A2000�N1��21���A�N�����g���đ哝�̂̉����i"���ƃi�m�e�N�m���W�[�v��"�j�����������������B10������1���[�g���܂��͕S������1�~�����[�g�����A1�i�m���[�g��(nm)�ƌĂԁB21���I�̓i�m�e�N�m���W�[�i�������H�Z�p�j�̎���ł���B���܂܂Ō��w�I�������Ō����鐢�E����A�ꋓ��3�����������E�ɓ��荞�킯���B����1927�N���܂�ŁA�l���̑啔�����~�N�����̐��E�����̐��E���Ǝv���Ă����l�ނł���B�i�m�̐��E�͕��q���`�q�̐��E������_�l�̐��E�����ƃr�N�r�N���Ȃ���c��̐l�����Ă���B������i�m�̐��E�͎��ɂƂ��Ă͕ʐ��E�ŁA�{���̎�����z���Ă��邪�A����͓ˑR�ɓ������̂ł͂Ȃ��A20���I�ɂ���������Ƃ͋C�t�����ɓ��荞��ł������Ƃ͋L�^���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B���j�I�ɓ��{�����E�����������{�l���g���C�t�������������A�N�����������Ă��Ȃ��B
10.2�@���E���̃i�m �����q�͓��{�ō���Ă���
�@������w�ݐE����20���I�㔼���̓~�N�����̐��E�Ǝv���Ă����B�ސE��A���ɖ{�Ђ�����Y�_�J���V�E�������锒�H�Ƃ̎ЊO������𖽂���ꂽ�B�Ȃ�Ƃ��̉�Ђ͖�����������10�i�m���[�g����̕����H�ƓI�ɐ������͂��߂Ă����B�����̓i�m�̗��q�Ƃ����ӎ��͂Ȃ��A�R���C�h��Ƃ���A�P���Y�_�J���V�E���ƌĂ�Ă����B20���I�����̑吳3�N�i1928�j6���ɂ́u���Ύ��y�����Y�_�J���V�E���̐����@�v���A������26117�����������Ă���B�����ׂ����ƂɌ��݂ł͔N�ԉ����g�����̃i�m�����q���H�ƓI�ɐ��Y���Ă����B���H�Ƃ͂͂��߂���i�m�����q���Ă���Ƃ����ӎ��͂Ȃ������B
�@���{�Ő^����ɓd�q�����������A�����œd�q�������̌������s�Ȃ��A���{�̓d�q�������B�������̂����̉�Ђ������B���̎w���҂����̍H�w�Ŋ��ꂽ�A�r�쐳���搶�������B
�@2002�N����A0.01�~�N�����Ƃ����͕̂ς��ƌ����������Ј��������B�̏d70�L���Ƃ͂������A0.07�g���Ƃ͂���Ȃ����炱�ꂩ���10�i�m�ƌĂԂ��ƂɂȂ����B�悤�₭�킪���ł�2001�N�ɂ͒ʑ��Ȋw�G���ɂ��i�m���[�g�����o�Ă悤�₭�s�������B����ƌ����悤�Ɍ��t�͕s�v�c�ȗ͂������Ă���B���Ȃ����Ƃ����A���̗͎m�̑̏d��200�L�����z�����Ƃ͂������A0.2�g���Ƃ͌���Ȃ��B�В�����u�Ј�����Ȃ�10�i�m���[�g���ƌ���Ȃ��̂ł����v�Ɩ���āu�����������v�������Ƃ����B��������̕����j�̗��j�I�����̂ЂƂł��낤�B
10.2�@�������̉�@
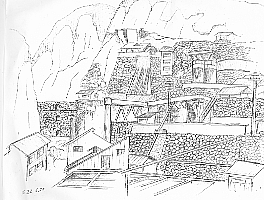 �̓��̔��H�ƍ��m�H��i�������i�m���q�œ��{�̎����x���Ă����j
�̓��̔��H�ƍ��m�H��i�������i�m���q�œ��{�̎����x���Ă����j
�@���H�Ƃ͕����̃o�����[�^�[�Ƃ����鎆�̐����ߒ��Ŏg���Y�_�J���V�E������͐��i�ł��������[�J�[�ł���B���݂͎��p�̕��̈ꕔ���N���C�i�S�y�j�ɕς���ė��Ă���B���ɂ��Ă͏��{�p�r�w���̖{�x�i�����H�ƐV����,2001�j���}�����ŕ�����₷���B�@�@�@
�@���������������{�ɓ`������̂͐��ÓV�c�̎���ɍ���̑m�@�ܒ����������̋Z�p��`�����Ƃ���A���̎��������������B�ܒ��͂��o�̖{�y���邽�߂Ɏ���`�����̂ł���B�������͎E���֒f�̋����̂��߁A������Ȓ`�����Ƃ��Ă��������̓��{�l�ɑ哤�������Ƃ��铤����`����K�v���������̂ł��낤���B���̍��͒���̌��͂̊m���ߒ��ł��������߁A�ܒ��͋�B�E���ɕ{�ɗ��Ă���Ɉڂ����̂����m��Ȃ����A���̂�����͗��j�̈Í��̉_�ɕ����Ă���B
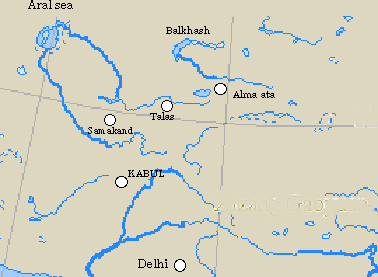 ���̋Z�p�̓`�d���[�g�̈ʒu�W
���̋Z�p�̓`�d���[�g�̈ʒu�W
�@���[���b�p�ł́A���͓��{���y���ɕ��y���x���V���N���[�h�����ɏ��X�ɐ��i���A���ɓ�����@�V�T�P�N�̓�����s����Talas�͂̐킢�̍ۂɁA�����̕ߗ���Samalkand�i���݂̃E�Y�x�N���a�������j�Ŏ�������`���A����Ɍ��̒����A���B�N���ɔ����`�d�����i���ꂽ�Ƃ����B���B�ł͓`����������̎匴���́A�����{�����������A�Y�Ɗv���ȍ~�͖ؖȃ{�����g�p����悤�ɂȂ����B�������ɓ���A���{�ɗm���̐����@���`������Ƃ��́A�����͖ؖȃ{���������B�����́A�C���N�̂ɂ��ݖh�~�܂Ƃ��ă[���`����ɂ�����g�p�����̂ŁA��������͒����������B����͌��݂̎_�����ɔ�����������i���I�ɂ��ǍD�������炵���B���E�ŌÂ̈�����Ƃ��ėL���ȁA�u�S�����ɗ���i�ЂႭ�܂�Ƃ�����Ɂj�v�͘a���̗��j�̏�ŁA�d�v�ȕ�����Y�ł���B770�N�ɁA6�N�̍Ό���������100�������ꂽ�B���܂��܂Ȏ��ō��ꂽ�o���́A�ؐ��̓��ɓ����āA���݂�1�����炢�c���Ă���Ƃ����B
10.3�@����̈��
�@2002�N�ɔ��H�Ɗ�����Ђ̏Љ�ő�萻���H������w�����Ƃ��A�u���͕��ł��ˁv�ƌ�������A�����̍H�꒷�͈�u���b�Ȋ�����ꂽ�B�u����ς�v�Ǝv���āu�����Č����͖؍ނɂ��đ@�ۏ�ɂ��A����������Ă���ɐF�X�̕��������Ċ������������̂�������A���ɂȂ�Ε��ł͂Ȃ����A���̑O�͂��ׂĕ�����ł���B�v�Ƃ����Ɓu�Ȃ�قǂ������������ł��ˁB�����͕�������Đ��ŗ����Ċ������������v�ƁB
�@�Y�_�J���V�E���������̃o�����[�^�[�Ƃ����鎆���x���Ă������Ƃ͈ӊO�ɒm���Ă��Ȃ��B�����ăi�m���̂̂͂����20���I�ɑ�K�͂̍H�Ɛ��Y���������Ă�������������20���I�̈̋ƂƂ��Ė{���ŋL���Ēu���K�v������B
�@�Ȃ�����قǍׂ�������K�v���������̂��B����͗��q���������قǗ��q�ԕt���͂��傫���Ȃ�A�ł��g�D������ꂽ�B���̔����͊�����ł��ĕ��ӂł��Ȃ��P�̊����i�̂悤�Ȃ��̂��ł����B����ł͕s�Ǖi�ł���B���̂Ƃ����̐��̂����Ƃ߂悤�Ƃ��āA���ꂪ�ׂ������q�A�܂�R���C�h�ł��邱�Ƃ��킩�����B���͂��ꂪ�i�m�����q�������B�������d�˂����ʁA�R���C�h��ɂȂ����X�����[�ɃX�e�A�����_�Ό��Ƃ������_�Ό��Ƃ��𐔃p�[�Z���g������Ƃ������������邱�Ƃɐ��������Ƃ����B�茳�ɂ���������ڂ�i�Ό��l���g�����̂ł���B
�@���̂��듯�Ђ̑n�ƎҔ��P��̏���Ƃ��Č�������`���Ă����u�R���Õ��q�͂Ȃ�Ƃ����ē�����悤�ɂ��������̂ƁA���낢��Ȗ�i�����낢��ɏ�����ς��ẮA�ʋl�̋�ʂɓ���A�����Ȏ�A���@�Ŋh�q���Ă͊������āA������d�˂邱�ƖS��ށA���̂��������ڂ̂悩�����̂��V���{���ł������B���ꂩ��A������V���{���̎�ނ��r���A�Ō�ɐF���悭�A�l�i�������A�S���ɂ����ʓI�Ȏ���i����ލ���ĠA�EB�EC�ED���̕����������B���̖����肪CC�ADD�ŁA���Ȃ����̂܂s�̂���Ă���v�i�w���H�Ɓx�_�C�������h�Й�,�j�K���H�����1969�N���������A���̍H��͎��̌̋��ɋ߂��A���]�Ԃōs���鋗������������A���ǂ��̍��̗V�я�̉������ゾ�����B���n�͒����N�����o�Ă���̂Ō��݂͔p���ɂȂ��Ă��āA�e�Ղɂ͗�������ł��Ȃ����A�g�o�����Ŕ��z�R�Ńq�b�g�����̑s��ȃX�P�[�������邱�Ƃ��ł���B
10.4�@�p���v�̐��@�̐i��
�@�����Ŏ������̉�Ɨ������Ă��������ɂ́A�������������j�I������v����B���͐A���@�ۂ𐅂̒��ŕ��U�����A���ԂȂǂŔ����A������h���ĒE�����@�ۂ𗍂ݍ��킹���P�����������̂ł���B���̍��g�݂ɂȂ��Ă���̂͌����͐A���@�ۂȂ̂ŁA�܂��؍ނ��ׂ���������i�K�Ƃ��ă`�b�v�ƌĂ��B��������{���ł����傫�����ł���B�����@���Ə̂��ĕ��ӂ���B�����H��ł͐��Ӌ@���邢�̓��t�@�C�i�|�Ɠǂ�ł��邪���H�Ɨp�ɓ����������Ӌ@�ł���B�@

�@���ӕ��̓��O�j���ȂǂȂǂŌł܂��Ă���B���ꂩ��@�ۂ������Ƃ�o���˂Ȃ�Ȃ��B����ɂ͉��w�I���@�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�܂��Ր��\�[�_�ŗn�������Ƃ��s���Ă����B�������@�ۂ��Z���A�ł������̈�������A�����A�܂�Ƃ����悤�Ȏ��̋������キ�A�p���v�̎������Ⴂ�̂ōs���Ȃ��Ȃ����B1882�N�Ƀh�C�c�Ŗ؍ރ`�b�v���_�������_�J���V�E���n�t�Ŕ�r�I���������ŒZ���ԏ������ăp���v��_�������_�@�i�T���t�@�C�g�@�j�����������B���{�ł�1889�N�ɐÉ����t�쒬�̉��q�����ő��ƊJ�n�B�؉��ɐΊD������ꂱ���ɗ�����R�₵�Ă����������_�K�X�𐁂�����ő������B
�@�����_�@�̃p���v���Ŏg���錴���؍ނ͎����̏��Ȃ��j�t���ނ��K���Ă��邽�߁A���{�ł͖k�C���⊒���i�T�n�����j�Ƀp���v�H�ꂪ���ꂽ�B��������K�͂ȍH��̂��ߍH��p�t��r���ɂ����Q��肪���������B���̔p�t�̏����͓���A�L���ȗ��p���Ȃ��B1958�N�ɂ̓p���v�H��r���ɂ�鐅���������������������B���̂��߂��̕��@�͎��̃N���t�g�@�ɕς�����B
�@ �N���t�g�@�Ƃ����̂�1879�N�Ƀh�C�c�Ŕ������ꂽ�B�؍ރ`�b�v���Ր��\�[�_�Ɨ����\�[�_�ō����E�����ŏ�������B���������ł���̂ŁA�N���t�g�i�h�C�c��ŗ�kraft)�j�@�Ƃ������B���������͊��F�ŕY�����ɂ��������̂ŕ���p�Ɏg��ꂽ���A�Y���܂̐i���ɂ��A�������������悤�ɂȂ����B
�@���̕��@�͌����؍ނ̎�ނ�I�Ȃ����߁A�j�t�L�t�̂�������g����B����ɔp�t��Z�k���ĔR���Ƃ��ĉ�����A�R�Č�̊D�͐ΊD�ʼnՐ��� �Ր��\�[�_�Ɨ����\�[�_�ɂȂ�A�z�g�p�ł���B���_�͈��L���o�����A���L����s���āA���Ȃ��Ȃ��Ă���B
10.5.�@�Y���@�Ƃ̓U���i�Ă��傤�j�̐i��
�@��N���i�a���ł͌����̞��i�������j�Ȃǂ̑@�ۂ̕Y���ɐ�̗���ɐZ���Đ����̎_�f�ŕY��������A�~�͐�̏�ɕ��ׂē����ɂ��Ď��O���ŕY�������B���f�Y���͗L�@���f���������r���ɏo��̂Ŏg���Ȃ��B�_�f�Y����I�]���Y�����s����B
�@������邽�߂ɂ͎��̕s�����x�����߂�K�v������B���̂��߂ɍz�����̔��F����������B�ΊD�ӂ��đ���d���Y�_�J���V�E���͎����@�̃��C���[�Ղ�����B�����ł����Ƃ��L�����p����Ă���̂́A�ΊD���ɒY�_�K�X�𐁂�����ő���y���Y�_�J���V�E���ł���B�J�I�����A�N���[�������ړI�Ŏg����B
�m���n���Q�����̂͂���F1956�N�A�����̍]�ː�ׂ�ɂ���{�B�����������p�t�𗬏o���A��≺���̉Y���̊C���������A�L����ʂɎ������B�����͉�Ђɗ������Čx�����ƌ��˔��l���ߕ߁B�������c�����Z�l����v�c�����Đ킢�Y���̐l�X���������B�����A13�N��ɋ����͖����Ȃǂ̂��ߋ��ƌ���S�ʕ��������Bhttp://home.att.ne.jp/iota/lupin/meiji.htm
�@�p���v�́A���̖�8�������Y�p���v�ł���Ƃ���Ă���B�������A����͓��{�����Ńp���v�ɉ��H���ꂽ���̂��w���Ă���̂ŁA���̌����ł���؍ރ`�b�v�̖�7���͗A������Ă���B�p���v�Ƃ��ėA���������̂ƍ��킹�A�p���v�̌����̖�4����3���C�O�̌����ł���A���{�̖؍ރ`�b�v�̗A���́A�����̌X���ɂ���B2000�N�ɂ́A1,442���g���Ɖߋ��ō��ƂȂ����B�������ɐ�߂�A���؍ރ`�b�v�̊������A�N�X�����Ȃ��Ă���B2000�N�́A�O�N�Ɣ�ׂăI�[�X�g�����A�A��A�t���J�A��������̗A���ʂ�������������A�A�����J����̗A���ʂ����������B���̂悤�ɐ����H�Ƃ̔��B�j�͂܂��ɕ����j�ł���B
10.6�@�i�m�e�N�m���W�[�̊댯��
�@WWW�����ŃL�[���[�h�u�i�m�e�N�m���W�[�@�댯���v�ŏo�Ă�����O�̐��Ƃ��_���Ă�����͓��X�ω����Ă���B�܂��ڗ����������͋N�����Ă��Ȃ����A������N����\�����\������B���i�m�����q�͎��R�E�ɂ͑��݂����A����͐l�Ԃ��������o�����̂ł���Ƃ������Ƃ��B����̎��R�E�ɂ͑��݂��Ȃ�����A���͂⎩�R�͐l�Ԃ����Ă���Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�u�_�l�͏���ɂ����v�Ǝ�������B�u�ł��댯�Ȃ��Ƃ́A�����̎��̂∫�p���l�⏬���ȃO���[�v�̎�̓͂��͈͂ōs�����ł���Ƃ������Ƃł���B�����͑傫�Ȑݔ���Ȍ��ޗ���K�v�Ƃ��Ȃ��B�m������������悢�B���ہA��X��GNR�Z�p�i��`�q�H�w�j�Ɋւ���m�����g�U���邱�Ƃɂ��{���I�Ȋ댯���|�m�������ő�ʔj����\�Ƃ���댯���|�ɂ��Ă̖����Ȍx���N�Ă���B�v�i�m�����͔��ɏ������̂łقƂ�ǑS�Ẵt�B���^�[��ʉ߂��Ă��܂��A�ڂɌ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���{�Ŕ������ꂽ�J�[�{���i�m�`���[�u�ihttp://www1.accsnet.ne.jp/~kentaro/yuuki/nanotube/nanotube.html�j�|�S�̐��\�{�̋����������A������Ȃ��Ă��܂�Ȃ��قǂ��Ȃ₩�ŁA��i�⍂�M�ɂ��ς��A������d�C���A�_�C�������h�����M���悭�`����B�R���s���[�^������萔�S�{�����\�ɂ��A�G�l���M�[������������\���܂Ŕ�߂Ă���Ƃ����B���R�E�ɂ͑��݂��Ȃ����̂�������ꍇ�B�����A��肪�����ăi�m������ʏ�̊����珜�����悤�Ƃ��Ă��A����͂��łɎ�x��ɂȂ�B�������̊O�ɏo���i�m���������o����Z���T�[�͑��݂��Ȃ��B�i�m�e�N�m���W�[�̋����ׂ��\���ɔ�߂�ꂽ�댯���ɂ͏\�����ӂ���K�v�����邱�Ƃ��B
�@�������A�����܂ʼnȊw�W�����Ă����l�ނɂ́A���͂�����Ԃ����͂Ȃ��B�Ȋw�Ƃ�������������Ɍ����g���Ă����̂��B�l�ނ̖����͂����ɂ������Ă���B��������̌��𑀂��悤�ɂȂ�͂��߂����܁A���̂��Ƃ͂܂��܂��^���ɂȂ��Ă������낤�B
�߂�
�@