 享保年間の鳥居清忠:浮世絵の戯画「道外ずくし」(模写)
享保年間の鳥居清忠:浮世絵の戯画「道外ずくし」(模写)リンク:第1章粉とは|第2章人類史一万年|第3章火薬製造工場|第4章石臼伝来|第6章食文化|第7章ダイナミックス|第8章二十世紀を演出|第9章鳴き砂|第10章ナノ微粒子|
 享保年間の鳥居清忠:浮世絵の戯画「道外ずくし」(模写)
享保年間の鳥居清忠:浮世絵の戯画「道外ずくし」(模写)
第5章 開花した日本の粉の文化
5.1 ステータスシンボルだった茶の湯
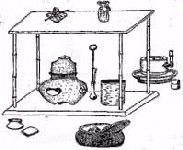 最近の茶書には茶磨が欠けている
最近の茶書には茶磨が欠けている
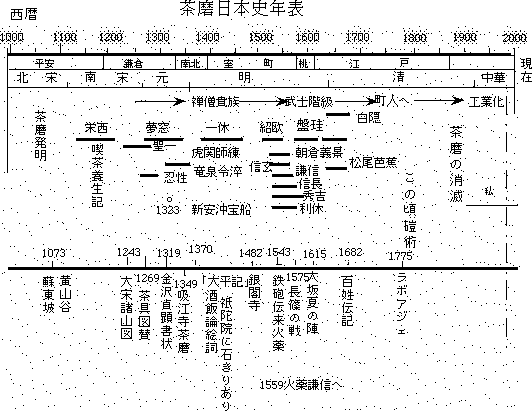
前章でのべた茶磨の歴史を年表にまとめたのが上図である。日本に伝来してからおよそ三百年間、茶の湯は、僧侶や貴族など専ら超上流階級の間で行われてきたが、戦国時代になると急速に全国の武士と高級商人の間に普及した。オランダの旅行家リンス ホーテンの『東方案内記』(一五九六年)には、外国人の目にうつった当時の様子が記されている。
「チャーと称する薬草の、ある種の粉で調味した熱湯、これはひじように尊ぱれ、財力があり、地位のある者はみな、この水を、ある秘密の場所にしまっておいて、主人みずからこれを調製し、友人や客人を、おおいに手厚くもてなそうとするときは、まずこの熱湯を喫することをすすめるほど珍重されている。かれらはまた、その熱湯を煮たてたり、その薬草を貯えるのに用いるポットを、それを飲むための土製の碗とともに、われわれが、ダイヤモンドやルビーなどの宝石(を尊ぶように、たいそう珍重する。」
茶の湯に限らず、貴族の文化をわがものにすることは、地位の高さを誇らしげに示す手段すなわち、ステータスシンボルであった。信長や秀吉の茶の湯好みはよく知られているが、これをまねて、われもわれもと、名器集めが行われた。リンスホーテンの記事はその事情を伝えていて興味ぶかい。一昔前の話だが、猫も杓子もゴルフ時代があったのとどこか似ている。
ところで茶の湯には抹茶は絶対欠かせない。現在のように工業製品化された茶道用抹茶などなかったから、抹茶をつくる茶磨(茶臼)がどうしても必要だった。しかし茶磨の名器を手にすることができるのは、特別な地位にある人物に限られていた。そこで石屋につくらせ、模倣に模倣を重ねていった。私が調査した限りでは天竜川以東の東国へゆくにつれ形態が粗野になり、目の刻みまで変ってゆく傾向が見られた。富士山麓では作りかけて断念したものが発見されたこともある。
茶の湯が日本の石臼技術の先達になるという、西洋や中国とは全く違う日本独自の石臼の発展過程をたどった。信長の茶磨は本能寺で信長の茶の湯道具類とともに失われたという。しかし秀吉、武田、朝倉などの大将級の武士たちの遺物は発見されていてさすが名器と感心させられる。小堀遠州の茶磨が、東京の茶の湯道具展で展示されたことがある。また毛利の配下には中国直輸入らしい名器も多く、現在でも茶が盛んなことは、その名残りであろう。
5.2 碾茶と茶磨
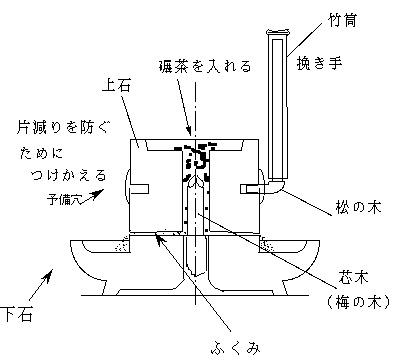 茶磨の構造
茶磨の構造
ここで予備知識として、茶磨の解説をしておく。抹茶の原料葉は、碾茶(てんちゃ)といって普通のお茶の葉とは違う。最近では茶の湯の師匠さんでも碾茶は初めて見たという方もあるようだ。覆いをかぶせて日陰でそだてたお茶の葉を蒸して、操んで乾燥したものが玉露である。覆いをさらに厚くして、柔らかく育てた特別上等のお茶の葉を、蒸してから揉まずに直ちに乾燥し、粗砕きして茎の部分を除去し、葉肉の部分だけを集めたものが碾茶である。この碾茶を上石の中央部の供給口に入れる。上臼を貫通した供給口は、芯木(木製の心棒)の直径よりも少し大きい。そのため上石を回転させると、単純な円運動ではなく、上石の摺動をともなう複雑な動きになる。これが上下石の狭い隙間を、微粉末がスムーズに周辺へ送り出す駆動力となる。粉が細かいから偏心による送り機構が不可欠になる。この一見アバウトなメカニズムが一般の機械ではできない茶磨や石臼一般の秘密である。これが茶磨の機械化を阻んでいる。
供給口から入った原料碾茶は心木と供給口との隙間で粗砕きされてから、上下石の隙間に入り込む。上石と下石は周縁部分(数ミリ程度)のみで接触し、中央に向かって次第に隙間が広くなっている。この上下石の隙間のことを「ふくみ」という。ふくみは最大○・五ミリ程度である。このふくみの調整と周縁部分の摺りあわせ具合が、茶磨の性能を決定的に左右する。この調整は微妙で、特別の熟練を要し、茶臼師と称する専門職人の仕事であった。「石臼芸より茶臼芸」という諺がある。「普通の粉挽き臼は、なんでも粉に挽く、つまり粉す(こなす)が、茶磨は茶しか挽かない。しかし、粉はすばらしい」の意をこめている。そこで、どんな芸でもこなすが、荒っぼいのを石臼芸、一芸に秀でることを、茶臼芸といった。
石材の種類も普通の粉挽き臼とは全く違う。輝緑岩や、きめの細かいの砂岩が使われた。摺りあわせ面が、適度の粗さになることが必要なためである。
古文書に「宇治は寔に御国の建渓北苑なり。且又其山骨を抜きては碾磑を造り出す。此石他山に出さず」とあるように、宇治には茶磨に適した輝緑岩の岩脈が現在でも山を貫いて走っていて、観光地の天ケ瀬ダムのすぐ上流で露頭を見ることができる。研磨面は実に美しい。宇治川は、昔、洪水で荒れ、大きい輝緑岩が転石になっていた。現在は、天ヶ瀬ダムができて、茶磨を作れるような大きい転石はない。小さな石ころなら宇治川でも発見できるが河川改修でそれも難しくなった。

現在は宇治から宇治川に沿って天ケ瀬ダムを過ぎた右側で崖になって露頭が見える。その上側に茶臼谷がある。そのあたりで合流する支流の志津川でも同じ輝緑岩の小石を見つけたことがある。
抹茶は数ミクロン(一ミクロンは千分の一ミリ)の微粉末である。これほど細かい粉末を造り出した茶磨の技術は、粉づくり道具中の最高の傑作であった。
5.3 茶を挽く
 茶坊主が縁側で茶磨を挽いている(原図あり)
茶坊主が縁側で茶磨を挽いている(原図あり)
そのむかし、茶挽きは客人を迎える隣の間で行われ、お寺では和尚の留守に小僧が挽いた。「茶を挽く」という言葉があるが、現代語では「窓際族」のことで、京都では今も通じる。お呼ぴがかからない女郎が、茶を挽かされたことからきている。粉を造る仕事が舞台裏の仕事だった、まさに典型的な例である。回転速度は速過ぎても、遅そ過ぎてもいけない。石の摩擦面での局部的発熱現象がおこり、抹茶が変質して特有の香りと味をそこなう。茶磨を長い時間動かしていると、次第に上下の臼の接触面あたりから暖まってくることがわかる。その温度は人肌の温度のときに出る粉が最高とされている。だから挽きはじめた時分の粉はお客さんには出さないようにする。早く挽こうとして速すぎる挽き方をすれば、苦味が出る。このように抹茶は鋭敏に挽き方を反映するので、茶臼は石臼を理解するために最高の教師となる。これは米や蕎麦では学べないことだ。
私は、茶磨の秘密を知る必要上、原石から作ってみた。一応まともな抹茶が挽けるまでに、試作に試作を重ね、二十二個めの作品が現在手許にある。石は花崗岩の中から硬すぎもせず、柔らか過ぎもしない石を選んだ。四国の庵治石か外国産の花崗岩で作った茶磨をしばしばデパートなどで見かけるが、装飾品ではあっても使い物にはならない。
茶磨について理解を深めるためには、自分で作ってみる必要があった。中国の本に
「知者創物、巧者述之 世謂之工」(本物の知者は自分で物を創りだす。小利口な奴は屁理屈をいう)(『周礼考工記』)と。
現代情報化社会は巧者と、さらにその情報ブローカーがやたら多いようだ。
ところで、コーヒーミルのような、手頃な手挽きの茶磨があったらとは誰でも思うが、コーヒーは、抹茶に較べると著しく粗い。粉砕に必要なエネルギーはリッチンガーの粉砕法則によれぱ、粒の大きさに反比例する。大雑把な計算だが、仮にコーヒーの粒の大きさを約○・五ミリ、抹茶を千分の五ミリとみて約百倍のエネルギーが要ることになる。これでは安価なティーミルは作れそうもない。
5,4 茶臼山
戦国の武将たちにとって、茶磨が特別な意味をもっていたことは茶磨山(茶臼山)とよばれる山が全国に二〇〇近くもあって、その大部分が当時の城跡や戦陣跡であったことからもうかがえる。上杉謙信と武田信玄の十二年間にわたる川中島周辺の争奪戦で、信玄は茶臼山に布陣した。現在のJR篠ノ井駅北西に見える山は、近年の土砂崩れで山容が変わったが、かつては頂上が平らで、ここに風林火山の軍旗がひるがえった。また、天正三年(一五七五)五月、織田・徳川の連合軍が戦国最強とうたわれた武田の騎馬隊を設楽原(しだらがはら)で迎え討った長篠の戦いで、家康が本陣をおいたのも茶磨山だし、慶長十九年(一六一四)二月の大坂冬の陣でも、家康は、現在の天王寺区茶臼山町にある茶磨山に陣をかまえた。

全国的に見ると、毛利の勢力下にあった地方には、なぜか茶臼山がきわだって多い。ところで、なぜ茶臼山なのか。布陣すればまず。「一先引き候えば、敵は粉になし可申候えば、実(げ)にも実にもとて……」(陣を布くが、引くにかかっている)。どの茶臼山も富士山の形をしている。
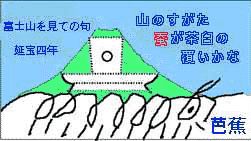
頂上が平らで円錐形に裾がひろがっていて、見渡しが利いて陣を布くには好都合なのである。俳人松尾芭蕉は富士山を見て、
山のすがた 蚕が茶臼の 覆いかな (延宝四年〈一六七六〉夏)
と詠んだ。岩波文庫『芭蕉俳句集』に「蚕(蚤)」とあるのは、後世に弟子が蚤と朱を入れたためらしい。古い諺に、ありえないことが現実になったことのたとえに「蚤が茶うす」とある。蚤が茶臼を背負って富士山をチョイと越えた、つまり足軽からの成上りものが天下をとった故事に由来する。しかし、蚤が茶臼を背負ったのでは句にならない。あるとき、初夏の早朝に新幹線から富士山を眺めたら、麓を白い雲が覆って、その上に茶臼に覆いをかけた恰好の山があった。芭蕉は夏にこの雲を蚕と見たてたにちがいないと思った。ほかにも2-3茶臼山の句がある。
5.4 戦国の秘密工場
日本では茶磨は茶の湯にともなって普及したが、粉挽きの石臼はどのようにして普及したのであろうか。実は意外な、これも日本独自の普及過程をたどった。軍事用だったのである。種子島に鉄砲が伝来したのは、天文十二年(一五四三年)とされているが、それ以降日本では鉄砲製造技術が急速に進歩した。ノエル・ペリンというアメリカ人が書いた『鉄砲をすてた日本人』(紀伊国屋書店,1984)によると、戦国時代の日本は、鉄砲の技術水準もその所有数も世界一だったとある。新技術導入には必ず何かペースになる技術があるが、鉄砲は刀鍛冶の技術がべ一スになった。伝来から約三十年後の長篠の合戦には織田・徳川の連合軍が鉄砲隊を組織して、戦国最強を誇る武田の騎馬軍団を撃破したことになっているが、それよりも2-3年前に石山本願寺で浄土真宗門徒が信長を千丁もの鉄砲で銃撃し大いに驚かせた。
戦国の武将たちは、この新兵器を手にいれるのに血まなこだった。しかし鉄砲も火薬なけれぱタダの筒」だ。これは「コンピューター、ソフトなければタダの箱」というのに似ている。だが歴史書に鉄砲の話はあっても、なぜか肝心の火薬の調達とくに製法については曖味である。鉄砲伝来当初には、火薬の一つの原料である硝石を、堺の商人を通じて外国から輸入したようだが、まもなく国産化した。黒色火薬は、硝石七五、木炭一五、硫黄一〇の割合で混合したものである。いずれも細かい粉末である。
硫黄や硝石は粉にしやすいが、木炭を粉にするのはかなり難しい。その粉づくりの技術次第で鉄砲の性能が左右される。粉にする仕事は下級武士が下々に命ずる。下々はまだその手下に命じる。このパターンは現代のハイテクの大企業が下請に素材をつくらせるのに似ている。現代の下請工場の歴史が残らないであろうように、戦国時代のマル秘火薬調合工場にも一切の記録がない。
しかし、ここにひとつの事実がある。この時代の激戦地の遺跡から、おびただしい石臼の破片が、まとまって出土することが多い。しかも、おもしろいことに、抹茶用の茶磨と粉を挽く石臼とが、同じ場所に集まっている。全く用途がちがい、挽く人の身分もちがうはずの二種類の石臼が混在するのはなぜか。よく調べると、石の質も形状もまちまちなのである。これはあちこちから集めてきた証拠である。茶磨は当時まだ一般庶民には普及していない道具だから、かなり遠方の寺院なごからとりよせた。その石臼は攻める軍勢に徹底的に破壊されている。敵の手にわたるのを恐れたのか、それとも侵入者が破壊したのだろうか。長野県伊那郡で発見された遺物は囲炉裏の灰の中だったという。おかげで火災で焼けてはいたがほぼ完全な形状を留めていた。それは天正元年信長軍の仕業だった。
 福井市の朝倉氏遺跡から出土したばかりの茶臼片(粉挽き臼と混在している),矢印は粉挽き臼
福井市の朝倉氏遺跡から出土したばかりの茶臼片(粉挽き臼と混在している),矢印は粉挽き臼

もうひとつ東京都葛飾区青戸の環状七号線の下に永遠に埋没した葛西城跡(http://www.asahi-net.or.jp/~ju8t-hnm/Shiro/Kantou/Tokyo/Kasai/)でも同様な発掘品があった。発掘現場で撮影した遺物。これは何の戰いかも不明だが、間違いなく同じ時代に違いない。強者どもの夢の跡を見る思いがする。
ところで、これが火薬工場だったとはじめていいだしたのは、福島県郡山地方史研究会.会長だった田中正能氏であった。氏は戦時中、平塚市にあった陸軍の火薬工場にいて、炭の粉づくりに苦心した人で、その体験がこの説を迫力あるものにしていた。
5.5 日本独特の石ウスの普及過程
戦乱の時代がおわり、徳川幕藩体制が確立すると、東海の島国日本は、鎖国により外国からの影響をうけない三百年の太平が、文化の純粋培養、独自の文化を開花させた。世界一の鉄砲と火薬の技術も不要になった。ノエル・ペリンがいうように、鉄砲をすて軍縮の見本を世界に示した。このように平和の文化を培った日本が昭和になって侵略戦争に突入したのは理解し難い。
 石臼の目立師が巡回していた(臼の目と挽き手の付け方からして東海道の静岡辺りか?(浮世絵より模写)
石臼の目立師が巡回していた(臼の目と挽き手の付け方からして東海道の静岡辺りか?(浮世絵より模写)
ところで、戦国時代に全国にひろがった石臼は、百姓にとっておもいがけない利用の道があった。米は根こそぎ年貢でとりたてられる。残るのは、屑米やそば、稗、粟、黍などの雑穀である。屑米はそのままではまずいが、粉に挽いてだんごにすれぱ食える。団子汁のことを「とちゃなげ」と言ったと東京都青梅で聞いたがうまい表現だ。天明の飢饉のいい伝えに「粉にすれば何でもたべられる……」というのがある(美濃民俗 第230号『天明の飢饉』)。
杵と臼よりもはるかに粉にする能率が高い石臼の出現は百姓に飢饉の耐久力を高めた。徳川幕藩体制を支えた技術に石臼があったのである。石臼以前にももちろん雑穀を食べたが、道具はすべて杵と臼だった。石臼出現の効果は、保存性のよい乾粉がつくれることである。それについて、柳田国男著『木綿以前の事』には、こう書いている。「近世の一つの顕著なる事実は、石の挽臼の使用が普及して、物を粉にする作業がいと容易となり、したごうてこれを貯蔵して常の日の「け」の食物となし得たことかと思う」。
百姓の食物にはお祭やお祝事などの「ハレ(晴)」の食物と、「ケ(褒)」つまり日常食の区別があった。石臼の普及によって、ハレの食物がケの食物に順次移行し、日本人の食生活には、まさに革命的な変化が起こったというのである。「搗き臼で粉を造ることは、今から考えると煩わしい作業であった。シトギの如く湿った粉でよければ、水に浸して柔らかくしてもおける。黄な粉、炒粉のように、一度火にかけたものもまた砕けやすい。蕎麦などは押し潰せるからこれもまだ始末がよい。生米、生小麦を粉にして貯え、入用のときに出して使うということは、挽臼なき時代にはほとんど望み難かった。したがって、ときどきの好み物の調理には、いわゆるときどきの好みの物の調理には、かなり女たちの長い骨折りな準備を要したのである」
このように柳田は湿式ではなく、直ちに使用できる乾粉の出現が、食革命のポイントであると指摘した。乾粉の便利さは現代のインスタント食品やコーヒーを見れぱ理解できる。江戸時代になると、籾すり専用の木摺臼や土臼が発達して、それまで搗き臼のみであったころに較べて、生産性が著しく向上した。木摺臼は中国にはないようで、日本独自の発明らしい。
5.6 石ウス文化圏]
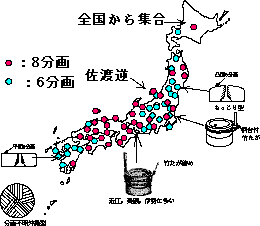 六分画と八分画の地方性
六分画と八分画の地方性
私は、1970年代に石臼を追って日本中をあるきまわった。日本の生活様式がいわゆる高度成長で大きく変貌しつつあった頃である。まだ田舎では、石臼が庭先に放り出されたばかりだった。臼についての記憶をもったひとたちも多かった。それを『石臼の謎』という著書にまとめたが、いまでは、その本に掲載した写真の人物はほとんど亡き人になった。こうして日本列島全体にわたって調査してわかったことは、まず第一に八分画圏と六分画圏の存在であった。そこで従来にはなかった分画という新語を導入することにした。近畿圏の八分画、関東およぴ九州の六分画は、じつに明瞭な分布を示した。くわしくは、複雑に入り組んでいるが、基本となる八と六の交流の結果であって、それぞれ理由があった。混在している例もあるが、興味深いのは白山麓にある福井県の白峰村である。福井は東海北陸の影響で6と8があきらかに混在していた。現地を調べたところ、この地は天領だったので、江戸から来た関東の石工が伝えたものらしい。このほかにも、形態や挽き手のつけかたなどに特徴があって、地方性が明瞭であった。石臼のお嫁入りといって、たとえば、四国・高知の臼が、江戸にあったり、信州の臼が、織姫について江州(近江)に来ていたりするのも、必ず理由があり、確認できた。また石工の移動はその他の石造物と関係していた。ことに信濃の高遠石工の移動は興味深かった。
しかし私が調べはじめた頃のこと。「名神高速道路で張っていたらいいですよ、大型トラックで四国の石臼が東京方面へ運ばれていますよ」という情報があった。庭師が石臼を使うのだ。確かに私も四国で倉庫に山と積まれた石臼に何度も出会った。しかしそれらは上石と下石が対になっていず、意味がないものだった。韓国から50組買い込んだが、売れない。どうかならないかという相談も受けた。その頃韓国の石臼は庭の蹲(つくばい)にちょうどよいので利用されたようだ。それからかなり後のことになるが、1998年にソウルを訪問したときには、もっとすごい光景を目にすることになった。ソウルの骨董屋街に城壁かと見まがう石臼の勢揃い。全部日本向けですと。一年後同じ場所へ行った友人はそれがすべて姿を消していたと。それが日本へ来たのかどうかは確認していない。現在では手に負えない状態だ。
石臼の研究は、日本の地方文化のながれを追うことでもあった。方言、風習、植物、その他各種の地方性研究結果と実によく一致したのである。石臼の材料は花崗岩、砂岩、溶結凝灰岩、安山岩などである。しかし、そのような岩石名は地学で岩石の成因を考えるにはよいが、石の道具を考えるには適当ではない。それはたとえば人の個性を問題にしたいのに、この動物は、人類か、それとも猿かと論じているようなものである。地方によって、同じ花崗岩でも性質が違う。同じ山でも採掘場所によって大きく変る。地方名のついた石材名、たとえぱ京都の白川石、滋賀の曲谷石(まがたにいし)、三重の石榑石(いしぐれいし)、岡山の万成石(まんなりいし)、四国の撫養石(むやいし)、東京都五日市の伊奈石など無数のバリエーションがあった。なお伊奈石についてはその丁場(石取り場)が開発により失われるため調査グループが誕生して詳しい報告書が作られている。
5.7 鉱山臼一隠し金山の謎
石ウスにはもうひとつ別なルートがあったようだ。鉱山技術である。戦国時代になると砂金が簡単に集められる川がなくなって、山師たちは次第に川をさかのぼって、砂金のルーツ、金の鉱山を発見した。これには自然物の単なる採集ではなく、人間がとりだす粉の技術を必要とした。そのひとつの例は、新潟県岩船郡朝日村にあった。探検好きの貝沼英雄氏(朝日村教育委員会)の案内で、私も訪ねてみた。上杉謙信の隠し金山と伝えられる鳴海金山跡である。最近まで、だれもそこには近づかなかった。「目をわずらう」と言い伝えられていたからである。金山であることを秘密にする手段だったのであろう。
かつては村から徒歩で山まで到着するのに、丸一日かかったという山奥だ。最近林道として自動車道が完成し 狸穴とよばれる狭い入口から中へはいると、洞穴は縦横にのび、あるものは山を貫通していた。金は岩の割れ目の粘土分にわずかに含まれていた。岩を砕き、さらに水を流しながら、石臼で細かく砕く。洞穴の奥深くに石臼多数が設置されていた。壁や天井一面に松明(たいまつ)を焚いた煤が付着している。鬼気迫るこの坑道に秘密の選鉱場があったのである。このような昔の金山は各地に知られているが、全貌はわかっていない。後世にもたぴたぴ山師達が入山しているので、どこまでが古い時代なのか知るよしもない。
ところで、これらの鉱山跡から発見される石臼は普通の粉挽き臼とは全くちがっている。水挽きであるから、硬い石英質のの石を利用し、目がない臼による完全な磨砕である。上石の中央には供給口があって、軸受の金物をとりつけた跡がある。このように中央に供給口があり、そこに軸受をつける方式は、ページ)に示した西洋のリンズ方式である。鉱山技術を伝えたのが宣教師だったことと関係があるのであろう。武田信玄の鉱山跡もあった・
5.8 化粧料]
古代から現代まで、色粉抜きで日本の色は演出できなかった。化粧の本によると顔に白粉(おしろい)や紅などを塗って美しく見せることを化粧といい、転じて、ものの外観を美しく飾ることをいうとある。化粧は人体にかかわるもののほか、建物や道具など、人間が生活する場にたくさんみられる。人間はなぜ化粧するのか。心理学の本を読むと、化粧は、平常とは違った気持、つまりある種の異常心理をつくることだとある。心理的条件設定である。なにか人のまえで、ひととは変ったことをやろうとするとき、人は化粧によって心理的条件設定をする。俗ないいかただが、要するにカッコウをつけることだ。お坊さんは黒い法衣にきれいな袈、裟(けさ)をつけ、ガードマンは警官のイミテーションで、お医者さんや看護婦は白衣でと、それぞれの衣装をつける。普段着にかえたら普通のひとである。私が大学へ普段着で演壇に立ったら学生たちがとまどった。
「なにかおかしいか」と言うと「やっぱりおかしい」と。それ以来私もスーツ姿に変えた。
あるいは、誇りを保つひとつの手段だともいえよう。人間にとって誇りを保つことは、ときに食欲を充たすことにまさり、場合によっては命をかけることも辞さない。古代人が顔や体に赤や白の土をぬりたくって、お祭をしたり、呪術者が特別な化粧をしたのもそれであった。科学以前の社会では、呪術(じゆじゆつ)や宗教の意義は、現在では想像もつかないくらい重要であったから、色をもとめて、たいへんな努力がなされたにちがいない。
古来、日本では赤と白の対照が鮮やかである。平家と源氏の赤旗白旗、運動会の赤勝て白勝て、白地に赤い日の丸、口紅と白粉(おしろい)、お祝の紅白、紅白歌合戦と、数えれぱ実にたくさん赤と白を利用している。そして奇しくも七〇年代に出現した赤ヘル白ヘルは、もっとも日本的だった市毛勲著『朱の考古学』(雄山閣,1975)。オフィスのハンコも白い紙に赤だ。この朱肉も、今はスポンジにつけた安物が多くなったが、たいせつなお金や信用を、ハンコにこめるのだから、朱肉くらいは本物を使いたいものだ。本物となるとグラムうん千円、繊維は良質のモグサに種油で練った朱つまり、硫化水銀である。ときどき練って、中高にもりあげておくものだそうである。ハンコでつついて、へこんでいるようでは、金も信用もぱっとしない。いまどき水銀といえば神経をとがらせるが、弁当箱やお箸などの食器の朱漆は大部分が硫化水銀だった。無機水銀は、有機水銀のようではないが、毒物には違いない。赤色顔料は最近ではほとんど有機顔料に変ったので、日光にさらすと変色する。京都の修学旅行の思い出に、平安神宮の赤い大鳥居が印象に残っている人も多いことだろう。平安神宮は全般に赤が多にいが、本当の丹塗つまり水銀朱は拝殿だけだと聞く。
古代中国の書『魏志倭人伝(ぎしわじんでん)』に、「倭人は朱丹をもってその身体に塗る。中国の粉を用うるが如きなり」とある。赤は日の出の色夕日の色、火と血の色だから、その色合をだすのに苦心した。深紅は色合により、荘厳恐怖権威を象徴した。楊貴妃やクレオパトラもは口紅に使ったから短命だったという。王様は不老長寿の薬にもつかった。おおらかな時代の話である。古墳のなかには朱が塗られている。さいきんでは藤の木古墳の朱塗りの石棺が有名だった。古墳の内装に使ったのは死者復活の願いをこめたと同時に防腐効果の利用であった。古代の赤色顔料は朱砂(水銀朱、硫化水銀、辰砂、朱砂)、鉛丹(光明月、赤鉛、赤色酸化鉛)、ペンガラ(弁柄、紅柄、鉄朱、鉄骨、酸化鉄)の三種だった。なかでも朱砂は貴重視され、殊に中国・湖南省の朱砂が知られていた。古墳から副葬晶として、朱をつくるための独特の臼が出土することがある。天然朱つまり天然に産する朱砂またはペンガラを微粉砕することによってつくった古くは中国から輸入したが、次第に国産化されるようになった。『続日本紀』(七九七年)によると、文武天皇の二年(六九八年)には伊勢常陸、備前、伊予、日向から朱砂が献上されたとある。神社、仏閣の丹塗に大量に使われるようになった。朱砂は水銀製造原料でもあり、金の精錬には欠くことのできない副原料だった。奈良の大仏にも莫大な水銀を使ったことは、よく知られていることだ。その産地は次第に富と権力が利用する地域になったであろうことは想像に難くない。しかしその製造はどのように行われたか。どんな石臼が使われたかはよくわかっていない。毒性の強い物質を扱った人々の苦難についても歴史の闇に葬られている。粉砕した鉱石は水流を利用した粒揃えの方法(水簸、淘汰、分級)が必要だった。有名な飛鳥の酒船石は朱砂の水簸装置ではなかろうかという有力な説がある。私も実測してみてその説に賛成したくなった。あの角度をなす溝は日時計であり、水簸時間を正確にコントロールしたと考えてはいかがであろうか。
『朱の考古学』(文献**)には従来の研究が集約されており、非常に多くの人々によって古代水銀鉱山の探求が行われている。水俣病問題のとき土に含まれた水銀分析の全国的調
査が行われたデータも参考になる。とくに「丹生(にう)」という地名が全国に数百箇所もあり、それが水銀鉱山に関係していること、およびその分布が特定地域に偏在しており、とくに弘法大師と縁がふかいのも興味深い。たとえぱ岐阜県揖斐郡徳山村に戸入門人という地名があり、これは丹生だという。おにゆう近くに垂直坑道をもつ水銀鉱山があり、弘法穴がある(しかしこの地はダムに水没した)。また福井県の遠敷郡が「にゅう」など、いまはさぴれているが昔は栄えた地方であったことを考えるのは興味が尽きない。
[ペンガラ]
赤色を演出するもうひとつの主役に、ペンガラがあった。鉄の鉱山で、真赤な粉が付着した石を見つけることがある。鉄の錆から連想する赤とはおよそちがう、毒性がなくて美しい色である。古代にはこれを集めたが、やがてその工業的製法が発達した。ペンガラの高級品は九谷焼、伊万里の柿右衛門の赤色に、また漆では輪島塗などの朱漆、堆朱に朱砂とともに珍重された。また町屋のペンガラ格子の塗料もこれであった。ベンガラ格子は、関西方面、とくに関ヶ原以西に多かった(金沢、名古屋仙台にも多少あった)。格子ばかりでなく、室内の塗装にも使った。武士や貴族の家には使わず商家に使うには訳があった。町人が高級な材木をつかうのは禁じられていたのでペンガラを塗ってごまかした。町人の意地である。田舎では金持の家につかった。京都の祇園一力薬屋の豪華な柱や室内、床の間の漆はペンガラと炭の粉を種油で練って黒色を出している。その他、マッチの摩擦面、船底塗料、レンズ暦き(研磨材)なとたくさんの用途があった。たとえば藍染の下染につかうと優に百年も退色しないという。
[吹屋ペンガラ]
岡山県川上郡成羽町吹屋(ふきや)に、江戸時代から栄えたペソガラエ場があった。昭和三十年代に生産を中止し、今は遺跡として保存されている。まだ遺跡指定されて整備されていない頃訪ねた私は、ちょうどその時代に、新入社員として、これとそっくりの工場へ就職して働いた経験があるので、タイムカプセルに入った感慨だった。種々の生産設備もさることながら、休憩室、風呂場、そこに落ちていた木製の物差し(スケール)まで、すでに忘れ去っていた高度成長期以前の日本の生活の匂いがそこにあった。工場の生活遺跡だ。現代に先だつ時代の生産方式の典型をここに見ることができた。硫化鉄鉱石を五センチ角ぐらいに手割りして、山の傾斜に高さ三メートル、幅六メートル、長さ二〇メートルに山積する。薪と鉱石を交互に積み、三十から五十日焼く。つぎにできたものを竹ざるに入れて水で浸出し、上澄みを煮詰める。晶出した結晶をローハという。残りは再度積み上げて繰り返し焼く。亜硫酸ガスで山は枯れ、川には硫酸が流れた。現代では想像もつかぬおそろしい光景だが、のどかな時代の話である。ローハは焙烙(ほいろ)に入れて焼いた後、これをカラウス、のちにはスタンプミルで粉砕、さらに石ウスで微粉砕する。次に粒揃えと酸抜きを目的とした水簸を行い、天日乾燥する。この技術は現代のフエライトすなわち、磁気記憶テープなど現代情報産業の故郷である。
[人肌色を演出した粉一胡粉(ごふん)]
おもしろいことに赤い色を造った水銀と鉛は、白粉の原料でもあった。御所白粉、伊勢白と人肌色を演出する粉はハラヤとも呼ばれて、水銀が原料だったし、京白粉は鉛だった。毒ゆえにシラミとり(駆虫剤)にも使われた。花魁(おいらん)薄命の主要原因になった。ちなみに現在の白粉は、酸化チタンである。それにくらべると、人形の化粧は、薬効成分のある胡粉であったのは不思議である。胡粉の原料は天然牡蠣である。昔の人形の胡粉が作りだす人肌色は、誰でもいいしれぬ魅力を感じる。水に膠を溶かし、胡粉を分散させる。それを静置すると、粗い粒子から先に沈んでゆくので、上澄みを筆につけて十一二十回も繰り返し塗る。その結果、表面ほど細かい粒子になる。乾くにつれて、胡粉の細かい粒子間の液体は少なくなるが、このとき、液体の表面張力による大きい吸引力が働く。それが固まる原因である。最後に残った膠の微妙な弾力が肌ざわりをつくっている。胡粉にはもう一つおもしろい性質がある。どろどろのものを塗るので、塗ったものが、だらりとたれては具合が悪い。たれることを職人用語で「へたる」という。ところが、胡粉は筆を動かしている間だけ自由に動くが、筆をとめると動かなくなる。このような性質のことを、フロインドリッヒの命名(一九二八年)にしたがってチクソトロピックな特性といい、塗料に一般的に要求される特性である。御所人形の、たとえば眉(まゆ)おきあげ手法とよばれるのはそれである。
昔は関西では生駒山麓や江戸にも胡粉工場があったが、現在では胡粉製造工場は宇治市の私の家の近くにある中川胡粉(株)だけになった。
[現代の化粧品の正体】
参考のため最後に現代の化粧品について付言しておく。すべて粉である。メークアップ化粧品の顔料ファンデーション(酸化鉄、酸化チタン、タルク、雲母有機顔料)
アイシャドウ、頬紅、アイライナー(酸化鉄、群青、雲母、タルク)
口紅(有機顔料、酸化鉄、酸化チタン)
白粉打粉(タルク、雲母、酸化チタン)
肌色を出す重要な顔料は酸化鉄で、これが入っていない化粧品はないとさえいわれる。酸化チタンは○.二一〇・三、・・クロン、あるいは○・〇三一〇・○八ミクロンという細かさだ。のびには、ナイロンパウダ=、シリカパウダー、セルローズパウダー、いずれも球状でローリング効果という。まさに粉飾の極である。