今から二百年ほど前の寛政十年(一七九八年)の『筑前国風土記』にはすでに現在位置にあることが記され、「茶臼」と注記してある。「鬼の茶臼」と俗称されたのは、当時すでに正確な言い伝えが消滅していて、わけのわからぬ存在だったことを示している。
一九八四年十二月十七日、同寺と九州歴史資料館およぴ同志壮大学の森浩一教授(考古学)らの協力をえて、大きな上石をもちあげて、実測調査する機会が与えられた(三輪茂雄『古代学研究』第108号11985)。


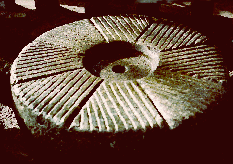
リンク:失敗作の行方
粉の文化史 4章
4.1 石臼伝来を暗示する日本書紀の記述
日本の石臼はいつ、どこから来たのだろうか。『日本書紀』に「推古天皇の十八年(六一〇年)春三月、高麗王、僧二人を献じ、名を曇徴、はじめて碾磑を造る。けだし碾磑を造るは、このときにはじまるなり」とある。碾磑というのは前章で説明したように、中国で発達した水車式製粉工場であり、貴族や寺院が経営して利益をあげていた。それがこのとき日本に伝えられたらしい。この時代は飛鳥時代で聖徳太子が活躍していた華やな時代である。
この碾磑という用語は古代中国文献で石臼そのものを意味する場合と、水車をふくめた製粉工場設備全体を指す場合とがある。第三章でのべた西洋のミル(mill)という語と全く同じ使われ方である。わが国でも当時の法律書に出てくる(瀧川政次郎:『社会科学』(改造社,1926))。
4.2 太宰府の観世音寺で実地調査
この碾磑をめぐり二つの謎がある。その一つは、九州・太宰府の観世音寺に巨大な遺物が現存する。もうひとつは後述する東大寺碾磑門である。観世音寺の遺物は寺の講堂前の広場に石垣で囲み「碾磑」と書かれた立札がある。その石臼は直径一メートルを超え、重量は上下それぞれ約四〇〇キログラム(体積から推定)という巨大なものだ。自由に見学できるので、現地に行かれる機会があったら是非確かめてほしい。
今から二百年ほど前の寛政十年(一七九八年)の『筑前国風土記』にはすでに現在位置にあることが記され、「茶臼」と注記してある。「鬼の茶臼」と俗称されたのは、当時すでに正確な言い伝えが消滅していて、わけのわからぬ存在だったことを示している。
一九八四年十二月十七日、同寺と九州歴史資料館およぴ同志壮大学の森浩一教授(考古学)らの協力をえて、大きな上石をもちあげて、実測調査する機会が与えられた(三輪茂雄『古代学研究』第108号11985)。


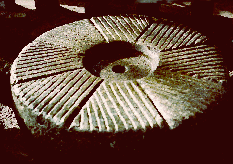
長い年月、風雨にさらされていたため、上石の上面はかなり風化が進み、亀裂もあるから、ウィンチで少し吊り上げ、計測と臼の目が観察できる程度の調査であった。堆積していた土砂を洗い落して、臼の目がはっきり姿を現わした瞬間の写真が上図である。当日は曇り空で、今にも雨が降り出しそうな天候だったが、臼面を水洗いした直後、明るい陽ざしが目をくっきりと照らし出した。居合せた人々は一瞬、八分画十溝の見事なウスの目の美しさに見とれて声もなかった。上下石が重ね合せたまま置いてあったおかげで、臼面は風化がなく、新鮮な石肌が保たれていた。石材は花崗岩かもだが断じ難い。私はさっそく準備していた長尺(1,5メートル)の直線定規を下石にあててみた。当然のことながら、完全な平面が保たれ寸分の狂いもない。現在のように大型の機械研磨盤がなかった時代に、これだけ大きな石材の加工を、この精度でやるのはただごとではない。石積みの平面程度の加工ではなく、機械の摺動面加工である。私はこれをつくり出した技術水準の高さに驚異を覚えた。飛鳥で2000年になって発掘されて話題を呼んだ数々の石像物に固い石に水を流すための円い孔が開けられているのを見て、当時の石材加工技術の偉大さを見せてくれたが、その同時代だから当然かも知れない。
もう一つこの調査で是非知りたいことがあった。四○○キログラムもある重量を支えて、スムーズに回転させる軸受機構である。これは上石の中心部に直径約三○センチ、高さ約五センチの凸起部をつくり、下方には上石の凸起部がちようどはまり込む穴をうがち、さらに中心に心棒孔を設け、ここに鉄の心棒を入れたらしい。さらに回転精度を保つために完全にすり合せて、ツルツルにしてある(これは上下臼があがった瞬間に手を入れて触った感触である。(そのとき作業者から「あぶない」と声がかかり、ひっこめた)。このような石臼の軸受機構はわが国では実物も文献にも類例がない。
ところで、この臼は何を挽いたのであろうか。私はこの調査を行うまで、小麦であることを半ば期待していた。ところが答はノーであった。臼の目の形は、頂上が平らでしかも滑面になっている。これでは小麦の皮を破ることは不可能だ。それに主溝が異常に深い。これではよい小麦粉は生成せず、粒の混じった粉になる。このような目は、水を流しながら鉱石の粉を微粉砕する場合のものか、それとも水挽きの豆腐製造用かも知れない。高句麗から来たとすれば豆腐の可能性が強い。僧曇徴が仏教の殺生を説くに際し、海産物に依存している日本人に、代わりとなる蛋白源として豆腐を与えたと考えることもできる。
次に私は吊り上げられている上石面を眺めて、上下の目の交叉について確認しようとして、不思議なことに気がついた。上石の目のパターンは下方と同じである筈なのに逆になっている。もしこれを重ね合せたとすると、目は交叉しない。これは石臼の原則に反する。そのことを報告すると、居合せた人々の間で、ガヤガヤといろいろな議論が出た。「もしかすると、もう一組あって、上下石が入れちがったのではなかろうか」「目立てを勘違いして、逆にしてしまったのだ。僧曇徴か臼師の勘違いだ」「水挽き用ならば、目はなくてもよい。中古の小麦用石ウスを転用したのかも」等々。謎はさらに謎を生む。観世音寺境内には、朱の製造という目で見れば、用途が考えられる怪しい石造物もある。同寺には造営時に朱を磨ったという伝えもあることから、将来に残された課題である。これが日本へ石臼が伝来した、碾磑第一号であることだけは事実である。そして、それは発展せず、それっきりに終ったらしい。
4.3 韓国の臼
1998年7月、日本臼類学会調査団として『韓国の食文化史』(ドメス出版)の著者ユン瑞石先生(中央大学家政大学名誉教授を訪問した。曇徴の生地は高句麗だが、とにかくソウルへ行くことになった。
 北朝鮮・妙香山普賢寺にあったと森浩一教授からいただいた写真
北朝鮮・妙香山普賢寺にあったと森浩一教授からいただいた写真
高句麗から来たという曇徴や、北朝鮮にあったという上図の石臼について聞くためだった。それに類する石臼がいくつかのソウル市内のお寺を案内してもらった。かなり古く少なくとも500年以上前という。上臼はいずれもなくなっていた。西洋の石臼はもっぱら乾いた粉末をつくる小麦製粉主体で発達したが、韓国ではでは豆腐用の湿式の粉砕が発達したようで、デパートでは。一九九八年十二月五、六日、大分県湯布院で日韓石臼シンポジウムを開催し、韓国の調理学者たちが韓国の古寺院に豆腐をつくった石臼が多数ある例を報告した。寺の催しの精進料理につかう豆腐を多数の参加者に供するためという。しかし形態は同じだが、これらはすべて直径七〇センチどまりで、観世音寺や北朝鮮のものほど大きいものは見つかっておらず、今後の調査に期待しなければならない。
 ソウルのデパートでは韓国の簡易電動小型石臼で豆乳の挽き売りをしていた
ソウルのデパートでは韓国の簡易電動小型石臼で豆乳の挽き売りをしていた
4.3 東大寺転害門

東大寺の西門は「てがいもん」と呼ばれている。奈良の東大寺は、南大門側から入るのが普通なので、西門を知る人は少ない。西門を転害門」というが、変な名前である。その門前にはバス停があって「手貝町」と書かれている。この門の呼び名の由来は古文書ではさまざまで、手貝、天貝、手蓋などのあて字が使われている。婆羅門僧正がはじめて東大寺に入ったとき、行基菩薩がこの門で迎えた。その姿が手で物を掻くようであったので手掻門というとか、小野小町が落ちぶれて乞食'になって云々などの俗説もある。ところで耳よりなのは『南都七大寺巡礼記』(『大日本仏教全書』120巻寺誌叢書第4所収:『続々群書類従』第11巻宗教の部所収)などの古文書に度々でてくる碾磑に関する記述である。「西向の南より第三門也。碾磑御門堂と号す。此の門の東に唐臼亭あり。故に碾磑門といふ」
また、「碾磑亭は、七間瓦屋なり。碾磑を置く。件の亭は講堂の東、金堂の北にあり。その亭内に瑪瑙唐臼を置く。これを碾磑と云ふ。馬璃(めのう)をもって之を造る。その色白也」。ここで唐臼と書かれているのは、俗にいうカラウス(足踏みの米つき臼)ではなく、外国から来たすぱらしい石製の臼の意味である。また享保二十年(七三五年)刊、村井古道著『奈良坊目拙解』には、以上の記録をまとめて「尋尊僧正七大寺巡礼記にいふ。天平の朝、瑪瑙東大寺食堂の厨屋(みくりや)にあり。これは高麗国より貢いだ所である。その西門を碾磑と云ふ。てん(車+展)硅あるいは転がい(石辺にじん)は、今俗に云ふ石臼が是である」と記している。高麗国より貢いだというのは『日本書紀』の記述を勝手に結びつけたものだ。これ以上、文書を調べても何もわかりそうにないが、今の転害門はもともとは「碾磑門」であり、そこの近くに人の目をひく美しい石ウスがあったことだけは確かだ。この話を学生諸君に話したところ、熱心な学生達(赤松徹君と清原義人君)が付近を調べて「臼の目らしい跡のある石が、基壇部にありました」と、写真をもってきた。さっそく見学に行った。確かに単なるいたずらにしては出来すぎている。八分画十六溝直径一メートル余りのウスの目のパターンが復元できるのである。それぞれ隣接する分画も一部分が確かに存在する。「これは偶然のいたずらだよ」と私は言い切ることができなかった。定規をあてると、観世音寺の碾磑と同じく、完全な平面加工の形跡もある。さりとて、碾磑と断定するには、転用されていて、確証がない。天平の謎は容易には解けない。
異国の珍貴な食べ物として、わずかに貴人にささげる小麦粉のお菓子などがあったとしても、その程度の製粉は、弥生時代以来の搗き臼や、足踏み式のカラウスで十分用が果せた。碾磑は水力利用の大量生産用である。輸入したものを使いこなすこともなく、廃れていったのであろうか。それ以後約四百年以上もの間、石ウスの形跡は日本列島にはほとんどない。というのは下記の東大寺での発見があるからである。確実に平安時代の層位と思われる遺跡から、例えぱ国分寺跡貴族の住宅跡に、石ウス片が発見されたという報告もないではないが、いまひとつ確実性を欠いている。とにかく記録に残ったり、ある程度の普及を示すほどには至らなかったことだけは確かである。
4.4 考古発掘物(石臼片)が碾磑仮説を現実にした
2000年10月5日夜電話があって「東大寺食堂遺跡で石臼らしいものが発見されました。石臼かどうか確認してもらいたいのですが、近鉄奈良駅の行基菩薩像まえで待ちます」。私は耳を疑った。それも食堂遺跡という。「明日うかがいます」と返事。発掘現場の泥だらけの車が迎えにきた。1999年何気なく二月堂から歩いた東大寺大仏殿北側だった。住宅建設にともなう発掘である。担当者は橿原考古学研究所の今尾文昭さん。
長さ約30cmだが幸い下臼の周縁部分なのでその円弧の半径から推定される直径は1メートルを確実に越えている。目は8分画で非常に大きい石臼である。付近から出土している食器類から少なくとも奈良時代前期と推定されている。となると東大寺古文書の記述にある石臼である可能性が高い。余りにもよくできた話であるが、現物を前にすれば否定しがたい。この発掘遺物はしばらく樫原考古学研究所の展示室で公開された後、今尾文昭さんの研究室で保管されている。研究所の従来の展示分類項目にないらしい。

 井戸の積石になった石臼片が発見されたそのズーム
井戸の積石になった石臼片が発見されたそのズーム
4.5 奈良・依水園で発見された謎の大きな石臼群
「名勝依水園は、前園は江戸期、後園は明治期にともに奈良晒しの豪商によって作庭された屈指の池泉回遊式庭園。特に後園は、若草山・春曰奥山・御蓋山を遠景に、借景に東大寺南大門の甍という大らかな天平時代の眺望を楽しめる。」
(http://dir.yahoo.co.jp/regional/japanese_regions/leisure_facilities/art_museums/nara/000950/)より
ここに大きな石臼があるという情報をいただいた。急遽石臼研究の仲間・大西市造さんと同園を訪ねた。東大寺境内は大きいが、依水園の矢印案内に従って確実にたどりつけた。お知らせいただいた小野和子さんは唐招提寺にお出かけ中だったが、寧楽美術館館長中村記久子さんの案内で拝見した。直径60cmの上臼だけが池を横断して並んでいた。ほかに道などに埋めたものも併せると十組を越えるがすべて上臼(雌臼)だ。対の下臼は池の下に埋まっているのだろうか。
石臼は明治末に使わなくなった石臼という。明治までは奈良晒しに使った糊臼と伝えられているという。晒しといえば木綿を想像するが日本では古くから麻布だった。奈良晒しとは麻の白地の布で、水に浸けて漂白してから糊を付けて板に張ってピンと平らにするいわゆる糊張りである。お寺の坊さんの衣類をまかなうとすれば、莫大な糊が要る。この庭園はその奈良晒しの豪商が作らせたというから、なるほど。なお、拙著『石臼の謎』に出ている京友禅の石臼も糯米を昭和48年まで挽いた記述がある。
私の石臼研究の出発点であった。感慨無量である。
矢印の個所にある切り込みは挽き手取り付け穴と思われるが下記の観世音寺とは違うやりかたらしい。どうしてつけるか不明。池の中に代わりの穴があるだろうか。
http://www.hemp-revo.com/jha/association/association.htm 麻晒し布
http://www.bigai.ne.jp/~miwa/powder/kanzeonji.html 観世音寺
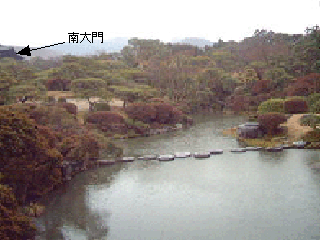

4.6 唐招提寺の大石臼
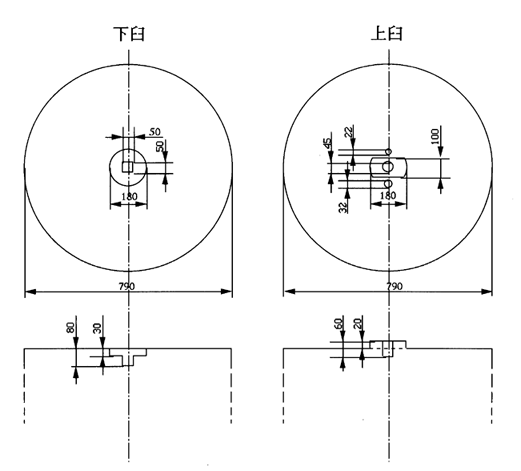

奈良の唐招提寺にも天平の遺物らしい物体があることを『奈良坊目拙解』の編者喜多野俊氏(奈良市在住)から教わった。同寺第81世長老の森本孝順著『唐招提寺』(学生社、1972)によれば、鑑真和上創建天平3年。昭和13年僧坊修理の時、北のはし、いま綱維寮という札のかかる部屋の中央の柱の下から、直径1メートル強の大石臼の片方がでた。これはとうてい人力ではまわらぬもので、たぶん牛などでひかせた今日中国で見る形式のものと想像され、奈良時代のものと推定した。やがて境内から庭石代用となっていたこの片方が探し出され、陰陽があった。柱石の根石となったのが元禄の修理とすれば250年、鎌倉時代とすれば600年ばかりのあいだ離ればなれになっていたのがまたあったわけである。」
そこで1995年に学生と現地調査した。一般観光区域外の庭石になっている。掘り起こし出来ないから、観察できる範囲で計測した。8分画12溝。下臼が凹部を持ち上臼に凸部がある点で観世音寺と共通している。供給口の大きさ2.2センチメートルは小麦の製粉用にしては小さ過ぎる。観世音寺と同じく下臼面も上臼面も完全な平面で、上臼にふくみは全くない。目の山は平滑で、溝の断面はほぼ矩型であり、これでは数個の小麦粒により溝がつまってしまう。
碾磑の臼面には同心円状に傷が見られる。この傷の存在は観世音寺の遺物と相違し、多少使われた形跡であろうか。穀物を粉砕する際に収穫時に紛れこんだ小石によるものというより、硬い鉱物質の感じ。鑑真が渡日した際に唐より引き連れて来た者による製作指導がなされたのであろうか。供給口を通過した被粉砕物は下臼の凹部へと落ちる。この凹部へ落ちた被粉砕物は、その後、溝のある部分へと移動
して行けそうもない。明らかに使用不可能である。鑑真和上は失明していた。当時の鑑真の足跡は確かに太宰府・観世音寺に立ち寄った形跡もあるから、観世音寺の碾磑を見てそれを伝えた可能性も考えられるが、鑑真がすでに失明していたとすれば、まさに手探りで指導し、このような明らかなミスが起こったとも考えられる。失敗作のは土中に埋められるのが日本の伝統(?)らしいから、その伝統のはしりかも知れない。
4.7 東福寺と碾磑
これから約五百年の空白の後、突如としてわが国最古の石臼古文書が出現する。京都五山の一つ、臨済宗東福寺派大本山、東福寺である。この寺は古くから小麦製粉や、麺業者の間では、宋代の中国から製粉術を伝えた開山・聖一国師(弁円)の威徳が讃えられているのも故あることである。この寺に国師が中国漸江省明州の碧山寺から持ち帰った『大宋諸山図』(重文)がある。テレビの取材で同寺を訪問した。たまたま五山の僧侶がお揃いの日だったので、私が訪問の趣旨を話すと、「それは見たことがないが、見て見るか」と全員の意見が一致して見ることになった。大部分は建物の絵図であって、国師が寺院を建設するさいの参考にしたのであろうが、その長い巻物の最後に、全く異質の「水磨様」と記された石ウス式水力利用製粉工場の立面図がある。最後に付け加えたという感じだ。
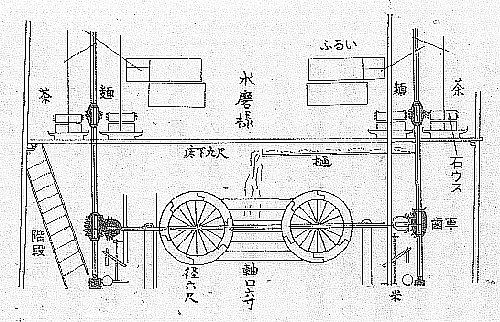 東福寺にある水磨様
東福寺にある水磨様
工場の図面としておそらく本邦最初である。絵図というより設計図と呼ぶのが正しい。たとえば中心線は現在の図面と同じく○・一ミリ程の正確な線で引かれている。水路からの水が直径六尺(約一、八メートル)の幅の広い水車によって駆動される水平回転軸で、二階まで貫通した垂直軸を回す。二階には垂直軸の左右に二台のイシウスがあって、その上臼に取り付けられた歯車で回す。石臼の近くには連結させたふるい分け機械を設置している。完全な製粉工場である。
この製粉工場が実際に建設されたのかどうかはわからない。東福寺は度かさなる戦火で再建されているためである。しかし、現存の通天橋の下を流れる川は建設するのに絶好の場所である。ここで興味深いのは、石臼の一方には麺他方には茶と書かれていることだ。抹茶と麺とは、当時の最高級の文化であった。
束福寺には文書だけではなく、もうひとつ耳よりな話がある。一九七六年に韓国・新安沖で大量の白磁や青磁を積んだ中世の宝船が発見されたが、一九八四年には東福寺と記された木簡(荷札)が見つかり、沈没したのは、聖一国師の帰朝から約八十年後と判明した。しかも発見された遺物の中に小型の石ウス二点が含まれていた。発見されたとき、留学生として同志壮大学に来ていた崔**植氏(現在釜山大学校教授)からこのことを聞き、延世大学・金えいちゅう**教授の協力をいだたき、ソウル中央博物館を訪ね、石磨の実物を見る機会をえた。1977年3月24日だった。


完全に海底の泥に埋っていたため、新品同様で使った形跡はなく、貿易品と考えられた。ウス面の直径は一四・五センチ・八分画十一溝の目は整然と刻まれ、目の形は丸みを帯びていた。下方の台には、六枚の蓮弁が刻まれた美しい作品であった。石は緑色のキメの細かい砂岩だった。これは確かに手挽きウスであるが、先に示した東福寺の文書をよく見ると、水車は比較的小さく、受け皿のついた小さな石ウスを使う小規模の工場に見える。手挽きウスを水力で回転させることもありうることだ。、日本への石ウス伝来は、この宝船以外にもあったに相違ない。このようにして抹茶用の石臼は青磁や白磁と並ぶ貿易品であった。しかし、当時の遺跡からの製粉用石臼の発見例は、私が確認したものでは鎌倉中期に一点の石臼片があるのみで、それは天皇家への海産物調理場からであった(大江御厨、東大阪市西石切町西の辻遺跡一九八二年出土》ひろく普及するのは、きらに二一三百年も先のことである。
4.8 茶の湯とともに
お茶の葉を微粉末にした抹茶をたてる茶の湯は、中国から栄西が伝え、茶の湯とともに『喫茶養生記』を著したとされている。しかし栄西は、「碾」(薬研と呼ばれている道具で粉にしていた。日本で抹茶を挽く専用の石臼が使われるようになったのはずっと後世で、栄西よりも百年以上あとのことと考えられる。中国では北宋の頃、初めて抹茶をつくる専用の石ウス、すなわち「茶磨」が発明されたと考えられている。次の漢詩は、黄山谷の叔父、王夷仲(政府専売の茶を監督する役人だった人)の詩に次韻したもので、北宋後期の詩人、蘇東坡が、杵臼(しよきゅう)杵と臼)から碾(やげん)へそして茶磨への技術の進歩をたたえている。
「次韻王夷仲茶磨」の詩
前人初用茗飲時 煮之無問葉與骨
窮*味臼始用復計其初確方出
計尽功極至干磨 信哉智者能創物
破槽折杵向恥角 亦其遭遇有伸屈
歳久講求知処所 住者出自衡山屈
巴蜀石江強畔 理疎性軟良可咄
〔解説〕前人が初めて茶を飲んだときは葉も骨も区別せずにいっしょに煮た。ようやくその味を窮めて、臼を初めて用いた。つぎには、薬研を使った計を尽し、研究して、ついに茶磨にたどりついた。知者は物を創りだすというが、まさにその通りだ。薬研や杵臼は、垣根のそばに捨てた。しかし、そこまで来るには、いろいろな曲折があった長い年月にわたる研究の結果、どこの石が最適なのかも分ってきた。良い石は衡山窟にあった。石工は苦労して石を取るが、目が通っていて、性質は軟らかで・まことによいという。
また宋の詩人、黄山谷は抹茶が茶磨からでてくる様を、「落磑*雪不如(磑より落っること、**として、雪も如かず一一〇七九年の作)
と形容した磑とは石臼。この落ちるさまは、まさに雪がふるようだ。
雪が降るように石臼から落ちるという表現は、性能のよい茶磨を実際挽いてみると、なるほどと思う。まさに吹雪のように、あるいは、ぼたん雪のように粉末が降るのである。非常にすぐれた茶磨がつくられていたことが、この詩から想像できる。しかし中国でも、特別に地位の高い人たちの間でしか使っていなかったのであろう。それから百年後に中国に渡った栄西禅師も、手に入れることはできず、旧式の碾をi云えたのであつた。栄西の没後、前述した弁円(聖一国師)が渡宋し、その頃からぽつぽつ新安沖の宝船が示すような茶磨が貿易品として渡来したと思われる。わが国で、はじめて茶磨の文字が記録に現れるのは、鎌倉時代末期頃の高僧、虎関師練(一二七八一一三四六年)の「茶磨」と題する詩である。
曾慣点頭解転身 煉余五色一般新
天常動*地常静 天地之間常有春
(『五山文学全集』第一巻、昭和十年所収)
天は上臼、地は下臼の意で、その間から春、すなわち緑の粉が落ちるさまを禅の悟りの境地にたとえている。 同じ頃、龍泉令* は粉を挽く石臼の詩を書いている。 石臼
雲根連処又相分 動静*行自策動
別是転身那一路 炎々六月雪粉々
高僧が、粉を挽く石臼をみて感激し詩をつくるなどということは、後世の日本では考えられないことだが、当時はまさに舶来の珍品であり、宝物だったことを物語っている。このようにして、石ウスは何百年もかかって、宝物として、あるいは高度の文化として、貴人たちの間にゆっくり普及してゆく。これはヨーロッパや中国とは全くちがう日本独自の発達と普及過程であった。
4.9 夢窓国師の頃

闘茶といって、お茶を飲み比べて産地をあてるゲームは、現在でも残っている。鎌倉時代末期には上流階級の間で行われた。しかし次第にゲーム化し、度をこえたものになった。男女混浴つきの闘茶などさえあったというから、現代も顔負けである。そこで「闘茶はけしからぬ」と叱った高僧がいた。京都・建仁寺の僧、夢窓国師であった。この国師が使ったと伝えられる茶磨が、高知市小津(高知市の東南、五台山、三十一番札所、竹林寺で知られる五台山公園、この山の麓、吸江寺にあると聞いて1977年五月十八日に現地を訪ねた。まさに日本最古で、いまでも使える茶磨である。
施八龍 土左国五台山吸江庵臼也
貞和五年巳丑十一月廿五
と銘がある。日の字の分だけすり減っている。一三一八年(文保二年)鎌倉の北条高時の母覚海夫人が、夢窓国師を鎌倉に迎えようとしたとき、国師はそれを避けて、ここに庵を結んだ。そのときのものと考えられている。余談だが、このウスは、物理学者で、科学随筆家でも知られる寺田寅彦先生が使っておられた記録がある。先生は粉の学問を奨励したわが国最初の方でもあり、私たち扮体工学の草分けである。数百年を経て、なお実用に耐える道具、これこそ日本の宝と思うが、国宝ではない。この頃、茶磨は大変な貴重品だったことを示す文書が、金沢文庫古文書にある。鎌倉幕府執権十五代、金沢貞顕と称名寺長老との間に交わされた書状に、貞顕はお寺へ茶挽きを依頼し、茶の葉も、長男が京都で僧職についているコネで、かなり苦労して入手している様子がうかがわれる。「なによりも、ちやうすこそ、まづほしく候つれ」という文面がそれを物語っている。舶来品の唐茶磨は入手困難だったのである。
4.10 一休さんの頃
 一休の原画に忠実に模写(著者)
一休の原画に忠実に模写(著者)
夢窓国師から約百年を経た頃には、茶磨の国産化が進んで、権力のある人達は茶磨をつくらせるようになっていた。トンチの一休さんで親しまれている一休宗純の有名な著作『骸骨』に、上図のような絵と文がある。
私のこの絵との出会いは少々無気味であった。それより先、岡山県美作町(みまさか)の石造美術研究家、土井辰巳さんの案内で、同町に五輪塔の台に利用されている古い茶磨を見学した。夏草が生い茂る山あいに・小さなお堂が建ち、木彫の仏像が安置され、その前に二つ三つの五輪塔が草に埋れていた。戦いに敗れた武士が自刃して果てたという、うす気味わるい場所に苔むした五輪塔の塔の地を表わす石に茶磨の下臼が使われていた。この墓の主が誰か知るべくもないが、多分彼の愛用の茶磨であったろう。私は名も知らぬ武人に合掌して去った。ここは地元で幽霊が出ると言われているという。墓を動かしたのはあと味が悪いことで、気になっていたところ、2-3日あと京都の古本屋でなにげなく開いた『骸骨』の本に、ふと次の一節が目に止まった。
なきあとの かたみに石がなるならば
五りんのだいにちやうずきれかし
活字印刷本だったので、もしかして「ず」が「す」のミスプリントだったとしたら……。ずいぶん勝手な解釈だが、さっそく竜谷大学へ出かけて『骸骨』の原本を調べた。なんと予想通りミスだった。しかも一休さん独得のゆかいなイラスト入りだ。そしてつい先日、美作で見た光景そっくりなのには思わずギョッとした。石臼には霊が籠るという古来の言い伝えを思い出した。
『骸骨』には副本があって、絵も文もちがうのがある。一休宗純は反骨の人だった。「ちゃうす」を権威の象徴と見、それに「いずれの人か骸骨にあらざるべき」という一休の無常観をダブらせると、権力に追随し、茶磨を切らせることができるような身分に安住して修行を怠っている高僧たちにたいする鋭い批判である。真実に禅がわからずに仏教を売物にし、名利にしがみついているものへの痛烈な風刺がこめられ、これが『狂雲集』の思想へとつながっていることが私なりにわかったような気がした。
4.11 祇陀林は茶磨のことなり
一六〇三年、日本イエズス会によって発行された『日葡辞書』(ポルトガル語辞書邦訳は岩波『邦訳日葡辞書』一九八○年刊)に「Guidarin茶磨のことなり.ぎだりん(祇陀林)chausuに同じ、茶を挽くうす」とある。これは御所の南、一条京極に祇陀林寺があって優れた茶磨師がいたので、茶磨のことを「ぎだりん」なまって「ぎんだり」と呼んだためである。たまたま一条京極に同志社大学の施設があり、発掘調査があった。関連遺物の出土に期待したが何もなかった。
『新撰犬筑波集』(天文年間に成立した俳諧運歌の撰集)に次の俳譜がある。
土佐までもくだりこそすれ京の者
こはぎんだりのちやうすがめどの
京の者とは、前関白、従一位の公卿・一条数房を指す。応仁二年(一四六八)土佐の中村へ都落ちした。土佐の豪族、長曾我部殿は舟を出して迎えた。高級な茶磨のなかでも最高級の「ぎんだりのちやうす」とかけているところがポイントである。私も土佐くだりをやってみようと高知県中村市まで出かけてみたが、長曾我部殿のおむかえもなく、ぎんだりも見つからなかった。四万十川河口の小京都といわれるだけあって、大文字山あり、東山、鴨川、祇園と、すべて整っていた。どこかに忘れ去られたぎんだりが関白殿のありし日の夢を秘めて残っているかも。
4.12 幻の松風(しようふう)の茶唐

民間伝承を集大成した『御伽草子』に『かくれ里」という物語がある。「秋の黄昏時は空ならでも心細からぬかは。風ものすごく……」と名調子で話がはじまる。そのさきを読むと「松風という茶臼あり。河しまという挽き木あり。これ一具の宝物なり……」。
比叡山にいた大黒様の手下であった鼠が、恵比須様の宝物であった茶磨に小便をしかけ、挽き木を折ってしまった。西の宮にいた恵比須様は一戦の内に雌雄を決すべしとて軍勢十万八千余騎を四条室町に集めた。一方大黒様は、隠れ里に使いを出し、鼠の大軍一万余騎を集めて二条河原町大黒町に陣をとる。あわや京都が両軍死闘の場と化す寸前もろこしの布袋和尚がとるものもとりあえずかけつけて仲裁に入るという話の筋。
以上はあらすじだが本屋で立ち読みできる程度の短文なので、是非一読をおすすめしたい。迫力満点である。(詳細追加).さて、ここでいう松風の茶磨とは何であろうか。上等の茶磨を挽くと、松風に似たさわやかな音が出る。ふつうの石ウスはゴロゴロと無粋な音だが、さすがに茶磨は貴人の宝物にふさわしい。私の手許には不思議なことにこの「松風の茶磨」のカラー写真がある。ひと昔まえまで京都には太閤秀吉の宝物と伝えられる二組の松風の茶磨と称する宝物があったという(京都新聞一九七年三月六日号によれば、中京区東洞院四条上ル、西村長足氏所有)。それが骨董屋の手をへて芦屋方面へいったという噂があり行方知れずのところ、私はふとした機会に、岡山市内でそれに対面する幸運にめぐまれた。幻の松風の茶磨は現存していたのである。側面に松風の文字が浮彫りされ、朱漆ぬりの、まさに宝物だった。この茶磨が次の戦国時代には、普及版の茶臼が急速に日本全国へ普及する。