
|
複数の図鑑や文献で貝を調べていると、同一の貝なのに和名や学名が違うことが 少なくありません。それはなぜなのか、そしてどう判断すればよいのか?初心者ならず とも悩む問題です。 こういった問題の対処の仕方を、岡本正豊氏が東京貝類同好会機関誌「ひたちおび」 に寄稿されていたので、氏と東京貝類同好会のご好意で掲載させて頂きます。 また、一般の皆さんにも分かりやすいように、内容を一部修正してありますので、ご了 承ください。 掲載にあたって、快く了承して下さった岡本正豊氏と東京貝類同好会には、厚くお礼 申し上げます。 |
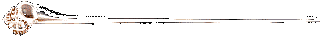
| 1. 学名は現実には世界共通の名ではない、そしてよく変わる | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
「和名は日本語による日本だけに通用する名前、学名はラテン語による世界に共通な名前」
という感覚を持っていた筆者には、全く意外なことであった。貝の学名は、図鑑・目録などでみると、
同一種が、著者や出版の時期により、別の学名で呼ばれていることが決して珍しくない。
分類の単位である「種」とか「属」とかについて、完全明確な定義づけができないため、
学者により種(あるいは属)の認識が異なり、同一種(属)とみるか別種(属)とみるかに見解の相違があるときには、
同一の貝が学者によって異なる学名で呼ばれることになる。
現実に世界中の学者がすべて意見が一致している訳ではないから、学者によって見方が異なり、
呼び名も異なるのは当たり前なのである。 また、研究が進み、より適切な学名が明らかになったとき(多くは古い学名の示す貝が、 今別の名で呼んでいる貝と同一種であると認識されるようになったとき)は、その名に改めることになるので、 同じ学者でも、従来とは違った学名を使うようになる。 以上のようなことで、従来と違う学名が用いられている記事に出会うと、初心者は 「すべての人の用いる学名がそのように改められた。最新の出版物以外の学名はすべて正しくないもの」 と思いがちだが、常に「別の見解もあり得る」ことを念頭においておかなければならない。 言いかえると、 「学名とは世界共通名として名付けられたもので、その資格を備えているが、いろいろな見解があるために、 使われ方は必ずしも世界共通にはなっていない」というのが現実である。 私たちは、多くの人に広く認められている学名を、 このような前提のあることを承知の上で仕方なく用いるしかないのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. はじめに同定を受けたものが必ずしも典型的なものではない。高名な先生でも誤りはあり得る | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
標本を先生に同定してもらうと、はじめての種では、その貝がその名の示す貝の「典型的なもの」
と思い込みがちである。事実そうである場合には問題ないが、
その人が接するその種が、特に地域的に狭い範囲のものに限られている場合などは、
いつも接するものがすべて同一の地方型であるために、ついつい井の中の蛙になってしまい、
それが変異型であることに気づかず、たまにその貝の「典型的な型」に接したときに、
「これは〇〇先生に同定してもらったこの種とは明らかに違う」などと言ってみたくなる。 また、いかに高名な先生に、その時点で最善を尽くして同定してもらったにしても、時の経過によって研究が進み、 新しい見解も生まれてくるので、同定結果が将来にわたって絶対に変更されないという保証はない。まして、 時間をかけずに同定してもらえば、誤りだって起こり得る。とくに旅先の宿を襲い、 疲れている先生を捉えて面倒な微小貝を持ち込み、うす暗い電灯の下で、 文献も比較標本もないという悪条件下で同定をしてもらうような場合は、間違いも起こりやすいし、 標本を差し上げてなければ、後日の訂正も期待できない。 それに専門家は学名中心であるから、それを和名になおして同定してもらうと、 和名に直すときに類似名との混乱、勘違いも起こることがある。 その和名を基準にして自分で学名を捜して付けたりすると、学名も和名も違ったものがついてしまう。 こんなものまで「これは〇〇先生の同定」と言ったのでは、先生に対する責任の負わせ過ぎになる。 さきに述べた地方変異にしても、同定を受けた名前を頼りに、 自分でも図鑑や文献で納得のいくよう調べてみると、 名前をつけてもらっただけよりよく覚えられるし、そこでもし疑問を感じたら、疑問点を具体的に示して、 ゆっくり教えを乞うことにすれば、より正確な知識が得られるだろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 同じ和名でも、広義と狭義がある場合がある | ||||||||||||||||||||||||||||||
和名は、基本の和名がまずあって、これと区別する必要のあるものが現れたとき、
基本名に特徴を示す語を付けて新しい和名が作られるケースが多い。例えば、
などは、基本名(以下「基名」と略す)に、修飾あるいは限定的な辞句(オオ、マル、イボ、シロ、アオ、オキナワなど)
を冠して派生名が付けられているので、当然基名のほうが古い。 ところが、上記のような形の名の場合であって、派生名の貝の学名が、 基名(狭義)の貝の学名より古いとき、つまり和名の優先順位(基名であるか派生名であるか)と、 学名の優先順位(早く発表された古い名が優先)が逆のときに、 両者が種として同一と認められるようになると、ややこしいことになる。例えば、
ウスカワマイマイとオキナワウスカワマイマイについても、 狭義のウスカワマイマイ(内地産)を呼ぶのに、 学名と結びつけてわざわざオキナワウスカワマイマイと呼んでいる人も多いが、その見解に従うと、 基名のウスカワマイマイという種は存在しないということになってしまうのである。
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 和名は今過渡期にある | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 「貝の和名だから、貝そのものを現わす和名でないものには『ガイ』を付けて、
貝の名であることをはっきり示すべきである」という見解が一般に広まり、最近発行される出版物では、
従来の和名の末尾にガイを付した和名が広く用いられるようになった。
この「ガイ付き和名」には必ずしも問題がないわけではない(ちりぼたん第8巻第4号 p.95、
かいなかま第8巻第2〜3号 p.14等に筆者が述べた)が、
ともかく現在は「従来の和名」「ガイ付きの新和名」「その修正和名」の新旧和名が併用され、
さらに一部の種にはこれに異名(完全に同物異名の場合もあるが、
別物と考えられていたものが同種と認められるようになって異名になったものが多い)が加わって、
同一種をさす和名がさらに多いものもある。 新旧和名の併用状況を具体的にみると、例えば、
種を単位として呼ぶ場合、基準とすべき正しい和名をどれにするかということは、 今すぐにはコンセンサスを得られる状況にはないので、 ここ当分は色々な和名が併用されてゆくうちに、 次第にどの和名かに固まってゆくのを待つより仕方がなさそうである。はじめて貝の道に入る方々には、 ご苦労であるが、類似の名前で別物であるものと、 別の名でも全く同一物であるものとを見分けていただかなければならない。 |
