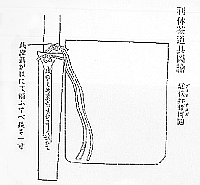 千利休の火打袋
千利休の火打袋リンク:火口は火薬への道|火の発見は粉の発見|伝統文化の風化と本物|火打ちの技学習記録http://www.d1.dion.ne.jp/~orbit_gu/arch/bookmark/fire/fire3.htm
忘れ去られた火打ちの技 (このファイル23kB) 表千家の機関誌『同門』に6回連載した文に加筆したものですこの文書25kB)(
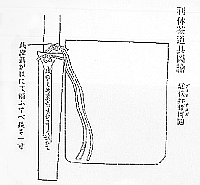 千利休の火打袋
千利休の火打袋
上図は利休茶道具図絵にあります(『古今要覧稿』の「巻二百二器財部火打袋」)。この袋 を俗にうきよ袋といい、それは火打袋であると次のように書いてあります。「うきよ袋は三角に縫いたる火打袋なり、うきよは御清の誤にて、火は物を清むるに用ゆる故、神前に物を奉るには切火を打ちかくることあり。其意をとりて御清袋とはいへるなり」。上図は四角形ですが、三角形が多いようです。
茶磨を速く回すと茶の味が落ちます。だから現在でも上等の抹茶は生産性は低くても石臼が使われています。粉が焼ける速度がこの火打ちの速度ですから、抹茶がなぜ現在でも石製の臼でなければならないかを考える上にも火打ちを知る必要があります。また茶磨山の地名を追っていると火打山もでてきます。
火打ちの実演
私は長い間ヘビースモーカーでした。ライターの代わりに燧ぶくろ袋(火打袋)を常時携行していました。

火打石、火打鎌(火打金)と火口の三点セットが入っていました。美しい伝統の燧袋から不思議な小道具を取り出して、着火準備。はじめて見る周囲の人々は何事が起こるのかとかたずをのむ。カチ、カチ。中空に咲く聖なる火花を楽しんだ次の瞬間、火口に輝く小さな火、そこへ巻たばをつけて吸う。たちまちひろがる紫煙に、一同異口同音に「おーっ、火がついた!」テレビで実演したこともありました。それを見たある修学旅行の高校生がひょっこり研究室へ訪ねてきて、アレを見たいという。手元にあった巻タバコに着火して見せたところ、おおいに感心して帰ったが、しばらくして手紙がきた。「ぼくも成功しました。うれしくて学校でトイレに入ってタバコに着火して友達を驚かせています。ただしこのことは両親と先生にはぜつたい内緒にしてください。」わるい火遊びを教えたものだと反省した。この好奇心旺盛な生徒はその後大学生を卒業し社会人になるまで文通していました。その後私は医者から禁煙をすすめられて、プッツリたばこをやめました。 今になればなぜあんなものを吸っていたのか、と後悔しています。
ただ困ったことに着火して人々を驚かす機会がなってしまい、自慢の火打ち袋の出番がなくなりました。それでも講演では演壇で紙に火を着けて司会者をあわてさせることもあります。
『古事記』に景行天皇の40年、日本武尊は東征に際し、倭姫命から草薙剣を賜わった。駿河で賊の計略にかかり四方から草に火を放たれたが、草薙剣についていた燧袋から火打石と火打金をとり出し、火を打ってこちらから草に火を放ったところ、急に風向きが変って火は賊に向かい、凶徒を打ち破ることができたとあります。私は静岡県の日本平を訪ねたとき、日本武尊の銅像があったので、像の前で火の奉納のまねをやったこともありました。銅像のミコトの顔が一瞬ほぐれたと私は感じたのですが、この話だれも信用してくれませんが、みなさんはさもあらんと思っていただけると思います。
古武士はこの故事にあやかって、旅に出るときは必ず家伝の燧袋を所持したそうです。山野で野宿したり、食事する際の発火道具に欠かせなかったが、別に諸難厄除の意もありました。江戸後期に燧の実用性がうすれた後も、旅立つ人の後から火を打って身の穢れ(けがれ)を払い、旅の安全を祈る風習が残り、今でも芸能界や花柳界では行なわれています。(最近のテレビでは火が出なくて音だけの事が多いようですが。)
なお火打金が手に入らない人たちの間では、木をこすって火を出す方法も平行して使われていました。古代にはよい燧袋、火打石、火打金を手に入れることができるのは武士や商人に限られていました。その証拠は次の聖(ひじり、火知りの意)という言葉にこめられています。
 ガチッと暗闇の静寂を破る来迎寺の一つ火
ガチッと暗闇の静寂を破る来迎寺の一つ火
時宗の本山を訪ねて
鎌倉中期に一遍上人が開いた浄土宗の一派に時宗があります。遊行念仏者一遍上人は聖(ひじり)とよばれ、「火知り」に通ずるといいます。栗田勇著『一遍上人』(新潮社、1977)によれば、時宗遊行派総本山は相模藤沢の清浄光寺とあります。この宗では年送りの行事として火打ちの行事、一つ火があり、夜に寺の戸を締め切って滅燈し、真っ暗にした中で、一発着火して燈火をともしてゆく。この時、もし一発で火が着かなければ、住職は門を追われて編笠一つを餞別にもらって下山するという。私はそれを見学させていただくよう本山と交渉したところ、「本山よりも新潟県十日町市、来迎寺のほうが情緒がありますよ。そちらへいらっしゃい」と新潟県十日町の来迎寺を紹介しいただきました。その行事は大晦日の行事というので、12月31日に大雪の中わざわざ新潟県まで行きました。全国からお坊さんが集まる盛大な行事だから、控室はお坊さんが一杯でした。
私は緊張していましたが、そのうちに2、3のお坊さんが巻たばこをとり出しました。どうするかと見つめていたら、意外も意外、ライターを出して着火するではありませんか。そこで私はやおら燧袋をとりだしました。派手な袋なので目立つのか皆さんの視線が集中しているのを意識しつつ、カチッと着火したところ、一斉に「おおーっ」と歓声があがって、「これは参った、聖(ひじり)だ」と一躍評判になりました。
私の火打ち3点セット
おかげで私はその日は聖(ひじり)扱いで行事には上座にすわらせていただいて、行事を見学させていただくことができました。お寺で上座に座るのははじめてでしたが、仏樣と目をあわせておられるのは本当に仏前にいるいい気持ちでした。夜もふけて12時が近づくとすべての戸が閉められ、真っ暗になり不思議な静寂の中、ガチッと暗闇に響く着火の音につづいて、火打箱にかすかな火が付きき、つぎに付け木(うすい板の先に硫黄をつけたもの)に火が移ると炎に変わって、それをお灯明に移すと、はじめて光明が灯る。読経が続くなか次々に光明が増えて次第に明るくなってゆく。この行事は、さすがに印象深いものでした。
参考のため「火打石や火口はどうしますか」と聞いたら、本山からもらってくるとのことでした。そこでそんなの川で拾えばというと、全員驚きの態。
なお切り火の行事は山岳修験にも伝わっています。(大和久震平「山兵山頂遺跡」『山岳修験』創刊号、(1985)
燧石はその昔秘密の場所だった
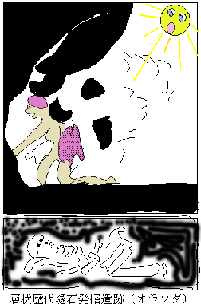 落盤で人知れず埋まった人骨が何層も見つかったという
落盤で人知れず埋まった人骨が何層も見つかったという
「鉄の発明以前には火打石と黄鉄鉱がはやくから使用されていました。ヨークシャーのラドストーンの新石器時代の塚から出土した火打ち石と黄鉄鉱のセットが発見されて、また、デンマークでは人骨とともに火打石を掘った鉱山跡も発見されたといいます。いかに長い間この鉱山があったかは、何層もの骸骨が見つかったといいます。掘り出す鶴嘴(つるはし)は鹿の角でした。納富重雄著『火』(1927、三省堂)。
「フリント(燧石)は道具や武器にもっともよい材料であることがわかった。火打ち石や黒耀石はどこでも見出せるというものではなく、それらの発見や試験には、時間がかかったからである。原始人はしばしばそれらをかなり遠くから運んだ。」(ルイス・マンフォード著、樋口清訳『機械の神話』河出書房新社、1971)またチャールズ・シンガー著、平田寛訳『技術の歴史』(筑摩書房、1978)には、火打ちがアメリカインディアンのある部族内に伝わっていた。
エスキモー、南アメリカのフエゴ島民、イギリスでもマッチ出現前(一八二七)まではときおりおこなわれていたとあります。握斧をもった旧人(ネアンデタール人)がいた頃は、氷河時代であった。この頃すでに火の発見があったかも知れないといわれている。数十万年前の北京原人が火を使っていた形跡が確認されているが、どのようにして手に入れたか、発火法を知っていたのか、それとも自然の火を利用したのかは、全くわかっていない。しかし、それを遡る百万年をこえる石器加工の仕事のなかで、人工的な発火法を発見した可能性は十分考えられます。石器の加工中に、石と石とがぶつかり合って、火花を発する現象は当然興味をひく現象であり、これは現在でも子供たちが幾度も試みることからも想像がつく。人類文明の曙でした。しかし、石と石の衝突で発する火花の実体は、急激な衝突の際の摩擦熱によって赤熱された石の粉であるから、スーッと消えるかすかな火にすぎない。ところが、石の組み合わせが、フリントなど石英質の石と、黄鉄鉱や赤鉄鉱のような鉄鉱石との場合には、火花の出方が全く違っている。鉄の粉の急激な酸化による発火、つまり燃焼である。石英質の均質な石の砕片の鋭い角に、長三角形状の焼を入れた鉄片(火打鎌)を強く打ちつけると美しい火花が散る。飛んだ火は、ときに線香花火のように、小さな爆発を起こす。そしてもしもそこに燃えやすい乾いた草の穂のようなものがあれば火が燃え移って炎を生ずる可能性は十分ある。石器の加工技術の延長線上で、発火法が偶然発見されても不思議ではない。木と木をこすり合わせて火を起こす方法と、ど熱石英質の均質な石の砕片の鋭い長三角形状の焼きをいれた鉄片(火打鎌)飛んだときに線香花火のように、小さな爆発を現在の線香花火の火花も鉄粉である。
そこに燃えやすい乾いた草の穂火が燃え移って、炎を石器の加工技術線上で発火法が偶然発明されても不思議ではない。木と木をこすり会わせて火を起す方法とどちらの発明が先なのかは不明ですが、木と木をこすり合わせていると、木が十分乾燥した粉つまり火口が自然に生成されるわけです。でも実際にやって見ても自然にできた粉にはなかなか火がつかないので、それには長い試行錯誤があったことでしょう。
やじりなど石器の素材として広く利用されたフリントやチャートなどがそのまま火打石になります。鉱物学的には同質の石であっても、産地によって道具の性能は全く違います。加工しやすくて、鋭い刃が得られて、しかも適度の強度があり、もろくない素材は、産地が著しく限られています。この石は、火打石として、ごく最近まで産地がひきつがれてきたもので、人類にとって最もつき合いの長い大切な素材のひとつでした。これが現在はレンガや砕石の原料になっているのは少々淋しい気がします。
ちなみに現代の最先端を行くLSIや超LSIの基板に使われる「シリコン」の語原は火打石を意味するラテン語の「シリクレス」です。人類とシリコンの何万年ものつきあいが現代につづいているわけです。
火打石
性能のよい火打石は貴重品でした。京都の鞍馬には、畚(ふご)おろしという地名が残っています。づくし「鞍馬寺名所盡(ずくし)」にはそのさまが描かれています。京福電鉄の貴船から鞍馬へぬけるトンネルの上です。寛文年間のこと、ここに武家くずれの浪人が住みつき、川をへだてた小山に小屋掛けして、畚(ふご、藁製のかご)を下ろす索道をつくり、鞍馬の参詣人に火打石を売っていたそうです。


『薙州府志』に「鞍馬山の産は発火性がよいので、鞍馬松尾東山腹に一堂を構え、一人その内におり、長縄にわらふごをつけ、往来する人あらば、そのふごを往来の路頭におろし、燧石を求めるものあらば、その志の多少に随ってふご内に銭をいれ、ふごをあげ、その銭の多少に応じて燧石をいれ之をおろす。これを鞍馬のふごおろしという」加茂川の上流が鞍馬だから、当然川原でも拾えます。(私も いくつか拾いました。)
こんな話も残っています。「寛永年中に、都の北紫野の西に紫竹という所あり。このかたわらにむしろを敷きて、二人の男すみけり。駒千代、熊千代とぞいいける。火打石を毎日、加茂川原にて拾い、京へもち出でて、、五銭十銭も売り、安居院(あごいん)というところの酒屋に待ち合せ、酒を買うて、打ち飲みて、歌うたい、物語して云云」。これこそのどかな時代の優雅な人生を送ったひとたちですね。私の研究室にいた学生が畚おろしの現地調査をしていたら、その場所の所有者が現れて連行されそうになったので、訳を話したら「儂はそんなこと初耳だ。おもしろい。もっと話しを聞かせろ」と彼の自宅に招かれごちそうになったそうです。これは現代の優雅な小話です。
ふごおろしは江戸時代まで火打石産地として受け継がれてきた場所ですが、斧の形をした自然の割れ目があります。まるで石斧の展示場を見る感じです。そのまま手に持てば、猿人たちのように野獣との格闘にも使えそうだし、細い木なら切断もできることを確かめました。また小さく割れば、果物ナイフに使えるし、特別に鋭い破片はヒゲそりもできました。他の石では到底こういう使い方はできない。はじめてこんな石を発見した石器時代人たちのおしゃれ道具でした。それを秘密にし、それを確保するための戦いもあったことでしょう。火打石は道端で少し気をつければ拾うことができます。ただし、よく火の出る石を選ぶことが肝心で、これにかなり試行を重ねました。私も江戸時代の優雅な庶民の生活にあやかって、京都の加茂川で火打石を拾い、火打金は刀鍛冶に打ってもらって、古老の指導で火を打つ技術をマスターしました。
石の割り方にもこつがあるし、火口の作りかたにも秘伝があるが、いまでは一発で巻タバコに火がつくまでになりました。そのために 大きな石全部割ってしまいました。
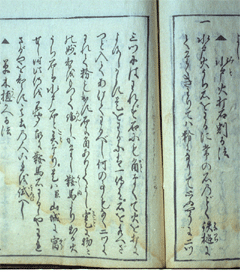 『百工秘術』
『百工秘術』
火打石を割るには工夫が必要です。三条の古本屋で偶然見つけた古本、享保九年刊『百工秘術』には次のように書いています。
「水戸の火うち石をわるに常の石のごとく鉄槌にてたたきわりては粉になりて、とぶように二つ三つには割れず、石にも角なくて火を打つによからず。これを割るには一伝あり。石を水へざっと入れて、あげて割るべし。何のこともなく二つに割れて粉も出ず。石に角ありてよし。まことに物々の妙、かぎりなく論じがたし。」この話は江戸で広く流通あしていた水戸の石は固かったためであろう。養老と鞍馬の石は青いチャートで割り易いが、石を火で少し加熱してから水に入れるとうまく割れます。
火打金
火打金は火打鎌ともいいます。
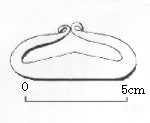 火打金富士山形の火打鎌(北方騎馬民族に使われていた)
火打金富士山形の火打鎌(北方騎馬民族に使われていた)火打鎌売り(『浮世めいたい記』享保年間)
その歴史については高嶋幸男著『火の道具』(柏書房、1985)に詳しく、長野県山ノ内町、金箱正美氏(日本のあかり博物館長)のコレクションの他、考古学者の各地の出土品がたくさん紹介してあります。古墳時代のものは岡山県真庭郡落合町の戸坂1号墳(古墳)からの出土であると書かれています。最近も古墳から出土しました。興味深いことにそれは上 図に示した富士山形であることです。なぜ富士山なのか。私は『古事記』の日本武尊のはなしに因むのかと思っていましたところ、過年、奈良で開催されたシルクロード博で、北方騎馬民族の持ちものにまったく同じものがあったのです。となると日本人起源説に関連することかも知れません。また中国・敦煌の骨董屋でも同じ形態でした。
実用には形にとらわれなければ、鑢や金鋸などの古いのを使えばよいし、現代では使えなくなったカッターの刃が最高です。刃の幅が10mmのものが使いやすいようです。私は見本を示して四国の刀鍛冶に作ってもらいました。
火口
火口はなにか柔らかい髄をもつ植物の茎などがよく使われる。私は蓬の葉を乾燥させてから、石臼で挽き、粉を風で吹き飛ばしてから、ふるいにかけて艾(もぐさ)をつくりました。中国の敦煌の骨董屋で火打ち道具を手に入れました。それには火口入れがついていました。その底にわずかの火口が残っていました。顕微鏡で見ると間違いなくもぐさでした。
乾燥した蓬の葉を粉にするのに高速回転のミキサーを使って見ましたが、それでは繊維分が粉々に切断されます。そこで私のお得意の石臼を使ったらうまくできました。現在でも艾製造工場では現在も石臼を使っています。それを焼いたものがよく火がつきます。
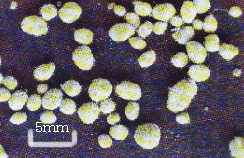 私が蓬から作った艾です。葉肉部分は微粉になるので風選で簡単にふるいで分離できます。
私が蓬から作った艾です。葉肉部分は微粉になるので風選で簡単にふるいで分離できます。
一休の名著『骸骨』にはおもしろい記述があります。「たとえば人の父母は火打ちのごとし。かねは父、石は母、火は子なり」とすれば火口は褥(しとね)でしょうか。
また『本朝食鑑』には「保久知者、厚紙を用い、これを揉んで綿の如くにし、二、三層ごとに細かく刻んで、小炭一個を畳み、軽く乾いた灰を覆って焼く。真っ黒になったら、冷やしてから出して使う」とあります。何でも細い植物繊維なら使えます。昔から火口は蒲の穂や薄の穂、黍(きび)、麻、いちびなどの茎、もぐさ、きのこ、朽ちた木片などを蒸焼きにし、多孔質の消炭にしたものです。よく火がつく火口をつくるには、いろいろ工夫を要します。
昔は硝酸カリウム(煙硝)を加えました。しかしその添加量はほんの僅かでいいので、100ccの水に1mm角より小さい結晶を溶かした水溶液に浸して乾燥します。これにより少し固化して飛散しなくなります。あまり濃すぎると手元で爆発して危険です。
艾の焼き方
現代なら使い古したアルミ箔に包んで蒸し焼きにするのが最高です。火がつきやすくても、飛散性があってはあたりを汚してしまいます。あるとき京都ホテルで実演して、白いテーブルクロスを汚して困りました。江戸中期には江戸の吉井火口や熊野火口が有名だったが、商品化の過程で着色料を使ったといいます。昔も今も商品となると悪知恵がいるようです。火口を左手の栂指の腹で石に押しつけ、このすぐ上で火を打つと直ちに着火します。火花は鋼が燧石の角で高速度(秒速約5メートル)で削られ、その研削熱により隕石のように燃えながら落下する。一発で着火できるまでにはかなりの熟練がいります。ぼけているときは絶対に着火しません。
精神を統一した火打ちの一瞬には、人間回復のよろこびがあります。ワンタッチライターのように技を一切要しない道具ばかり使っていると人間の手先は退化し脳にも影響するかも知れないですね。ひと昔まえまではプラットホームなどで「ちよっと火を貸してくれませんか」といえば見知らぬひとが気前よく吸いかけのたばこを差し出うさんしてくれました。いまどきは胡散臭い目つきをされそうな雰囲気です。昔は、この火を借りる風習がありました。これで見知らぬ人々との交流も生まれました。
 火を借りる
火を借りる
キセル煙管ではお互いに雁首の火皿をくっつけあった。江戸小咄にこんなのがあります。お殿さまのぜいたくが目にあまるので、ある日、家老がお殿さまを野良へ誘い出し、百姓たちの辛苦の様を見せることにした。つぶさに視察して感慨ぶかげなお殿さまのいうことに、「わしも今日はたいへん勉強になった。なかでも百姓が一服のたばこを二人で喫うほど貧しいとは、夢にもしらなんだ。今日からわしも改心するぞ」。
火を借りるのも、たばこの楽しみの重要な一環でした。「たばこは恋の媒(なかだち)」とも言われました。
十返舎一九の『東海道中膝栗毛』の一節「あとになりさきになり行く比丘尼(びくに,尼僧)は、まだとしも22、3、今ひとりは年増。中にもわかい比丘尼が北八のそばへよって「モシあなた、火おざりませぬか」「アイアイ今打ってあげやせう」と、すり火うち(火打ち道具)を出してカチカチ。「さあおあがり。ときにおまえがたアどけへいきなさる」
これがきっかけで弥次さん北八さん楽しい旅をする。ところが火打坂(現豊橋市内)をすぎ、二軒茶屋へきたところで比丘尼連は脇道にそれ「じゃあーねえ」ふてくされて旅をつづけるうち、吉田に着く。
旅人をまねく薄(すすき)のほくちかと
ここもよし田の宿のよねたち
吉田名物は火口とよね(遊女)。薄の穂と「ほくち」がかかり、俗謡の「吉田通れば二階からまねく」風にそよぐ薄に表わされています。また薄は火口の原料。火打石で火をつけるときの助燃材である火口と「よね」の連想について考えるのも楽しいものです。
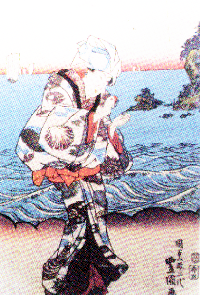 浮世絵にある花魁の火打ち
浮世絵にある花魁の火打ち
火口についての文書を2、3紹介します。享保、文化年間、江戸日本橋金吹町の裏長屋に住み、大屋裏住と称した白子屋孫左衛門の狂歌。
此の家は たとえのふしの 火うち箱
かまちでうって 目から火が出る
まえがきに「家のかまちにてかしらをうちて」とある。彼の生活ぶりがうかがわれて面白い。
吉井ほくち売り
「いちびの幹などを消炭にしたもの。いちびの茎の皮をはいだものを焼いてつくる。
ほくちに二種あり。一はほくち殻という。灌木の殻を焼きて消炭の如きものを入れたほくち箱。二は厚紙をもみやわらげたもの。綿ぼくち(吉井ぼくちともいう)袋につめ、黒い綿のごときもの(現在東京の上野の夜店で売っているのはこれ)。
「守貞漫稿』
「火口ほくちと訓ず。蒲穂を以て之を製す。黒赤二種あり。三都とも燧嚢には之を用う。京坂日用にも之を用う。江戸常には火口木と云草幹を焼き、炭として之を用う。日用にも之を用う家あり」。
火口は火のつきやすい消炭の粉で、古くは朽ち木や柔らかい木やきのこなどを蒸し焼きにしてつくった。沼地に自生する多年生草本で夏に蝋燭状の茶褐色の穂をつける蒲の穂の炭も用いいちぴられた。また麻、黄麻、黍などの茎の皮をむき、その中身を消炭にしてもよい。江戸時代には蒲の穂、つばな、ぱんやの消炭に焔硝(硝酸カリウム)を少々加えた熊野火口などのほか、赤や黒に色付けした商品もあったようです。
燧石(ひうちいし)
珪酸質の硬い石で、何億年もの昔、海中の放散虫の遺骸が堆積したもので化石です。地名から古代の火打ち石の産地を探険するグループがあります。岐阜県大垣市青墓町の堤正樹氏のグループは、岐阜県養老町唐谷(空谷)でチャートの燧石産地を発見。また火打ち石の産地は石器時代の石器の材料でもあり、石器生産地の研究にもつながっていますが、まだ研究は進んでいません。考古学者も記録するようになり、名古屋市見晴台考古資料館の水野裕之氏の報告:「名古屋市中区栄一丁目竪三蔵通遺跡調査概要1991年」や関東では「川口市遺跡調査会報告第三集(東・上ノ台・道合久保前)1989年」などに江戸時代遺跡からの使われた火打石の詳細な報告がでています。
また茨城県山方郡山方町文化財保存研究会編『山方町誌』(1976)には「火打石は久慈郡諸沢村、那か郡下小瀬村、那か村より出す。燧石なり。世に水戸火打という。諸沢に火打山あり。上ること一里半ばかり。高山を峰の方より次第に切採りて山下に至る。石切の者鉄槌を以て砕き品の上下を選ぶ。商品税を出して之をとる。殊によろしき年は五百両余の金を出すと云ふ。」とある。ここは現在も採掘していて、上野のあたりで市販されています。灰白色半透明の美しい緻密な石で割るのに工夫がいります。これが前述の火打ち石の割りかたにある石です。
『新編常陸国誌』には「諸沢の奥、大久保(上山へ上り口の所)に火打山あり。火打石を発掘していた。ここに燧石山会所があって、中島藤衛門の家が会所守を勤め、採掘に尽力した。諸沢、北富田の農民は火打山の工事や採掘の労役に当てられることが多かった。採掘した燧石は西野内の渡場近くにあった火打石倉に運び、さらに水戸、江戸方面に運搬して販売された。」とあり、このほか上納例や大阪でも売ったことなどが書いてあります。火打金の商売もありました。火打鎌売りに関して、朝倉無声の『図絵江戸行商百姿』に「火打ち、火口を商う者は、江戸では升屋、京都では吉久、大阪では明珍。この三者の独占になっていた。Lとあります。
また『絵本江戸風俗往来』には「江戸の升屋は芝神明に本舗を構え、江戸一円に売子が行商した。甲首がマーク。その後ほぼ天保年間に上州の吉井火打鎌が江戸の市場に進出し、その後江戸を独占した。」とあります。
火打ちは鉄の文化とともに古い発火法ですが、他の発火法と共存して伝えられ、マッチが普及した後も残ったのは興味深いことです。その理由は携帯しやすい簡単な道具で、直ちに火が得られ、野良仕事や山仕事のさい雨や汗で濡れても、火口さえ乾いてあればよいのは、他に代え難い利点でした。
とくに煙草用にマッチは硫黄くさくて嫌われました。「タバコは動くアクセサリー」とはずっと前の専売公社のCMでしたが、吸うしぐさとならんで、火をつけるまでのしぐさにもかなりのウエイトがかかっています。ライターの快い発火音と美しい火、その点では火打ちは抜群。火花は自由奔放そのもので、電子ライターのようにみみっちくない。また危険な火花は出ないから、子供がいたずらする心配は皆無。特にこどもは石拾いが好きですから、ついでに鉱物学や火の歴史とを人類学を教える機会もできます。不況対策会議が
長引いて疲れ切ったとき、家伝の燧袋を取り出し,カチンカチンとやったら、会議場の視線は一瞬集中、三発目成功、満場の拍手、会議場のストレスは忽ちに解消し、難しい議題もすらすら進むこと請け合い。気難しい初対面でも話がはずみ商談は成功間違いなしです。大林太良著『日本古代文化の探求』(社会思想社、昭和四九)に次のように書かれています。
目の前で燃える火を見る機会は非常に稀になりつつあります。ことに都会では、人が日常目にする火は、コンロやライターなどの、これ以上は制御不可能なほどに小さく制御された、機械的で無表情な火だ。……火の荒々しさに触れ、炎のゆらめく魅力に見入るといった、火との情的な接触の機会はなくなった。火と人間との有史以前からの密接な関係がここ一世代か二世代の間に激変したが、もしかするとこれは、人間の情意に微妙な変化をもたらすかも知れないことを、前記の著者は鋭く指摘しています。松明(たいまつ)、どんど焼き、松明、花火、そして火打ちの火花、この自由奔放な火の表情を見入ることによって、私達は祖先のたくましい人間性を呼びもどすのかもしれません。最近エコロジーの専門家に見せたら、おおいに感激して「それは21世紀をリードする生活ですね」といいました。いずれ鞍馬に私の店をだそうと暖簾も用意しています。
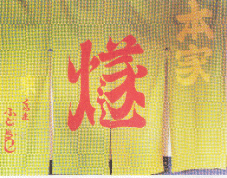 私が準備した暖簾(のれん)
私が準備した暖簾(のれん)