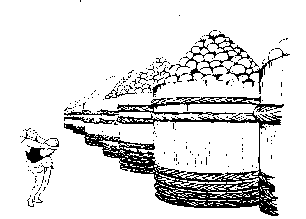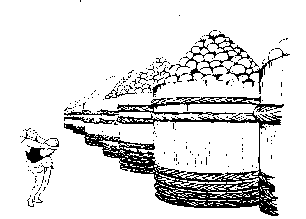
リンク:おせっかいとは?
八丁味噌 (ここにも遺伝子操作の影響が懸念される)
味噌に関する日本最古の記録のひとつ東大寺古文書,尾張国正税帳に「天平2年,尾張国から未醤弐斗壱升を朝廷に納めた」とある。『味噌沿革史』(川村渉編,全国味噌工業協会刊,昭和33)に詳しい考証がある。「味噌の字が現れたのは平安時代のことで,奈良時代には「未醤」と書くことが多かった。 夏季は高温多湿で腐敗しやすい尾張,三河地方の気候風土は,大豆だけを原料とし,米や麦の麹を用いない味噌を発達させ,その伝統は三州味噌,三河味噌の系統をひく八丁味噌につながっている。「手前味噌」の言葉が示すように,味噌は地方性が濃く,よその味噌にはなかなか馴染みにくいものである。八丁味噌も,そのくせの強い香と味のために,愛知,岐阜,三重の三県を除いてはあまり一般化せず,他の地方では高級料亭や味噌通の間で愛用されるにとどまっている。 天皇家は,もと京育ちだから京の白味噌を連想しがちだが,意外にも八丁好みだという(雑誌『ウーマン』 (昭和54年1月号「皇室御用達の品々)。その納入元,岡崎市八帖町(古地名八丁)の八丁味噌カクキュー合資会社(旧名早川久左衛門商店)を訪ねて確認した。この店は創業が中世まで遡る老舗で、明治25年以降「宮内省御用達」の木札をかかげる八丁の本家で現在も年間3、4樽を皇室へ納めているという。振動篩機、ソーティングテーブル(異物選別機)などを使う大豆の精選から,水洗,浸漬,蒸煮,玉握りまでの工程は,いずれも粉体処理機械で近代化され、原料大豆の90%以上が風味に欠ける輸入大豆になっているなど,昔の趣はないが,建物や熟成のための樽を並べた倉庫は古い伝統をそっくり残していた。 玉握りは味噌玉をつくる工程で,昔は蒸した大豆を臼に入れ杵で搗いたものである。豆の臭いが鼻をつく,その厳しい労働の経験は筆者もあるが,現在は混練機から直ちに味噌玉が出る連続作業になっていた。出てきた味噌玉は摂氏35度の恒温麹室に四日間入れて嫌気性菌による醗酵が行われる。これを荒砕きしてから,水と食塩を加え,30石人りの大きな樽に入れるのだが、これから先は江戸時代そのままなのがうれしい。現在使用中の大部分の樽は,慶応年間から昭和初年のもので,吉野杉に見事な竹の組みたが嵌った文化財級のしろもの。約6トンの味噌を入れ、その上に人頭人ほどの丸い石を約3トン積みあげて重しにし,2夏以上、約三年間熟成する。蔵には約600本の樽がある。
信長も秀吉も家康も三河,尾張の地で育ち,豆味噌のエネルギー源で天下をとるスタミナを養った。筆者には天下をとる必要などないが,中京育ち故に,八丁味噌なしでは日が経たない。信州味噌の本場に住んでいた頃も,今、白味噌の京都でも,八丁の粒味噌を樽から出して秤り売りしてくれる店を探しあてて,八丁を切らさないようにしている。粒味噌で味噌汁をつくるときは,必ず摺鉢を使う。はじめは水を入れずに,つつきながらよく摺る。次に少しずつ水を加えながらのばしてゆくのがこつ。こうすれば味噌滓は全く出ないから,味噌漉しは不要。へたに味噌漉しをつかうと味が変る。白いカビのようなものが浮くが、これを「ささみ」とか「ざみ」といい,これは僅かに渋味を呈して,八丁の味の秘密を握るひとつの重要成分だ。その主成分は,チーズの中に発見され,チロシンと名づけられた蛋白質構成アミノ酸のひとつである。網や布で漉すと,吸着により失われやすい。粒味噌を固めて庖丁で刻み、布で包んで,おつゆのなかでゆり出したのを「赤だし」という。高級料亭向きのぜいたくな食べ方だが,八丁独特の「くせ」がぬけるので一般向きする。パックされた「赤出し八丁」は,ずばら族向きだから,熱処理により死んだ味噌で,ぐっと味がおちる。ずぼら族向けには豆味噌を潰した漉し味噌もある。すりこぎ摺小木も,せっかいも使いこなせぬ物臭じゃ天下はとれない。
アサヒグラフ記事1979.10.19.号。より(増補)