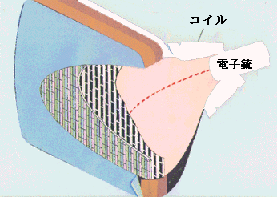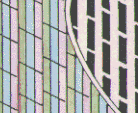テレビも粉の塊だ
古いテレビが大型ゴミに出たら、すぐ捨てないでバラして見るのも楽しい。10年前と比べて進歩のあとを考えてみるのもいい。粉屋の目には箱や基板の材質まで気になる。
30年ぐらい前の基板のベークライトには、石臼で挽いた木粉(セルロシン)が使われていた。(拙著『石臼の謎』(クオリ刊)1975)。こんなのがあったら産業考古学の記念品になる。
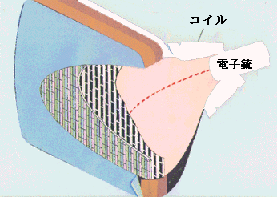
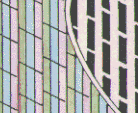
ブラウン管の内面と外面には導電膜として黒鉛微粉末が塗ってある。この微粉をつくるのにも多くの研究の集積があった。ふつうの粉砕法(ポールミル)では粉砕動力を莫大に消費する。これは黒鉛が層状構造のためにすべるのである。ひとつの解決策は水素気流中で粉砕することであった。粉砕能力は八倍にも達し。粉末の性能も格段に改善された灯現在では粉砕機にも粉砕方法にもさらに進んだ方法が採用されている。1970年頃の製品からテレビの画面が鮮明になった。それまでは外の光線が螢光面で反射して見にくかったが、これを防止するため、螢光面に黒鉛の導電膜と、螢光体を塗った螢光膜とを交互に排列させたプラックマトリックスが登場した。それにより前面のガラスもグレーから透明ガラスに変わり、コントラストはぐっとよくなた。
螢光膜は約10ミクロンの粒子が2層ぐらいに充填した薄い粉の膜である。これはピンホールのない均一な膜でなけれぱいけないから、非常に精巧な塗装の技術が要求される。まず第1に、ままっ子がないように均一に分散させるが、初期にはこれにボールミルがつかわれていた。ところが粉砕の機械的作用が粒子を構成する結晶をいため、格子不整などの構造欠陥を生ずるメカノケミカル現象が発見され、その後はミルをつかわない分散法に変わった。これも画面の輝度向上に著しく貢献した。
ところでテレビの螢光体はく母体結晶、つまりべースになる結晶の中に、数十ppmから数バーセント入っている不純物イオン(付活イオン)が発光の中心になる。3つの電子銃から出力20キロボルトの高速電子線が、青、緑、赤それぞれの螢光体に当って発光する。ごく微量(ppmオーダー)の不純物によって発光特性が変化するのであるから、その製造工程には高度の技術が駆使されている。
青の螢光体(ZnS:Ag,Cl)は硫化亜鉛を母体とし、銀と塩素が入る。緑(ZnS:Cu,Au,Al)は同じく硫化亜鉛を母体とし、銅、金、アルミ、赤は酸化イットリウムに稀土類元素のユーロピウムを数パ1セント入れる。この稀土類螢光体は1968年頃開発されたものでヘ酸化イットリウムと酸化ユーロピウムとを硝酸に溶かし10%のシュウ酸水溶液を加えてシュウ酸塩共沈物をつくるが、このときの温度と濃度を最適値にコントロールすることが粒揃いの粉末をつくるポイントである。りこれを1200度Cで焼成すると、螢光体粉末になる。画面の明るさ向上には次次と微妙な製造上の改良が加えられていて、粉末製造技術面から興味深いものが多い。たとえば蛍光体が五ミクロンだったのを10〜8ミクロンの大粒子にするとか、螢光体表面にヘ赤にはベンガラ、青にはコバルトプルーなど着色顔料の徴粒子を付着させ、螢光以外の余分な光を吸収する(顔料付着螢光体)など、次々に新技術が登場している。こうして粉の履歴書は次々に書き換えられてゆく。
戻る