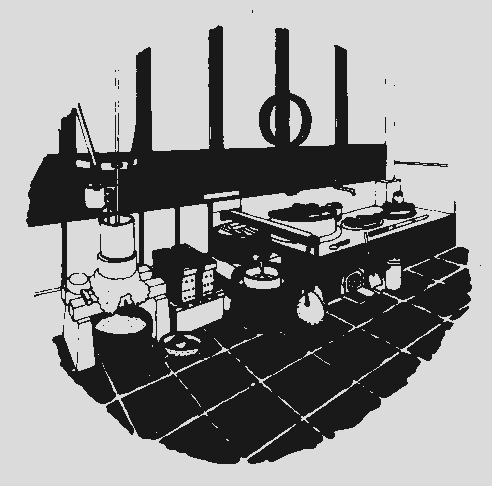
シュルトレフ著"The Book of TOFU"(1975)の表紙
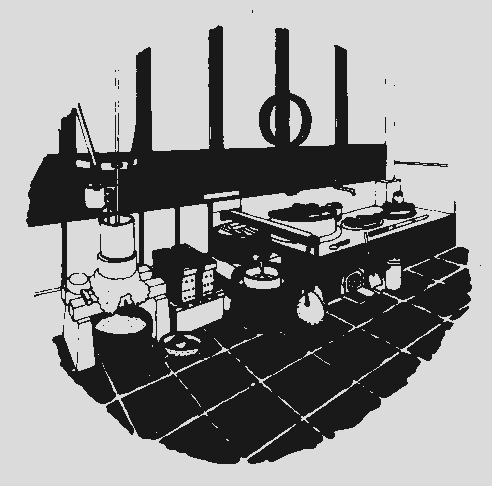
日本の昔の食べ物が、アメリカでブームになったものに豆腐がある。今も”tofu”で検索すると何と20000件を越える情報がでるのには驚いた。バイブルはシュルトレフの著書だ。
豆腐は、一晩水に浸した大豆をざるにあげて水をきり、やわらかい大豆に水を加えながら、水挽きするところからはじまる。これを湿式粉砕といい、やはり”粉づくり”の手法である。適量の水を加えながら挽くと、下臼の周囲には白い挽き汁(呉汁)がしたたりおちる。加える水の量は呉のたれ具合で調節する。できた呉を約三十分煮ると、豆の青臭みがとれて、大豆の蛋白質、油分、糖類、ミネラルなどが溶出する。汁を袋で漉し、袋の口を固くしばって完全にしぼり出す。このろ液が豆乳である。このしぼる所作を江戸川柳はおもしろおかしく表現している。
生捕った ように豆腐屋 しぼる也
袋に残ったのが、おからである。かん入り豆乳風飲料が、ひとときスタンドで売られていたが、その味のまずさでまもなく絶えた。すりばちで豆をつぶして、自家製造したらいい。少しぜいたくして軽くしぼれば、豆乳ができおからもおいしい。
かって豆腐は、家庭でつくるハレの食べ物で、正月やお盆などに自家製造した。石ウスのたいせつな用途のひとつだった。いろんな豆腐があったと思われるが、いま沖縄に残っている豆腐はその原型をとどめているのかも知れない。にがりを入れてから、固めずにモヤモヤに浮いたまの汁である。京都には、今も石臼で豆を挽く豆腐屋さんが、まだ残っている。豆腐ウス独特の目立て師もいる。あるとき店舗を改装したお店があった。「とうとう時代の波におされたのですか」と聞くと「そやおまへん、まあ見とくれやしゃ」。サニタリー化、オートメ化といたれりつくせりで、呉はパイプラインで輸送され、ヒーターの温度も浸出時間もプログラム制御である。だが、石臼の工程と、にがりを添加して凝固させるところだけは、設備こそ新鋭だが、もとのままだった。「今の機械のグラインダーに替えたんですが、お得意さんから”豆腐の質が落ちた”と不評でした。やっばりあきまへんわ」とのこと。グラインダーというのはセラミックス製のディスクが高速回転する。直径が小さく、回転速度が速い。円周部分の速度は伝統的な石臼の十倍程度である。能率は格段によいが、高速のため、微粒子の微妙な組織をずたずたに切断する。鈍刀でも素早く振れば糸が切れるのと同じ理屈である。グラインダーの組織が粗くて、ここがバクテリアの巣になるおそれもある。最近、ニューセラミックスのグラインダーが超高速回転し、豆の皮も微粉にして収率を高める機械も出現しているが、こういうのはハイテクではない。
呉に、にがりを加えてかためる凝固剤も変化した。昔は塩から出たにがり(苦汁)を使った。家庭では塩をかます入りで買い、潮解して出る汁を受けて集めた。これは塩化マグネシウムを主成分としているので、昭和十年代にマグネシウムは戦略物資として使用が禁止された。代用として硫酸カルシウム(石膏)が奨励された。カルシウムは健康食という俗説を高名な化学者がとなえたこともある。カルシウムを摂取すれば、ビタミンも同時に消費されることは、わかっていなかったのである。硫酸カルシウムは凝固時間が長く、作業性がよいので普及し、当時は健民豆腐とよばれた。現在では、グルコン(グルコノデルタラクトン)という有機化合物がつかわれている。ネオニガリともよばれる。これは熟練を要せず、低温で操作でき、水を抱き込むので収率も高い。伝統の豆腐の味が完全に消えた一つの原因である。箸でつまめない充填豆腐は工場での大量生産に適し、保存性も著しくいい。京都の店に200キロもはなれた地方で生産された豆腐が販売される。一方、しぼり糟すなわち、おからは、しぼりとれるだけしぽるから、味がだめになった。そのおからは牛も食わないから廃棄物になる。国産の大豆がほとんどなくなった(自給率は四パーセント以下)ことも味が落ちた原因である。豆腐に関するかぎり、退化がますます進んでいる。アメリカから技術を逆輸入することになりかねない。