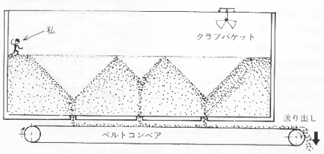
リンク:
私はなぜ石臼にとりついたのか?(2)
資本論に出ていた石臼
私が石臼に本気でとりくみはじめたきっかけは、いままで語らなかったが、それは昭和24年に入学した名古屋大学時代にさかのぼる。サークル活動で当時星野芳郎の技術論の理解に関係して資本論を調べる必要が出てきた。資本論で工学部でもが理解できそうなのは「相対的剰余価値の部分らしいということで、そこの部分の勉強をすることになった。問題になったのは下記の部分だった。
マルクスの『資本論」の和訳(長谷部訳)に「すべての機械の原基的形態はローマ帝国伝来のワッサーミューレ(水車)である。」とあった。水車はWassermuhle(ワッサーミューレ)の訳だ。ミューレとはなんだ。そこで独逸語の原文に当たる必要が出た。原文は前後関係から察すると工場の意味になる。日本訳の水車では読者は水墨画の水車を想起する。この辺りまで調べてマルクス学者なんていいかげんなものだ。いずれ調べてやろうと思ったまま大学を卒業し、つづいて会社に就職したのでマルクスなどというのはヤバくてそのまま忘れていた。
大学の卒業論文では物理化学の森田徳義先生を選ぶつもりだった。これは勤労動員で日本合成化学工業の研究室にいたころ、当時の課長が君は猫も杓子も行くような有機ではなく物理化学へ行けと言っていたためであった。「森田研に入るとロシア語の文献を読まされる。」という噂があったので、大学一年生のころから名古屋市内にあった初級ロシア語講座に参加した。講師はロシア駐在の大使館武官だったという陸軍中将だった。スターリンと話したことがあるという。だから、文法にうるさかった。グレーボフの『ロシア語文法』を読めといわれた。それを古本屋で購入した。「英語は算術だが、ロシア語は代数だ。きちんと文法を習えば間違いない」と。(おかげで昭和電工塩尻工場時代にはロシア語の講座を自分で開くことが出来た。) 研究室に入ると教授は「私のロシア語は独学です。君は本式にならっているのなら、ここで勉強会をやりなさい」といわれた。 しかし先生には資本論をロシア語で読むつもりであることは話さなかった。先生は「君は会社で勤まる人間じゃない」と大学院に行くよう勧められた。
就職活動の季節になると、同輩達が会社へ行ってうまいものをご馳走になった話を自慢げに話すので、受験遊びにと四社ほど推薦状を教授に頼んだ。その一つに昭和電工があった。当時昭電事件で有名だったので面白そうだと受けてみることにした。会社の将来や給料などは考えても見なかった。第一次試験では当時の日比谷高校の幾つかの大教室に一杯の受験者がいた。とても受かる筈はないと思っていたが、第二次試験に出るころには小教室一杯分の受験者が残った。結果は合格。教授に「どうしましょうか」と相談したら、「決まったものは行きなさい」だった。昭和27年3月だった。
昭和電工入社
昭和電工〔株)に入社し、勤務先の希望を聞かれたので、塩尻工場というと、「皆、京浜地区というのに君は変わっているな。なぜだ?と問われるので、「登山したいから」と答えると「呑気なやつだ」と言われた。この単純な動機が私のその後の運命すべてを決定することになった。
工場では直ちにカーパイド課に配置された。現場に掲示された名簿では臨時工の下にあった。これはさすがにショックだった。大学での専攻は物理化学だったが、現場は赤々と炎え盛るカーパイド電炉(開放炉)であった。現在では考えようもないような埃だらけの工場。物理化学など思い出す余地もない。三交代勤務の現場で黙々と電炉を鉄棒でつつく仕事が何か月もつづいた。大きな送風機のモーターの据え付けベースを枕に仮眠する深夜勤で赤い汗をかく日々。これが労働者だと思ったから、メーデーには「聞け万国の労働者・・・」の歌詞を自力でガリ版刷りを造って仲間に配って気勢をあげるリーダーになった。私の上の臨時工のお兄ちゃんが、「じきに工務室へ行けるよ」と慰めてくれた。
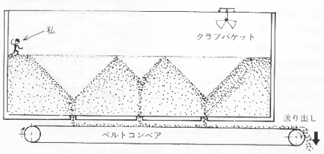
原料が吹出して、原料の粉で火傷することも何回かあった。吹出すのは細かい粉が通気性をわるくするためだ。このあたりが今にして考えれば粉との関わりの原点だった。故郷へ帰省したとき父から電炉の光線焼けの顔を見て「お前は土方をしとるらしいな」と言われた。その通りだった。
現場技術者という用語
やがて工務室に入ると、原料の品質管理を命じられた。当時工務室では猫も杓子も品質管理図を書いていた。流石統計的工程管理でデミング賞を取った会社だと思った。大学では統計的手法を勉強して、それで会社で仕事をしようと思っていたものだが、猫も杓子もやっているとなると反発したくなった。その頃、原料コークスの粒度が変化して曲線が大きく変化していた。粉が一部に集中するのは原料粒度にムラがあるからだ。結果だけ追っていては、はじまらない。「俺が解明してみせる」。このムラはどこから来るか、工程を炉前ホッパー、鬼歯ロールクラッシャーと逆にたどっていくと、ついに原料倉庫にたどりついた。暗い倉庫の上を走るベルトコンベアから見ると、下に巨大なコークスと石灰石の蟻地獄が口を開けていた。そのころ隣の工場で同じ場所で人身事故が発生した。蟻地獄に落ちた友人を助けようとして、三人が引き込まれ、翌日下方の抜き出し口に足が出るまで分からなかったという。「君そんな場所に登るな}と係長に叱られた。
そこで現象解明のために実際の倉庫の20分の一程の模型を手作りでつくって、粒度偏析の実験をはじめたのは、入社した年の冬であった。篩も全部手作りだった。標準篩なるものがあることも知ってはいたがこのあたりから私の粉体工学への道がはじまっていた。数年後に粒度偏析を社内研究発表会で報告し、さらにそれを、学会の印刷物で出した。随分あとのことだったが、その印刷物が当時の八幡製鉄へ伝わり、高炉の運転条件改善に役立ったことを知らされた。これが私の運命を左右する篩との始めての出会いだった。「現場技術者」という題目で星野芳郎が主宰する『技術論研究』という機関誌に書いたが、この用語も私が初だったといわれている。