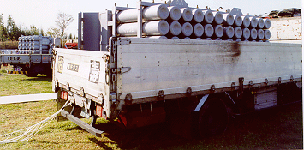 1992年11月20日午前ヘリウムボンベ満載のトラックが3台(280万円)河川敷に到着。
1992年11月20日午前ヘリウムボンベ満載のトラックが3台(280万円)河川敷に到着。リンク:金華山沖の海上で発見後の動き|多摩川でのハプニング|
近江八幡の河川敷での風景と鈴木さんのハプニング.までの経緯
彼は当初島根県仁摩町の仁摩サンドミュージアムからスタートするべく準備していた。それは平成4年9月12日午前11時発予定だった。そのために気象庁から入手した日本上空の高層気象図を持っていて、この頃はいちばん気象状態がよいと彼は考えていたようだ。その地図にはRinoというアメリカの地名も書き入れてあった。「気象庁も親切だよなー」と。島根へ来たとき彼は「赤い風船」のビデオを皆に見せた。赤い風船と仲良しになったパリの少年がイジメられて大事な風船を割られてしまったとき、パリ中の無数の赤い風船が集まってきて彼を救い青空高くつれて行くというストーリーだった。
ところが島根県の県警に許可を取るべく県警に行ってみるとそこに多摩川畔でのハプニングに立ちあった警官がいた。「しまった。先を越された」と彼の言。すでに仁摩町に手がまわっていた。
その頃、多摩川畔で彼にヘリウムを供給していたS社から「鈴木氏の行動にはついてゆけそうもないから、あなたからストップをかけてくれないか」と私に要請されていた。仁摩町でのストップで彼は次を考えている様子だったから、彼に無線の免許を取ることと、簡単な英会話の準備期間を持つよう要求した。彼は素直にそれを受け入れた。これで安心と思ったのは甘かった。11月16日に彼から電話があって「ヘリウムはO社が売ってくれる。琵琶湖干拓地で実戦さながらの300メートル上昇浮力テストをしたいので手伝ってくれないか。絶対に上昇はしない」と。酸素は別の会社から買うことにしたと。「やられた」。浮力テストだけとなれば断りようがない。
学生たちは鈴木氏が気に入っていたから文句なかった。以下は初公開の画像。
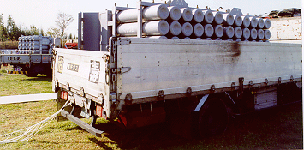 1992年11月20日午前ヘリウムボンベ満載のトラックが3台(280万円)河川敷に到着。
1992年11月20日午前ヘリウムボンベ満載のトラックが3台(280万円)河川敷に到着。
 バランス調整用錘は砂ではなく 沖縄焼酎200本単価5500円(これはナイロン袋に詰め替えてゴンドラに乗せたが、浮力不足で全部おろしてしまった)
バランス調整用錘は砂ではなく 沖縄焼酎200本単価5500円(これはナイロン袋に詰め替えてゴンドラに乗せたが、浮力不足で全部おろしてしまった)
 どこから手に入れたか無線緊急発信装置(左)と夜間ライト。別に某テレビの小型テレビカメラがついていた。彼の飛行中の様子を映すためという。
どこから手に入れたか無線緊急発信装置(左)と夜間ライト。別に某テレビの小型テレビカメラがついていた。彼の飛行中の様子を映すためという。
 ピエロの服装で準備中の鈴木さん
ピエロの服装で準備中の鈴木さん
 ヘリウム充填は簡単(下から上へ)これに2日半かかった。毎日弁当抜きだった。
ヘリウム充填は簡単(下から上へ)これに2日半かかった。毎日弁当抜きだった。
 22日繋留して浮力テスト(浮力が足りない)
22日繋留して浮力テスト(浮力が足りない)
計画では6m直径の主力風船6個,3m直径の補助風船26個の予定で、揚力800kgの計算だったが、実際には主力風船4個、補助風船若干個でヘリウムガスが不足してしまった。
だからこれ以上上昇しない。彼はあわてて持ち物を降ろすことにした。揚力調整用の焼酎をすべて捨て、最後には酸素ボンベも降ろしてようやくフワッと来た。彼はこのフワッに弱い。「行って来ます」「どこへ」「アメリカ」「冗談だろう、バカモン。上昇しないといったじゃないか。ウソツキ」「大丈夫です」もはや理性を失った人間と私は見た。「成功すれば冒険家だが、失敗すればバカモンだ。俺は知らんぞ」と言い放ってゴンドラを離れた。
かれこれしているうちに本当にフワリ。「アレヨ アレヨ」とあきれる見物人はただ呆然。浮揚直後テレビ局が携帯電話したとき、ヘリウムが少し漏れているが、大丈夫だ」と。だれも手を振らなかった。
堤防の桜にひっかかりそうになるくらいの低空飛行がスタートだったが、その後みるみるうちに東の空に消えた。それは5-10分間だったか、われに返って回りを見るとわれわれ同志社勢だけ。いつのまにか皆消えていた。晩秋の日は落ちて暗いあたりは一面ゴミの山。人気がなくなると河川敷の風は寒かった。「飛ぶ鳥後を汚すだな、止むおえん。焚き火して暖をとることになった。ゴミだけでは寒い。そうだあの焼酎に火をつけよう。河川敷故、火の高さも遠慮はいらない。河川敷の夜は真黒の闇、星空が実にきれいだった。

 海上保安庁が金華山沖で発見したときの写真では主力風船は2つだけ。どうして?あとで分かったことだが、充填中に風船からヘリウムもれがあったので、彼は粘着テープを貼って「これでok.
君は人にいうな」と口止めされたとは作業を手伝った学生が、半月ほどあとからボソリ。
海上保安庁が金華山沖で発見したときの写真では主力風船は2つだけ。どうして?あとで分かったことだが、充填中に風船からヘリウムもれがあったので、彼は粘着テープを貼って「これでok.
君は人にいうな」と口止めされたとは作業を手伝った学生が、半月ほどあとからボソリ。
この学生は「たったひとりの河川敷で鈴木さんがかわいそうだ」 と彼と共に2夜を過ごしたよしみで秘密を守ったという。「鈴木さんは飛行のため星座を研究していて詳しいんだ。たのしかった」と。
荷物を降ろしたとはいえまだまだ重いゴンドラ。もし高速道路や人家に墜落したら、大人身事故になりかねない。彼が勝手に行ったのだが気になる。彼の携帯電話番号を聞いていたからその夜何度も電話したが、スイッチを切っているらしく、アナウンスだけだった。不安な夜だった。
そして11月25日 東京駅に下車するやFテレビカメラが私に近づいて「金華山沖で鈴木さんが発見されました」と。「そう よかったね」としか言えなかった。