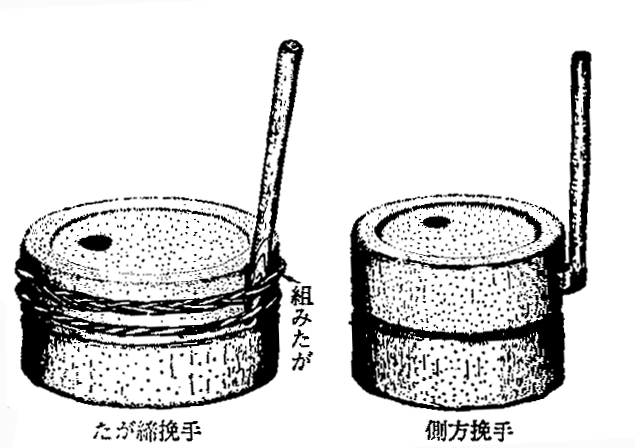
鈴鹿山系に沿って
石屋と桶屋の合作が生んだ傑作
石臼の産地を求めて、糸をたぐるように知人をたどって歩いた生の記録である。鈴鹿山系に沿って、特別な形態の石臼があるのはなぜ?
石臼の形態の謎
石目の目のパターソは6分画と8分画とが地域的に分布していると前章でのべたが、それらとならんで、もうひとつ大きた謎がある。それは図に示すように、大別して二種類の形態があることである。(そのほか局地的には特殊なものもあるがそれについては三章にのべた。
右の側方打込挽き手形式が大部分を占めるが、左のようにうに上臼に二つの竹の「たが」をはめた石日が日本列島の中央部(今までの調査では岐阜、三重、滋賀、京都および愛知の一部)に存在することである。しかもこの形態の臼は大部分の手挽き臼の直径が約一尺であるのにたいし、直径が一尺二寸と、ふつうよりひとまわり大きいことも注目される。さらに詳しくみると、この「たが」の組み方がまた特殊である。次ぺージの写真は典型的な例で、上臼には上側に太い「たが」、その下に細い「たが」があるが、太い方の「たが」をよくみると、いわゆる「組みたが」になっている。上下とも組たがのこともある。
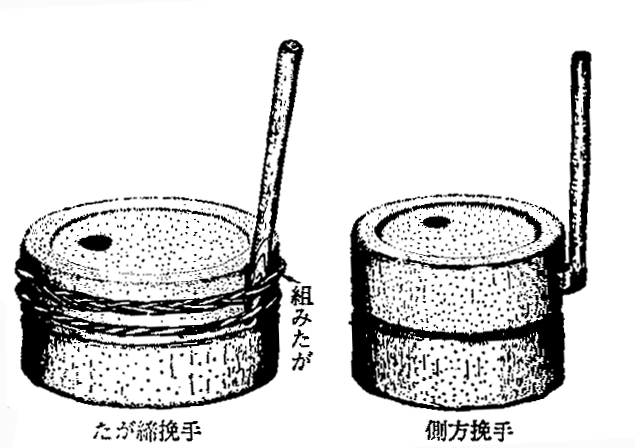
これは石臼が熱練した桶屋との合作であることを示している。たがを使うと、挽き手を非常に強く保持できる。とくに組みたがを使ったのは、強く打込んでもゆるまないためであるが、さらに組みたがには装飾的効果もある。これに比べ側方打込式は、上臼の側面に掘った穴に打込むだけであるから、穴のあけ方がまずいとぬけやすい。組みたがを使えば確かに便利で、桶屋と石屋の技術がドッキソグしたと考えることができる。ところが、この方式がこの地方の発明だとはにわかに断言できない。さいきん韓国の延世大学校家政キムエイチユ大学の金策沫教授がお送りくださった写真によると六分画と八分画が、お隣りの韓国にも存在することがわかったが、たが付きもある。
さらによくみるど組みたがにはなっていない。これは最近、観光用に作られたソウルから約五〇 Ɠのところにある民俗村のもので、新しく修理したものらしく、組みたががないのかどうか、まだ確言はできない。もし大陸から伝来したものなら、どうして日本ではこの限られた地方にだけ残っているのであろうか?以上のような謎を追って、この目が見られる鈴鹿山系に沿う地方をうろつくことになった。
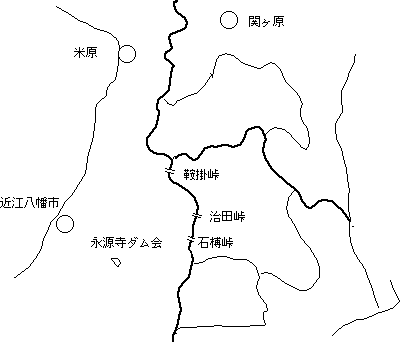
石臼のふるさとは何処?
次の地図をみよう。新幹線の大雪で名高い米原、関ケ原の南に鈴鹿山系が横たわって、東海地方と近畿地方を分断している。筆者の郷里は美濃、伊勢、近江の三国の境が接する付近の上石津町下山にある。「たが付き」の花こう岩製の石臼に子供の頃からなじんでいたものだが、全国の石臼を訪ねてあるいてみて、たが付きのものは他の地方ではあまり見かけない。ところで最近、粉体の空気輸送工学で有名な静岡大学の狩野武先生から、琵琶湖の北に.ある先生の郷里にあった石臼の写真をいただいたし、筆者も八日市の石塔寺の近くでもみつけている。また抹茶臼の研究者である茶業研の大西市造さんからは、奥さんの実家である三重県阿山郡の石臼.の写真をいただいたがいづれも全く同じ形態である。「たが付き」の分布の中心はどうも鈴鹿山系の近傍にあることは確からしい。
それより西になると、いまのところ京都の大原でみている。北は敦賀までのびているかどうか不明。東は全く不明だが、静岡西部でみつかっている。しかしこれは上、下とも組みたがではあるが、小さいたがであり直径は一尺で石質もちがう。これはまた別系統なのかもしれない。東西南北の境は今後の探求にまたねば ならない。静岡市立登呂博物館の大村和男氏の報告書に.よると、静岡市では八と六分画が混在し、たが付きはないようである。ではこの地方独特の臼のふるさとは、どこなのだろうか。それは石の産地と石屋を探せばよい。伊勢の国、石榑だということになった。
上石津の臼
まず筆者の郷里、上石津町の臼を確認するため、近くの家の臼を片っぱしからみせてもらうことにした。しかしどれも同じ形式で変ったものは出てこたかった。しかし、たがの入れ方はいろいろで、上下とも組みたがにした頑丈たものもあれぼ、上下とも組たがのもあった。箍(たが)が弱いのは挽手が抜けやすかつたようである。呈く打込み・くさびを入れて容易にぬけないようにしたのもあり、いろいろの工夫がうかがわれたがが完全に残つているのは、今も物置隻に入つているもので、たいていのうちでは外に放りだして、たがは全くなくなつていることが多かった。ものもちのいい家とそうでない家とのちがいである。ひとつおもしろいのがみつかつた。ふつう芯棒は下臼にはめこんであり、上臼に凹みがある。ところがその逆のがあつた。これはまさに男性上位の臼であり、あらためてその家の主人の権威を想ってみたがこれは全くの特例にすぎない。挽き手は少し外向きに突き出ている方がひきやすいようである。上石津町の西の端、筆者の実家から一里ほど山あいの谷川にそって入った谷間の村落、大字、時山Lへもいつてみた。ここはかなり秘境で、さっと回っただけでもいくっかみっか、そこではまだ縁側に傭えつけてあり、最近ひいた形跡のある臼もあった。ポリバケツきと共存している姿は、いかにも奇妙なとり合せであったが、なにか生活の臭いが残つている石臼に出あつたのははじめてで、そばに大野伴睦の胸像があるのもいかにも地方的色彩が濃く、まだここでは過去のものとはなっていなかったのである。竹のたがは、いままで見たうで、最も立派なものであり、その美しさにしばらく見とれてしまった。その時家人は留守だったが、あとで聞いたところによるとこの臼は滋賀県の「五僧(ごそ)」を経て運ばれたもので、今から五十年くらい前にここの主人がまだ12才の頃、山道を「せた(ショイコのこと)」で背負ってきたが実に辛かったと話された。後で述べるように大君ケ畑(おじがはた)へは石榑から入っていることは確かだから、この臼はまちがいなく石榑の臼ということになる。
まだ生活の臭いが残っている石臼(上石津町時山川添時男宅の臼)*
"大字「上(かみ)」では昔近くの小川にあったという水車小屋の二尺臼が保存されていた。また今は田んぼになっている南側の土地にあった、豆腐屋の臼もおいてあった。これは水に浸した大豆を供給するため、供給口はじょうご状にひらいたものであった(十一章でのべるように、これは酉洋の方式である)。
もうひとつ、大字下山に。地蔵寺という寺があり、そこにも大きな二尺臼があった。ここの庵主(あんじゅ)さんの話によると前住職は田光(たびか)の石屋の出身なので、そこからもってきたものらしく、下臼の底が丸く加工してあるのは、どうも灯籠にしようと思ったらしい。これはモミスリ用といわれ目が粗いという。
石臼のふるさと石榑探訪
夢に.までみた石屋のふるさと「石榑」へ、四月末(昭五〇)のとび石連休を利用して出かけることにたった。途中、三重県員弁郡(いなぺ)本郷および東員町長深の松下繁さん方に、立寄ったが、いずれも上石津町と同じ形態のものであり、とくに松下さんのは、物置に入っていたので「たが」も完全であった。石は「菰野」の奥郷石(おくごう)(花こう)岩で石榑石のなかま)という。
石榑には筆者らと同郷のれているので訪ねてみた。貯金の精算のまっ最中で、札束をめくっておられた。われわれのおしゃべりに応じながらなので、なかなか計算が合わたい様子だった。土蔵に案内され、りっぱな宇治石で漆ぬりのみごとな抹茶臼と、直径350ʔの典型的な石榑の挽き臼をみせてもらった。岩花局長の知り合いで天理教朝華分教会の方を訪ねたたが不在、ここで石目のことならと、菰野町田光の石慶石材店を紹介された。ここの主人、水谷秋さんは終戦直後のころ、石臼づくりの経験があり、いろいろお話を聞くことができた。昔は石臼一個の工数は二人であった。つまり一人で二日かかるわけだが、昔の労働時間は長かったから、今だとその倍以上はかかることになる(参考までに、石の会の諸君が調査した佐渡の目は砂岩なので一人、京都白川の石屋さんは白川石で三人)。終戦直後、目とりは大変ボロイ商売で、一面分米一升、上下臼で二升であって、夜なべ仕事にできたという。
また前出の「大君ケ畑」から石榑へ臼を買いにきたそうである。これで江州への交易路は確認できたわけだ。石榑石はキメがあらく少しやわらかでもろいから、墓石や建材などには適さないが臼の目にはよい。石英の結晶が目立ち、雨にぬれると黒っぽくみえる。また表層部は酸化して赤っぽい。古くたった石臼もこの酸化による赤味がかっているのが特徴である。ききたいことは一っぱいあったが、突然の訪問なので再会を約して失礼することにした。水谷さんには近いうちに石臼一式をつくっていただく約束をした(この石臼は現在臼類資料室で保管している)。
風吹けば桶屋がもうかる
ところでこの地方の石臼には竹の「たが」がつきものだから、桶屋がいなくては話にたらない。次は桶屋探しだ。水谷さんに紹介していただいた梅山さんという桶屋さんを訪ねると、高齢なので二年程前にやめられ、道具もっかっていないということで、員弁郡北勢町大字中山四-11の武藤定太郎さんを紹介していただいた。武藤さん宅までたどりっいたときはもう午後七時をすぎていたが、家の前までくると、シヨーウィソドウには見事な桶が山とつまれ、桶屋の道具が整然とならんだ仕事場が見えたので、小おどりして喜んだ。武藤さん夫妻は突然の訪間者を快く招じ入れてくださり、いろいろお話をきくことができた。目の前にはみごとな「祝いびつ」があった。これにはまぎれもなく「組みたが」が使ってある。この祝いびつは婚礼や誕生祝いに、親戚へ赤飯や餅を入れてもってゆく桶である。濃い親戚へは二個、うすい親戚へは一つもってゆく。これを特製の風呂敷につつみ、棒で二人で担いでゆく。赤飯だと山もりに入れ、南天の葉をはさんでふたをする。(ちなみに筆者の郷里では重箱(じゆうばこ)であるが、伊勢の親戚へはやはりこの祝い櫃でもってゆかねばならぬ。「伊勢櫃」といい、伊勢に親戚がある家では必ずもっている)。
この組箍のことをこの地方では「おいね輪」という。「おいねる」とは背負うことである。この箍は2本の竹を用い、4回まわして締めるから8本かかっていることになる。ちょっと見るとどこが始めでどこが終わりかわからないが、最後に親株の下に.見えないように留めるのが技術である。生竹を割ったものからこの竹をつくることを「竹をあげる」といい、「組みたが」は中凸で七対三のところに山があり、このことに.よって、たがのふくらみしんをつけている。もっとふくらますときは裏に芯を入れる方法もある。粉挽き臼の受鉢に.つかう「はんぎり」は、石臼のまわりに手が入るように一尺八寸径ので四升用、二尺径ので六升用になる。桶屋は昔は員弁郡だけで60人いたが、今は昔の技術を伝えているのはここだけに.なってしまった。昔は生活の中で桶はいろいろに用いられ洗桶、茶だる(現在の水筒やマホービソ代り)、手桶、つるべ、おかわ(便器)などたくさんあった。久しい間探しあぐねていた「組みたが」。ときにはもうこれを作る人はいないのではないかと、半ばあきらめかけたりしたのだったが、今なお健在で生きている伝統技術に.目のあたり接することができて、筆者らはもう夢中であった。聞きたいことは山程あったし、武藤さんのお話もっきなかったが、夜おそくでもあり、あらためて機会をっくり、できれば手さばきも見せてもらい、さらにはその伝統をつぐことができる人をみつけるところまでゆきたいと念じつつ、お別れした。
「風吹けば桶屋がもうかる」という諺があるが、粉と桶屋のつたがりもまたおもしろい。(この探訪には伯父の大橋政治、いとこの大橋正則らが同行した。)
三輪茂雄著『増補 石臼の謎』(クオリ刊,1994)p.63-78)より