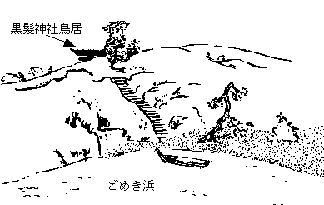
「昔、能登国・仁岸の郷の渡瀬という部落に、次郎助という百姓家があった。次郎助の娘お小夜は家が大変貧乏だったので近くの女郎屋に遊女として売られたが、その後、江戸の吉原まで流れてゆき、吉原いちの売れっこ花魅になった。義理にかたく、情に厚く、芸に秀でていたので、一目千両の花魁お小夜と、もてはやされた。そのうち同郷の誼で、能登輪島の重蔵という船乗りが、お小夜のもとへ通いつめ、お小夜はこよなく重蔵に魅かれた。だがあるとき重蔵は輪島に帰ったまま、ばったり寄りつかなくなってしまった。不審に思ったお小夜が輪島の重蔵のもとへ行ってみると、すでに他の女がいた。愛憎半ばする心で故郷の靱地へ帰ったお小夜は、海に身を投げて自らの命を絶ってしまった。その怨念が砂浜にのりうつって、砂の上を歩くと泣き声に似た音をたてるようになった」剣地の方言で、泣くことを「ごめく」というので、村人たちはこの浜を「泣き浜」と呼ぶようになった。「村人たちは不爛に思って、剣地海岸が一目で見渡せる渡瀬に小さな祠を建ててお小夜の霊を慰めたが、沖に白帆が見えるたぴに暴風を起こして大時化となり、そのつど遭難させた。お小夜の亡霊が船をとめる、それではかなわぬと、村人は海の見えない山の上代に移した。それがいまに残る黒髪神社である」(上図で鳥居だけ見える)。以上は定梶昭三さん(門前町剣地)から聞いたお小夜伝説である。次のような話もある。「重蔵はこの浜から船出したまま、いつまでたっても帰ってこない。お小夜は恋いこがれ、毎日、この浜へ出て、浜の岩(浜の中央、やや南寄りにある奇岩)にのぼり、「重蔵恋しや」と嘆き、沖合いの船を眺めて待っていたが、とうとう病にかかり死んでしまった。やがて帰ってきた重蔵は、お小夜の死を聞き、浜を涙でぬらした。それ以来、浜の砂がごめくようになった」。ところで、この伝説には琴が出てこないのに、現在の地図や案内書にはごめき浜とならんで「琴ケ浜」と書いているのはなぜだろうか。定梶さんの話によるとこうである。「これは近年つけられたもので、私の父・定梶宗次が昭和初年に付けたと聞いております」。伝承に忠実であるためにも、泣き浜(ごめきはま)というすばらしい名称を残したいものだ。
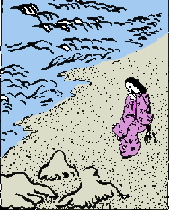 お小夜悲恋物語
お小夜悲恋物語 お小夜の黒髪を祭った黒髪神社
お小夜の黒髪を祭った黒髪神社